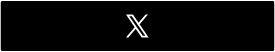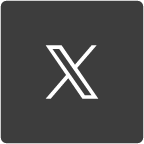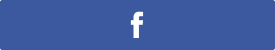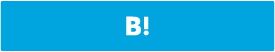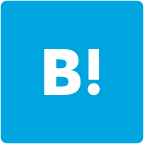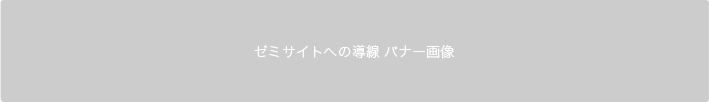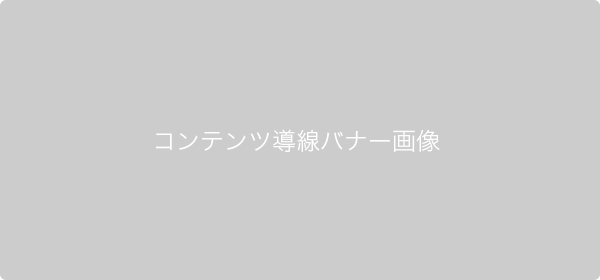いつ、どう伝える? いのちと死【前編】死生観を育む「物語」と「棚上げ」
お気に入りに登録
いのちの大切さとは? 死ぬとはどういうことなのか? 子どもの「いのちと死」への疑問や不安に、保護者はどう応えていけばよいのでしょう。小中学生を中心とした「いのちの教育」の研究者であり、スクールカウンセラーとしても活動されている近藤卓先生にお話を伺いました。
「いのちと死」について、子どもはどのように理解しているのでしょう。ここでは発達段階別に、死生観の理解の在り方と関わり方を紹介します。
◆5歳未満:「ずっと寝ているね」
死んだら動かなくなることはわかりますが、生き返ることがないことは理解していません。長い間寝ているだけで、いつか目が覚める……と信じている場合も多いようです。
この時期の子どもは、虫を踏んで死なせるなど、一見残酷な行為をすることがあります。しかし、これは動いていたものが動かなくなっていくことを不思議に思っているだけ。好奇心の表れであることがほとんどなので、あまり神経質にならないほうがよいでしょう。
◆5~9歳:「死ぬとお星さまになるんだよ」 死んだら生き返らないことは理解するようになるものの、誰もがいずれ死ぬという実感は薄いようです。また、「死ぬと別のおうちで暮らすことになる」といった表現をする子どももいます。
死んだら生き返らないことは理解するようになるものの、誰もがいずれ死ぬという実感は薄いようです。また、「死ぬと別のおうちで暮らすことになる」といった表現をする子どももいます。
この時期までは、「死」について尋ねられることがあったとしても「死ぬとお星さまになって、空からみんなを見守っているんだよ」など、安心につながる「物語」を用意してあげましょう。「子どもだまし」と感じられるかもしれませんが、これは「サンタなんていないよ」とわざわざ告げる必要がないのと同じ。やがてそうじゃなかったとわかることでも、この時期の子どもには必要なお話なのです。
◆10歳~:「死んだらどうなるの?」
自分を含めて、死は避けられないと理解します。学校の授業や友達との会話、親戚やペットの死などの経験から、いのちや死を強く意識する「いのちの体験」をし、私たちと同じ死生観の基本が成立します。
死への恐怖を感じるようになる時期ですが、「パパもママもまだまだ死なないから、あなたも大丈夫!」といった、保護者からの力強いメッセージが救いにつながります。
◆思春期以降:「いのちと死に、答えはないんだ」
死んだら動かない(不動性)、戻らない(不可逆性)、避けられない(不可避性)を経て、いのちと死について真剣に自問自答し、「どうせ死ぬのに、なぜ生きているのだろう」など、本当に悩む時期が訪れます。
保護者自身、「この問題には私もまだ答えが出ていない。だから、時々考えるようにしている」と、同じモヤモヤを抱えていることを共有してよいと思います。私はこの状態を「棚上げ」と呼んでいます。ふだんは使わないけれど、捨てることもできないやっかいな荷物を「見える場所に棚上げして時々見つめ直す」という意味です。
「死んだらどうなるの?」や「人はなぜ死ぬの?」といった根源的な問いには、明確な答えはありません。しかし「わからない」と正直に答えて「棚上げ」をすすめるのは、大人と同じ思考がほぼできるようになる思春期以降にしたほうがよいでしょう。それまでは、「お星さまになった」などの「物語」を聞かせて、死への不安を取り除き、生きる希望へと導いてあげましょう。
後編では、いのちの大切さがわかる子どもについて考えます。