友達の輪に入れない……保育園や幼稚園の先生へ相談するタイミングは?
- 育児・子育て
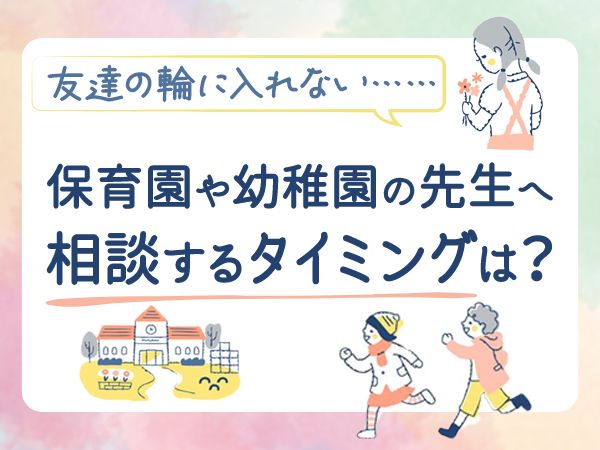
「うちの子、いつも一人で遊んでいる……」と感じて、子どもの友達関係が心配になる保護者のかたは多いのではないでしょうか? 気になることがある時は、保育園や幼稚園の先生に気軽に相談して大丈夫です。その時に、先生へ相談するタイミングやコツを知っておくことで、よりお子さまの園での様子を知ることができます。
今回は、臨床心理士・公認心理師である高木紀子先生に、子どもの遊びと友達との関わり方や先生への相談のタイミングやコツについてお話を伺いました。
【年齢別】子どもの遊びと友達との関わり方

子どもの遊びは、一人遊びから始まり、時間をかけて友達と遊んだりルールのある遊びをしたりするようになります。まずは、年齢別に友達との遊び方や関わり方の目安を見てみましょう。
【1~2歳ごろまで】
1~2歳ごろは、「一人遊び」を行います。友達とのやり取りがまったくないわけではありませんが、長時間続くことはなく、一人で何かに没頭して遊ぶ時期です。
【2~3歳ごろ】
2歳ごろからは、「傍観遊び」が始まります。傍観遊びとは、友達が遊んでいる様子を見るものの、一緒には遊ばず一人で遊ぶことです。一人遊びや傍観遊びを行いながら、次第に「並行遊び(平行遊び)」が始まります。
平行遊びとは、友達の隣で同じ遊びをするものの、子ども同士の関わりが少ない遊びです。たとえば、隣の子が「ガタンゴトン」と言いながら電車のおもちゃで遊んでいるので、自分も電車を持ちながら「ガタンゴトン」と言ってはみるけれど、二人が共同の遊びをしているわけではなく、別々に遊んでいる状態を指します。
このように、2歳ごろは友達を意識し、興味を持つようになる時期といえます。
【3~4歳(年少)】
3~4歳の年少くらいの時期から、「連合遊び」が始まります。連合遊びとは、平行遊びより友達とやり取りをしながら遊びますが、ルールなどは共有しない遊びです。
たとえば、子どもが集まってサッカーをしているとしても、1人はゴールを目指している、もう1人はただボールを蹴ってパスの出し合いをしているというように、同じ目標やルールを持っているわけではないものの、一緒にいることを楽しんでいる遊びです。
【4~5歳(年中)以降】
4歳ぐらいからは、自分と他人との違いがわかるようになり、集団での遊びが楽しくなっていきます。そのため、ルールや役割分担があり、友達とコミュニケーションを取りながら遊ぶ「協同遊び」が見られるようになります。
このように、子どもの遊びは「一人遊び」から始まり、成長と共に、遊びの中で友達との関わりが少しずつ増えていくのです。ただ、上記の友達との関わり方はあくまでも目安で、生まれてからの環境や性格によって大きな個人差があります。
もし年齢に応じた遊びをしていなくても、心配しすぎる必要はないので安心してくださいね。
そもそも「友達の輪」に入らないとだめ?

そもそも「友達の輪」に入らないとだめなのでしょうか? 「友達の輪に入っていない状態」には、大きく分けて2種類あります。
(1)一人で没頭したい遊びがある
「ブロックで作りたいものがある」「一人でけん玉がしたい」など、やりたいことがはっきりしていて、一人で夢中になって遊んでいる場合、「友達の輪に入れていない」のではなく、「今は友達を必要としていない」という状況です。
一人遊びに没頭しているのなら、友達の輪に入る必要はありません。「一人遊びが多くて、社会性が低いのかしら……?」と思われるかもしれませんが、「没頭して遊ぶことは大切なこと」と思ってみてあげましょう。
(2)友達と遊びたいけれどうまく遊べていない
友達と遊びたいけれどうまく遊べていないという時もあるでしょう。「うちの子大丈夫かしら……」と心配になるかもしれませんが、友達の輪に入れていないのには何か理由があるはずです。
たとえば……
・「(遊びに)入れて!」と言えなかった
・「入れて!」と言ったタイミングが悪くうまく遊べなかった
などがあります。
(1)と(2)の理由を踏まえ、「友達の輪に必ず入らないとだめ」ということはありません。もしお子さまが友達の輪に入れず困っている時は、保護者のかたや先生のフォローが必要な時もあるでしょう。
友達の輪に入れていない時の、先生への相談のタイミングは?

ここで、お子さまが友達の輪に入れず困っている時の、先生への相談のタイミングについて見てみましょう。
まずはお子さまに話を聞いてみる
まずは、お子さまの話をよく聞くことが大切です。たとえば、「遊ぼって言ったらだめって言われた」とお子さまから聞いた場合、「何をしようとしてたの?」「みんなは何をしてたの?」など状況を詳しく聞いてみましょう。
気を付けたいのは、「仲間に入れてもらえなかった」という子どもの発言に、過剰に反応してしまうことです。内容をよく聞く前に、重く受け止め「一大事だ」という雰囲気を出してしまうと、お子さまは「この話はママ(パパ)の興味を引く話題なんだ」と思い、話を大げさに話したり本当ではない話をしてしまったりすることがあります。
まずは、中立・公平な立場で淡々と内容を聞くのがおすすめです。
気になる点があれば、先生に相談してみる
お子さまに聞いた内容を踏まえて、気になる点があった時は「子どもが○○って言ってるのですが、実際はどうかご存じですか?」のように聞いてみてください。
先生が見ていた場合は、「意地悪で入れてあげなかったのではなく、トランプ遊びがもう始まっていたので、友達は『(今は)だめだよ』と言っただけなんです」のように、事実を話してくれるでしょう。
先生の話を聞くと、もしかしたらお子さまの理解とその場の事実が異なる場合もあるかもしれません。また、先生が見ていなかった場合でも、今後は気を付けて様子を見てくれるでしょう。
お子さまの話から、我が子がいつも一人で遊んでいるのか気になった時も、先生に「いつも一人で遊んでいますか?」と聞いてみて大丈夫です。お子さまの園での様子を教えてもらえると、安心できますね。
子どもの様子がいつもと違うと感じたら
園での話を聞いた時や普段の生活での様子を見ていて
・そわそわしていて落ち着かない
・叱られている口調になる
・妙なタイミングで真顔になっている
・あまり笑わなくなった
・怒りっぽくなった
・食欲がない
・理由が思い当たらない体の痛みを訴える
など、「いつもと違うかも」と感じた時は、先生に相談してもいいかもしれません。なぜ様子がいつもと違うのか、先生が原因を見つけてくれる可能性があります。
先生に質問する時のコツ

先生は、大勢の子どもを日々見ています。そのため、お子さまの様子をしっかり知りたい時は、質問の仕方を工夫するとより詳しい情報が得られるでしょう。
まずは問題提起だけしてみる
相談は、その場で答えをもらうより、後日に持ち越したほうが、総合的な返事がもらえる可能性があります。
たとえば、「うちの子、いつも一人で遊んでいるみたいなんですけど……」と相談する場合、続けて「園での様子を教えてください」と聞くと、先生は今持っている情報だけを保護者のかたに伝えることになります。
しかし「少し見ておいてもらえますか?」や「また後日お話を聞かせてください」などと伝えると、その後お子さまの様子をしっかり見てくれたうえで回答してくれるでしょう。
よりお子さまの様子を知りたい時は、即答を求めず、先生に情報収集をしてもらう期間を設けたほうが、より詳しい様子が得られます。
連絡帳や連絡アプリを利用する
園バス登園などで先生と顔を合わせて話す機会がない場合、連絡帳や連絡アプリを利用するのもよいでしょう。
先生が連絡帳などを確認してから、保護者のかたに報告をするまで時間が取れるため、園でのお子さまの様子を観察しやすく、先生間同士の情報共有や引き継ぎも行えます。そのため、より正確なお子さまの情報が得られる可能性が高いです。
友達の輪に入れていない我が子に保護者のかたができること
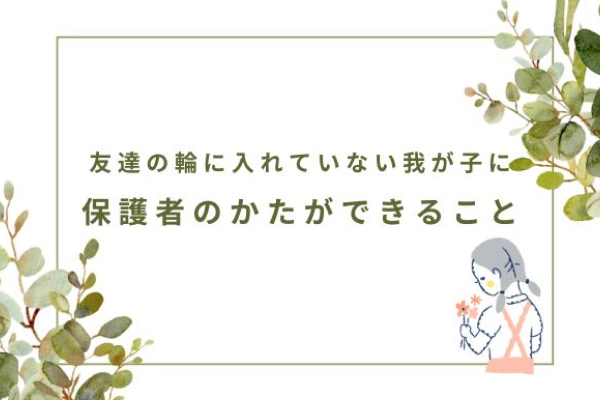
子どもの話をよく聞いてからアドバイスを
まずは、子どもが困っているのが何なのかを知ることから始めましょう。
「『入れて』や『遊ぼう』が言えていない」のか、「『入れて』や『遊ぼう』を言っても入れてもらえない」のかによって、アドバイスは異なるからです。
実は「いじわるで入れてもらえない」というパターンより、「タイミングが悪くて入れない」というパターンのほうが多くあります。
たとえば……
・鬼ごっこの鬼が決まったあとに鬼をやりたがって入れない
・やりたい楽器が3つしかなく、4人目になってしまって遊べなかった
などです。
お子さまの話をよく聞いたあとに、困りごとに対してアドバイスができるとよいですね。
先生にフォローをお願いしてみても◎
子どもが遊びに入るタイミングで困っている場合、おうちでアドバイスするのは難しいかもしれません。そんな時は、先生にフォローをお願いするのもよいでしょう。
お子さまと友達との橋渡し役として、先生はうまく立ち回ってくれるはずです。一度仲間に入れると、次の遊びの時もスムーズに仲間に入れることはよくあります。
友達関係で悩んでいたら気分を変えて楽しむことも大切
お子さまが、友達関係で悩んだり、寂しがったりする様子が見られたら、家族でいろいろな遊びや体験などをして楽しむのもおすすめです。遊びや体験をとおして、幼稚園や保育園以外で気分を変えて楽しむことが、きっとリフレッシュになるでしょう。
また、友達は一人だけではないので、うまくいかなかったら一度離れてみて、他の友達に目を向けてみるよう促すのもいいですね。
まとめ & 実践 TIPS

「友達の輪に入れていない」と感じても、それが「一人遊びに没頭している」のか「友達の輪に入りたいけれど入れていない」のかによって、対応は異なります。まずは、お子さまが何に困っているのかよく聞くことから始めましょう。気になる点がある時は、先生に気軽に相談して大丈夫です。子どもの友達との関わり方や遊び方には個人差があるため、心配しすぎず見守れるといいですね。
編集協力/海田幹子、Cue`s inc.
- 育児・子育て















