【体験談】おすすめ勉強法!5つのお悩み別に効果的な方法&NG勉強法をプロが解説
- 学習

勉強には悩みが付きもの。
「なかなか勉強に取りかかれない」
「取りかかっても集中できない」などに加え、お子さまの勉強法が気になる保護者のかたもいらっしゃることと思います。
そこで今回は、「進研ゼミ小学講座」の「赤ペン先生」に聞いた、お悩み別のおすすめの勉強法と、やりがちなNG勉強法を紹介します。
あわせて、合格した大学生の「結果が出た!」勉強法の体験談と、やる気を引き出すための保護者のサポート法もご紹介します。
5つのお悩み別 おすすめ勉強法
お悩み1:気が散って集中力が続かない
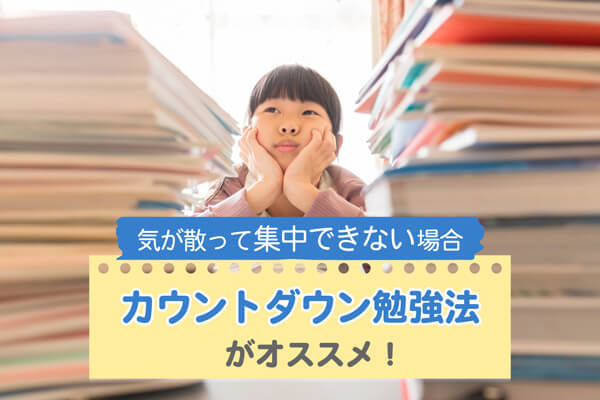
10分だけ集中する「カウントダウン勉強法」がオススメです。
大人でも集中し続けることは難しいもの。小学生ではなおさらです。一般に、集中力が続くのは5〜10分程度。学校でも、特に低学年では、10分セットで授業を組み立てる工夫が行われているほどです。
まずは、10分集中できていればOKととらえ、10分集中を積み重ねていくことを意識しましょう。そのためにおすすめなのが、タイマーを活用したカウントダウン勉強法です。
カウントダウン勉強法
<方法>
- 勉強する時間を決める。勉強時間全体の目安は学年×10分。そこから、1回の勉強時間を決める。
- タイマーをかける。
- 時間が来たら、5〜10分程度の休憩を入れる。
例)小学4年生の場合 4×10=40分 1回の勉強時間を10分×4セットに設定。
<コツ&注意点>
- 1日で勉強する内容は、あらかじめ決めておきましょう。早く終わらせようという意識が高まって、集中しやすくなります。
- タイマーに従うことを厳密にしすぎなくてOK。きちきちしすぎると、段々と疲れてきてしまうことも。集中して取り組めていれば、早めに終わっても、延長してもOKというくらいのスタンスで大丈夫です。
カウントダウン勉強法に繰り返し取り組むことで、自分なりの集中のリズムや、勉強の仕方がわかってきます。自分に合った勉強計画も立てやすくなりますよ。
【体験談】合格した先輩の勉強法
- 5分勉強したら、5分休憩するを繰り返す。いつの間にか勉強時間のほうが長くなっていた。(千葉工業大学・未来変革科学部)
お悩み2:暗記ができない
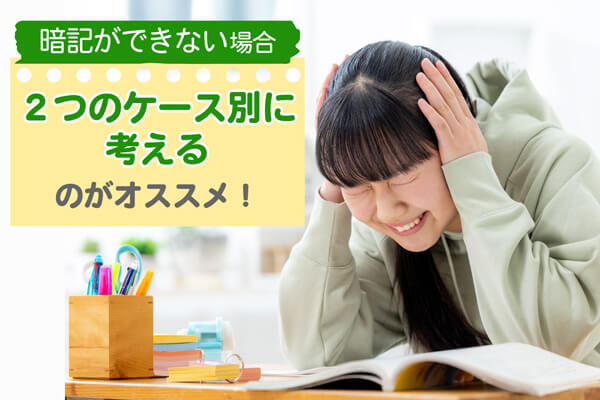
暗記が苦手という場合は、二つのケースが考えられます。一つ目は、機械的に覚えることが苦手というケース、二つ目は一気にたくさん覚えようとするケースです。それぞれ、おすすめの勉強法を紹介します。
ケース①機械的に覚えることが苦手な場合は、何かと結び付けて覚える
暗記は、この英単語はこの意味というように、1対1で機械的に覚えていくことも必要です。しかし、それだけでは単調に感じて、覚えづらいと感じることも。そんな場合は、意味付けをしやすい工夫がおすすめです。
たとえば、英単語であれば自分の部屋や1日のスケジュールなど日常と結び付けて覚えるのもいいですね。漢字であれば、「圧巻のコンサートだった」というように、身近に感じられて自分がうれしくなるような例文を作って覚えるのもおすすめです。
ケース②一気にたくさん覚えようとする場合は、反復学習と暗記が楽しくなる工夫を
1回で10個も20個も暗記項目を覚えるのは難しいものです。暗記は、繰り返し取り組むことで少しずつ覚えていくことが基本。ゆっくりでもいいので、繰り返すことが大切です。脳は、何度も触れる情報は大切なものだと認識し、記憶しようとすると言われています。
とはいえ、暗記は先が見えないように感じることもあるもの。そうならないコツは、「これだけがんばった」と努力や成長を目に見える形にすることです。次のようなアイデアを取り入れてみてくださいね。
- 覚えた数だけシールを貼る
- 単語帳の目次などに、取り組んだ回数を記入する
- 暗記の確認に何分かかったかを計測。過去の自分と現在の自分とでタイムレースをする
【体験談】合格した先輩の勉強法
- 夜に暗記をする習慣を付けた。暗記は夜にやったほうがよいことは科学的に証明されているからです。時間が空きやすいので、習慣付けがしやすかったです。(東北大学・文学部)
- 覚えたいこと、英単語や間違えた問題などを小さい紙に書いてポケットに常に入れておく。ちょっとしたスキマ時間や、信号待ちなどの時間でも見ることができて、よかったと思う。(秋田大学・理工学部)
お悩み3:なかなか勉強に取りかかれない

勉強しようと思っても、なかなか机に向かえない。気が重くて後回しにしてしまう。そんな場合は、無理なく始められる次の2つのアイデアがおすすめです。
アイデア①取りかかりのハードルを下げる
勉強に取りかかるには、簡単でサクサク終わる内容から始めることがポイント。5分程度で終わるドリルや、あまり考えなくていい音読などで、勉強へのハードルを下げましょう。いいウォーミングアップとなり、勉強へのエンジンがかかるはずです。
アイデア②「ついで勉強」を取り入れる
「勉強するぞ」と時間をつくるのではなく、何かのついでに勉強もしてしまうというゆるさで勉強を始めてみましょう。歯磨きのついでに英単語チェック、お風呂の前はドリル1ページなど、今の習慣にプラスするのがポイントです。
「ついで勉強」のタイミングを決めたら、1週間は続けてみてください。1週間続けると習慣になって、やらないと気持ち悪くなるほどになる可能性も。保護者のかたは1週間は続けられるよう、声かけでサポートしてあげられるといいですね。
【体験談】合格した先輩の勉強法
- すぐに終わる課題や好きな教科の勉強から始める。やる気になって難しい課題や苦手な教科の勉強も始められました。(徳島大学・総合科学部)
- スマホをリビングに置いて、自分の部屋で静かに勉強する。勉強はまずはやり始めないと続けるのは無理なので、まずは始めましょう。(千葉大学・法政経学部)
- ご飯を食べ終わったら、とりあえず勉強机に座って毎日少しでも勉強をするようにした。(長崎県立大学・国際社会学部)
お悩み4:勉強しているのに結果が出ない……
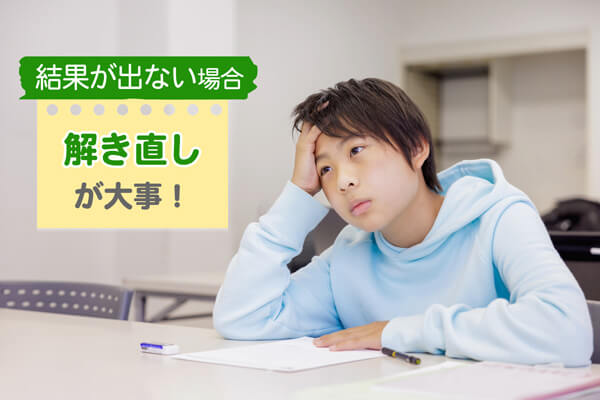
勉強をやってもやっても成果が出ないことは、つらいもの。「努力したって報われない……」とあきらめそうになってしまうケースもあるでしょう。こういった場合は、「1回解くだけ」の「やりっ放し勉強法」になっていないか、振り返ってみてください。
勉強は、1回解くだけではなく、前に間違えた問題を解き直したり、復習したりすることが大切。「前よりわかったかも」「この間は間違えたけれど、今回は解けた」といった成長実感を覚えることで、勉強が楽しいと思えるようになります。過去の自分に勝つぞと挑むつもりで、解き直しに取り組んでみてください。
また、小学校低学年などではバツがつくのを嫌がって丸付けを拒否したり、バツを見返したりすることが厳しいケースも。その場合は、バツを付けるのではなく、青で丸を付けるといった工夫がオススメですよ。
【体験談】合格した先輩の勉強法
- 間違えた問題のみ、何度も繰り返し解いていました。わからなかった問題に印を付け、1日のうちに何度か解く、1週間以内にまた何度か解く……といったことを繰り返して、効率よく定着させることができました。(神戸大学・医学部)
お悩み5:苦手科目をがんばれない
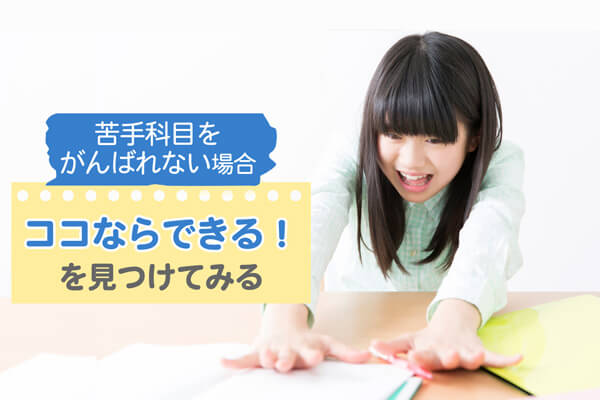
苦手科目は、勉強への意欲も上がりづらいもの。まずは、苦手科目の中でも、「ココならできる」点を見つけてみましょう。苦手科目とはいえ、じつは「ココなら解ける」「他よりも解きやすい」単元なら、勉強が進みやすくなりますよ。
また、どこができて、どこができないのかを明らかにすることで、苦手科目のつまずきの原因も見えてきます。苦手な部分がどこかわかるだけでも、人に質問しやすくなりますよ。
苦手科目について、小学生で特に注意したいのは、計算が苦手なケース。計算は、どんな単元のどんな問題を解くときにも関わってくるため、苦手解消が遅くなればなるほど苦労します。
ポイントは、今のつまずきよりも前の部分から振り返ること。全部マルになるような簡単な計算に戻って、演習を重ね、徐々に現在つまずいている部分に近づいていくようにしましょう。
また、小学生の場合は計算以外の苦手は、苦手解消を無理強いしすぎないことも大切。ますます苦手意識が強くなり、悪循環に陥ってしまいます。苦手科目の中でも「ここは得意だね」という部分を見つけてあげたり、その教科に興味が持てるようなことを話してあげたりすることで、科目自体が嫌いになってしまうことを防いであげたいですね。
注意したいNG勉強法3選
作業しただけで問題を解かない
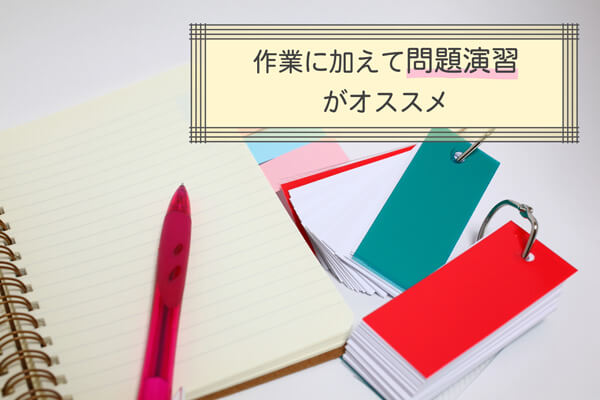
「ノートまとめ」「教科書に線を引く作業」「単語帳を作る作業」。この作業だけで「勉強した!」と満足してしまっている場合は要注意です。
作業をすると、内容が頭に入る場合もあります。ただ、作業が目的になってしまうと効果が薄れる可能性も。これだと、時間ばかりかかって学習の内容が身に付きません。さらに、アウトプットが足りないため実践力が付かないことも。
作業だけに一生懸命になるのではなく、問題演習をして知識をしっかり身に付けていきましょう。演習を重ねることで、テストで問われやすい点もわかり、テスト本番にも強くなっていきますよ。
問題を解きっぱなしにしている
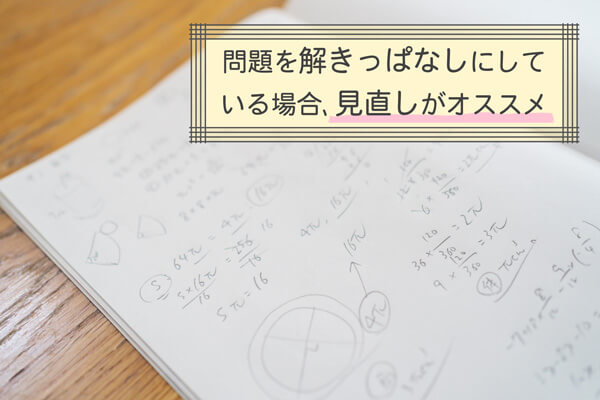
問題演習をしてわからないところや間違えたところがあったとき、どうしていますか? もし、「なぜ間違えたか」「どこがわからなかったか」を解決していないのであれば、要注意です。これだと、理解できていない部分がそのままになり、いつまでも同じところでつまずくことに。その結果、効率が悪くなってしまいます。
わからなかったところや間違えたところは、解説を読んだり学校や塾で質問したりして、早期に見直しをしておきましょう。また、つまずいたポイントが解決したら、再度同じ問題を解き直すことも重要。これにより、理解できたかどうかをチェックすることができます。
問題演習と解き直しを繰り返すことで、解法や知識がしっかり身に付いてきます。一見地道な作業ですが、結果的にこちらのほうが効率的。問題を解く際は、自分自身でフィードバックすることが大切なのです。
漢字や単語をたくさん書く

漢字や英単語は、書いて覚えることが大切。でも、必要以上に書かせすぎてしまっては逆効果です。一つの漢字を20回も30回も書かせていては、書くことが目的の作業になってしまいます。
一つの漢字や英単語は3〜5回くらい練習すればOK。数を絞ったほうが「ここはハネる」「ここのスペルはこう」とポイントを意識しながら書けますよ。
お子さまのやる気を引き出すには「楽しい雰囲気で、巻き込むこと」が大事

最後に、「うちの子に合った、もっと効率のよい勉強法はないかな?」と保護者のかたが気になったときのコツをお伝えします。
大事なのは、お子さまをうまく巻き込んで、やる気にさせていくこと。
お子さまの意欲が高まっていないままでは、どんなに効果的な勉強法であっても、やらされ感を覚えてしまいます。お子さまの勉強の仕方が気になる際も、いきなりあれこれアドバイスをしなくても大丈夫。
とはいえ、保護者から勉強について話されるのは、どんなお子さまでも身構えてしまうものです。心のバリアを張ってしまうことのないよう「今日の授業で面白いことあった?」と勉強に関する楽しい話を引き出してみたり、「一緒に勉強スペースを片付けよっか!」と共同作業しながらそれとなく授業の話を聞いてみた入りできるといいですね。
もし、お子さまが勉強への悩みを話し始めたら、共感的に聞いてあげることを心がけてみてくださいね。アドバイスはそのあとでOK。
勉強の効率は、お子さま自身の意欲がカギを握ります。保護者のかたは、「楽しい雰囲気で子どもが勉強ができる」お膳立てをするスタンスでいられるといいですね。
まとめ & 実践 TIPS
勉強の成果を上げるには、自分に合った勉強法で意欲的に取り組むことが大切。結果が出ると、「次もがんばるぞ」とさらに意欲的に取り組もうとするよいスパイラルが生まれます。お子さまが主体的に勉強法の改善に取り組めるよう、サポートしていってあげられるといいですね。
- 学習















