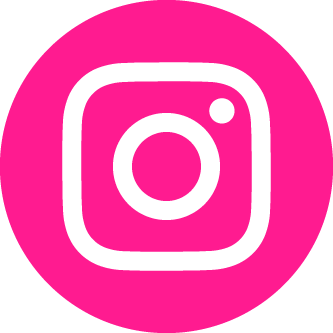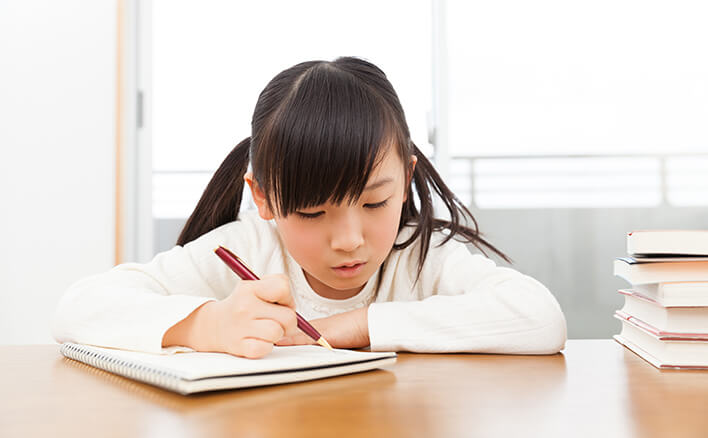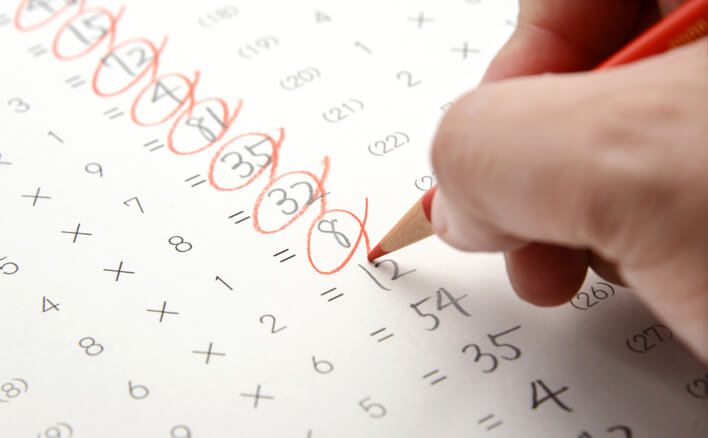通信教材の丸つけまで自分でやらせたいのですが……[教えて!親野先生]
お気に入りに登録
今まで通信教材の丸つけは親がやっていましたが、4年生になったのでこれからは自分で丸つけができるようにさせたいと思います。でも、教材をやること自体がやっとなので丸つけまでやらせるのは無理かなという気もします。何か良い方法はないでしょうか? (ジグザグ23 さん:小学4年生男子)
![通信教材の丸つけまで自分でやらせたいのですが……[教えて!親野先生]](/img_o/kj/kyouiku/201105/20110531-2.jpg)
親野先生からのアドバイス
ジグザグ23さん、拝読しました。
通信教材では、4年生から自分で丸つけすることをすすめているところが多いようです。高学年になったので自分で学ぶ習慣をつけさせよう、ということだと思います。
自分で解いた問題を自分で丸つけすることには利点がたくさんあります。
まず、やってすぐに答えを確認できるので、合っていればとてもうれしく感じられるということがあります。達成感を得られますし、それが次のやる気につながります。
ただ、何時間も経ってからの丸つけだと、丸がついてもそれほどうれしく感じられないことがあります。というのも、そのときは遊び、テレビやゲームなどもっと別のことに関心が移っているからです。
次に、間違えていたとき間違えた理由がわかりやすいという利点もあります。また、正しい答えややり方を覚えてしっかり定着させるのにも効果的です。というのも、問題を解いたときの記憶が頭に残っているからです。
しかし、何時間も経ってからの丸つけだと、もう問題を解いたときの記憶があいまいになっています。ですから、もう一度最初から問題を読んだり解いたりしないと間違えた理由がよくわからないことが多いのです。
そして、その作業をしないと記憶も意味のある記憶にならないので、ただ機械的に記憶することになります。
このように、自分で丸つけをする習慣をつけることは学力向上に大いに役立ちます。でも、丸つけは子どもにとってかなり面倒な作業でもあります。遊びたい盛りの子どもで通信教材の問題をこなすだけでも大変という場合、丸つけはかなりハードルが高いと言えます。
下手に無理強いすれば、教材そのものもやらなくなるかもしれません。そして、叱る材料が増えるだけという結果になりかねません。
そこで大事になるのは、その子の実情に応じて進めるということです。
何事もそうですが、「もう○年生だからできて当然」という発想で臨むとうまくいかないことが多いのです。子どもの成長スピードは百人百様だからです。
無難なのは少しずつハードルを上げる方法です。いきなり全部丸つけさせるということでなくて、まずは丸つけをしやすいところだけやらせてみるのです。そして、それができたらほめて、さらにやる気を高めてあげます。
たとえば、選択肢のある問題だけ自分で丸つけさせてみます。丸つけをしやすいところとしては、ほかにも漢字の読みや計算問題などがあります。そして、記述の問題や漢字を書く問題など、丸つけをしにくいところは親が見るようにします。
そして、丸つけができたら大いにほめます。自分で丸つけができたこと、間違いに気付いてバツをつけられたこと、こういうことを当たり前と思わないでしっかりほめることが大切です。正解と自分の答えの違いに気付くことは立派なことであり、正直にバツをつけることもさらに立派なことです。そういうことを、口に出してきちんと伝えてください。
親が「丸つけの点数」をつけてあげるという方法もあります。丸つけが全部正しくできたら、そのページに「丸つけ100点」と書いてあげるのです。
そして、丸つけを1つ間違えていたら99点です。
子どもはこれをけっこう喜びます。問題を解くうえで100点が取れない子でも、丸つけなら100点が取れるからです。
丸つけの筆記用具の選び方も大切です。ポイントは、色が鮮やかできれいなことと、太い線が描ける物を選ぶことです。つまり、少しでも華やかな丸が描けるようにしてあげるわけです。
かわいい花丸の描き方を教えてあげるのもよいでしょう。花丸の中に目を描けばにっこり花丸になります。花丸に目・鼻・耳などをつければ動物やキャラクターの花丸になります。こういうことは、特に女の子に効果的です。
また、丸つけの練習をさせてほめるという方法もあります。まず、教材をコピーして親がその問題を解きます。そして、子どもが正解の答えを見ながら丸つけをします。つまり、親子の立場を逆転させるわけです。
このとき、わざと1、2問間違えた答えを書いておきます。子どもがそれに気付いてちゃんとバツをつけられたらほめます。そして、「丸つけ100点」とか「丸つけの天才」などと書いてあげます。これは、丸つけを始めるときの取っかかりとして有効です。
ちなみに、正解の答えを見ながらでなく、子ども自身に考えさせて丸つけをさせると、かなり良い勉強になります。お母さんの間違いを見つけられたら子どもの勝ち、見つけられなかったらお母さんの勝ちというゲームにすることもできます。
さて、ここまで少しずつハードルを上げる方法を紹介しました。では、それをいつから始めたらよいでしょうか? 一番よいのは、学年・学期・年齢が変わるときや、新年を迎えるときなどの節目を活用することです。
こういう節目では子どもも気持ちが高揚しています。「4年生になったら……」「2学期になったら……」「10歳になったら……」「今年から……」という漠然とした気持ちを持っていますので、それを活かしつつ新しいことを始められるようにしてあげてください。
でも、いきなり「2学期になったから今日から丸つけもしよう」では芸がなさ過ぎです。まず、子どもをほめるところから入ります。これは子どもに何か新しいことを取り組ませたいときの鉄則です。
たとえば、それまで教材をがんばって続けてきたことをほめます。あるいは、教材や勉強と直接関係ないことでも良いでしょう。ほめられると子どもはとてもうれしく幸せな気持ちになります。
そこで、丸つけのことを持ち出すようにします。ただ、見え透いたやり方はしないように上手にやってくださいね。
ところで、少しずつハードルを上げる方法について詳しく書いてきましたが、子どもは百人百様なので大幅にハードルを上げても大丈夫な子もいます。そういう子はそれで良いと思います。でも、親が油断して放任してしまうことなく、必ず定期的に見届けをしてあげてください。
これはどんな子でも絶対に必要です。
それをしないでいて、あとになって「信じていたのに裏切られた」と言っても始まりません。それは親の怠慢を子どもに責任転嫁しただけのことです。
ところで、もう一つ大事なことがあります。子どもは百人百様なので、少しずつハードルを上げる方法でも丸つけさせるのが難しい子もいます。そういう場合は、丸つけは諦(あきら)めれば良いだけのことです。諦めが肝心ですよ。あまり欲張らないことです。
そのときは、親が楽しみながら丸つけをしてあげてください。親がたくさんほめながら丸つけをしてあげれば、子どももなんとか勉強を続けることができます。
最後に一つ、ちょっとしたコツを紹介します。
問題集や教材の答えのページは、活字が小さくなっていることが多いようです。これは大人には大したことではないのですが、子どもにとってはかなりの障害です。というのも、小さい字は子どもには読み取りにくいからです。
ですから、該当の答えがどこに書いてあるかを見つけることからして子どもには大変なのです。しかも、問題集や教材によっては問題のページと答えのページのレイアウトが違っていることもあります。こういうちょっとしたことが障害になっていることが多いのです。
次のような工夫で少しでも障害を減らしてあげるとよいでしょう。
・答えのページを拡大コピーしておく
・その日の分の答えのページに付せんを貼っておく
・答えがある場所を見つけやすいように、問題のページと答えのページの関連部分を同じ色のマーカーで囲っておく
この他にも、子どもの実情に合わせていろいろな工夫ができると思います。ぜひ、子どもの目線で工夫をしてみてください。
私ができる範囲で、精いっぱい提案させていただきました。
少しでもご参考になれば幸いです。
皆さんに幸多かれとお祈り申し上げます。
![]()
 | 【お知らせ】 こちらの親野先生のコーナーから単行本第三弾が誕生! 大人気のこちらのコーナー、[教えて! 親野先生]が、本になりました。『「共感力」で決まる!』です。子育てが激変する親子関係の新ルールが相談例をもとにわかりやすく提案されています。 |