「丸つけ」が家庭での学習効果を高める! 丸つけができる子、できない子
- 学習
休校期間を受け、例年以上に家庭学習の時間が増えた2020年前半。「学習内容がきちんと身についているのだろうか…」といった学習へのお悩みも、例年以上に耳にします。
そこで今回は、家庭での学習効果を高める「丸つけ」についてお伝えさせていただきます。
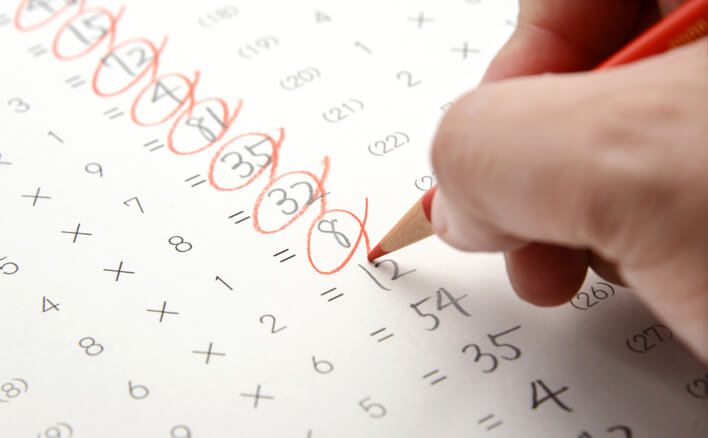
「勉強」とは「できない問題ができるようになること」
丸つけのできる子、できない子の具体的なお話の前に、そもそも勉強とは何か?という部分についてお話しさせてください。
表題にも書きましたが、「勉強」とは「できない問題ができるようになること」を指します。
つまり、「できる問題」を解くだけでは「できない→できる」に変わった問題が増えていない、という点で「勉強」にはなっていません。
しかし、どんなに素晴らしい参考書や問題集も、自分ができない問題・自分の弱点に合わせた問題だけが掲載されているわけではありません。
「できない問題ができるようになる」=「勉強」を始める前に必要なことがあります。
- 課題や問題集にある問題を、「できる問題」と「できない問題」に仕分ける
そうすることにより、これから学習すべき問題だけが掲載されたオリジナルの問題集ができあがっていきます。
この仕分けこそが、丸つけの大きな意義なのです。
丸つけをしない、子どもの心理とは?
「できない問題」を見つけるための仕分けとして、丸つけに重要な役割があるのですが、ではなぜ“丸つけができない子”は丸つけをしないのでしょうか?
“丸つけができない”“丸つけをしない”を、以下のチェック事項に当てはまるかどうかで見て下さい。
- (自分で)丸つけをやらない
- 丸つけを後回しにしている
- 数~数十ページ解いた後、まとめて丸つけをしている
- 丸つけに間違いが多い
上記のような丸つけの状況は、特に、学校の課題が増え自分で学習を進めるようになる小学校高学年~中学生のお子さまに多いかと思います。
“丸つけができない”お子さまは「課題を終わらせること」つまり、解答欄を埋めることが主目標になってしまい、「できない問題をできるようにする」ということまで意識されていないのです。
もちろん、問題を解いた後にもう一つ作業がある…という億劫(おっくう)さも手伝っています。しかし、先ほどのチェック事項は、以下の点が共通しています。
- 正解かどうかは二の次で、課題を終わらせることに終始してしまっている
つまり、丸つけをしない・丸つけができない子は、そもそも「できない問題をできるようにする」ことが「勉強」なのだ、という根本の意義に気づけずにいる場合があるのです。
「できない問題」こそ、大切に
×がついた問題はだれでもいい気分ではありません。しかし、「できない問題」をできるように努力することは、勉強に限らず様々な場面でお子さまの力となってくれます。
「できない問題」こそ成長のチャンス!と思って積極的に取り組めるように、ご家庭でのポジティブな声かけが重要になってきます。
<声かけ例>
- 「この問題ができたらすごいってことだよ!」
- 「できない問題があったなら、この課題はやった意味があったね!」
- 「次のチャレンジでこの問題ができたら、成長してるってことだね!」
できないことを悪とするのではなく、できるようになるためのファーストステップと伝えてあげることで、取り組むお子さまの気持ちは上向きになります。
もちろん、〇×といった記号に限らず、間違えた問題に★をつける、間違えた問題にふせんを貼る、などの方法も有効です。特に、学齢が小さいお子さまほど、〇がつけばうれしいですし、×がつくと悲しい気持ちになる場合が多いです。そこで、正解した問題には〇、間違った問題には★をつける(または、わかるようにシールを貼る)など、繰り返し取り組みたくなるような工夫で丸つけをルール化するのも効果的な手法です。
まとめ & 実践 TIPS
「丸つけ」と聞くととても些細なことに思いますが、課題を見分ける力や、課題に取り組む力を養う、大切な役割を果たしています。できなかったことができるようになる達成感や成長の実感のきっかけは、実は身近なところにあるのだ、ということをお子さまにも感じてもらえればと思います。
株式会社プランディット 英語課 堀内(ほりうち)
編集プロダクションの株式会社プランディットで、進研ゼミを中心に、小学校から高校向けの英語教材の編集を担当。
- 学習














