家庭学習の習慣をつけさせるために【高学年編】
お気に入りに登録
高学年の家庭学習はとても重要なもの。低学年のうちは習慣づけをメインに考え、机に向かうことができれば比較的内容はどんなものであっても大丈夫です。しかし、高学年では「学校だけでは不足してしまう部分を補う」「中学校に向けて、小学校の勉強内容をしっかり押さえておく」など、家庭学習の意味が違ってきます。高学年の子どもにはどのような家庭学習が必要なのでしょうか。
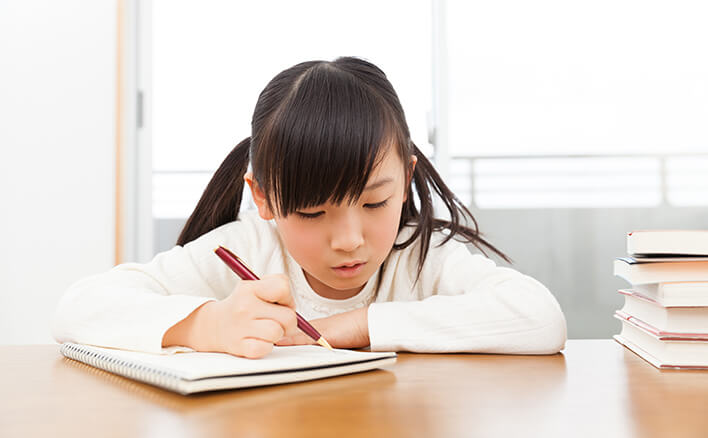
高学年の家庭学習時間の目安は3年生で30分
家庭学習の時間は、宿題以外に《1日10分×学年》ということがよく言われています。低学年のうちは宿題をまったく別に考える必要はないかもしれませんが、高学年は可能な限り「宿題以外に」を意識しましょう。
家庭学習の時間を一日のうちいつにするのかをしっかり決めておくようにすると、より習慣づけがしやすくなります。もちろん、本人の都合によって柔軟に変更してもいいのですが、「基本的にはこの時間」ということを決めておくほうがいいですね。高学年ともなると学校から戻るのも遅く、習い事などもあるとまとまった時間をとりにくいことも。その場合には「朝30分、夜30分」など、体力的にも無理のないスケジュールを組むのがおすすめです。
内容は「復習」に重点を置く
学習内容は、予習よりも復習に重点を置くようにします。子どもが望むようであれば予習でも構わないのですが、学校によって教え方が違ったり、学校において「どう思うか」を議論したりする場合もあり、正解が簡単に導き出せることがあまりプラスにならない面もあるためです。もし予習するなら、漢字や英語などにしておきましょう。
また高学年の子どもは低学年以上にいろいろなことに興味を示します。ゲームなど興味をそそられるものも多々。なかなか習慣化していくことが難しくお悩みの保護者のかたも多いでしょう。
学習習慣をつけるためには、子どもの話をしっかりと聞くことが必要です。そこから、子どもにとって、今、何が必要で、その内容を家庭で学習することで、どのような結果が得られるのかを保護者のかたが具体的に考えてあげることで、学習に取り組みやすくなりますよ。
基本的なことがしっかりできるように考える
高学年になると、子どもによっては完全に自主勉強が可能です。しかし、学校で勉強したところで不安なところ、わかりにくかったところはないかなど、「どういった勉強をするべきか」はまだ自分だけで考えることができません。
保護者のかたが導いてあげると、より効果的な復習ができます。
そのとき大事なのは、決して難しい内容にしないこと。基本的なことがしっかりとできるように考えてあげることで、一つひとつ丁寧に学習をすることも学べるようになるはず。具体的に何をすればいいのか、それによって、どのような結果が得られるのかを子どもがわかれば、学習に取り組みやすくなり習慣化しやすくなります。
そのうえで質問しやすい環境があれば、子どもも安心して学習に取り組めるので、より習慣化できると思います。高学年であっても保護者のかたが家庭学習に関わることは重要。子どもが保護者のかたに声をかけやすいような環境を整えてあげたいですね。
もうひとりでできるから…と完全に目を離してしまうと、やはりどんどん楽をすることを覚えてしまいます。「どんな感じに進んでいる?」といった感じで気にしてあげるといいのでは。
高学年とはいえ、「可能な限りたくさん勉強させたい」と思う必要はありません。低学年よりは長めになりますが、家庭学習の習慣づけのほうが大切なことだと考えましょう。1日数10分の積み重ねは、数年後に大きな差を生み出します。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 【入学準備】どうする?年長さんの文字の学習。ひらがなやカタカナを正しく美しく書けるようにするコツ
- AI時代に求められる「生きる力」を育てたい。将来のために子どもに無理をさせてはいけないワケとは?
- 2025年版「子ども用GPS端末」のおすすめ9選!安くて人気なのは?キッズスマホとの違いは
- 富岡製糸場について知る
- 国際関係学ってどんな学問?研究内容・就職先・大学選びのポイントは?
- 「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]
- 成績とスマートフォン使用との関係性アル? ナシ?
- 大学に入ってから後悔しないために! 学問・学部・学科選びの鉄則
- 【どうなる?どうする?娘の大学受験】第12回 合格発表
























