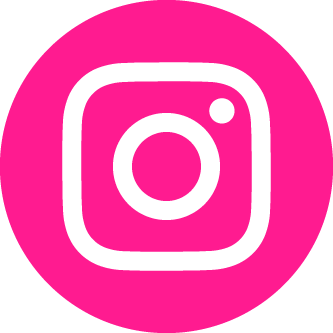人と話すのが苦手な子 必要なサポートは?【親野先生アドバイス】
- 育児・子育て
言葉が出てこない、滑らかに話せない、まわりの子に比べて遅れているよう……など、子どもの言葉にまつわる不安はいろいろ。
本人が気にしている場合の関わり方、相談先などのサポートのアドバイスなどを、教育評論家の親野智可等先生にお聞きしました。

この記事のポイント
叱らず無理をさせない
話したいことがあっても言葉が出てこないことがある、言葉が滑らかに出てこないので度々聞き返される、家では普通にしゃべるのに友達の前では言葉が出なくなるなど、言葉の気がかりにはいろいろなタイプがあります。
話し方にも個性があるので、もともと口数が少ないタイプだったり、発達の個人差で今は遅れているように感じるだけだったりと、あまり深刻にとらえなくてよいケースもあるでしょう。
一方で、専門家のサポートが必要な場合もあるので注意深く見てあげることは必要です。特に学校での友達関係やコミュニケーション、勉強のうえで本人が苦しい思いをしているなら、なるべく早く緩和したり取り除いたりしてあげたいですね。
まず心にとめておきたいのは、子どもを叱ったり、無理に「話しなさい」と迫ったりしても効果はないということ。心配や、がんばってほしいという親心から、背中を押そうとしてしまうこともありますが、子どもは、できれば自分でうまく話したいけれど、うまくできないのです。
叱られたり指示されたりしても思うようにできないことで、自己肯定感が下がって余計に話せなくなってしまいます。心理的な不安のサインである可能性もあり、プレッシャーは悪影響になるので大らかに接することを心がけましょう。
学校での様子は先生にたずねてみるといいでしょう。友達との関係や授業のことなど、気になることは相談を。学校でも家庭同様、子どもを追い詰めないように接していくことが大切ですから、安心して過ごせるように先生にもお願いしておきましょう。
ときには、先生や学校から専門機関への相談をすすめられることもあります。驚いたり抵抗を感じたりすることがあるかもしれませんが、実際に相談してみると、子どもはもちろん保護者のかたにとってもよいことがあるはずです。
「この程度で相談するのは大げさかもしれない」と考えたり、「もしも障害があると診断されたら……」と思って踏み出せない保護者のかたも多いと思います。でも、どのようなサポートが必要かは、原因や状況によって一人ひとり違い、保護者のかたが判断するのは難しいのです。
相談すると安心できる
言葉のサポートは、なるべく早い時期からスタートしたほうが効果的です。診断の内容、困難の程度にかかわらず、子どもの特性や状況を把握でき、今できることが見えてくると安心できるでしょう。
何より、相談できる専門家がいるというのは、親子ともに心強いものです。先送りせず、相談してみることをおすすめします。相談先として身近なのは、子どもをよく知る、かかりつけの小児科や内科などでしょう。
医療機関には、児童精神科や小児神経科などもあり、かかりつけ医から紹介してもらえることがあります。学校や教育委員会にも、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門家がいるので、まずは学校で相談してみるのもよいでしょう。
公立の小中学校ではコミュニケーションや学習をサポートする「言葉の教室」で支援を受けることもできます。必ずしも校内に併設されていなくても近隣の学校のどこかにはありますし、診断の有無にかかわらず必要性を判断して支援してもらえます。
支援が始まると、子どもの困りごとや不安を改善していくためのトレーニングを行います。発話だけでなく、「いやなことをされたら、こうしてみよう」「こんなふうに伝えてみよう」といった、やりとりのアドバイスもあり、家庭で練習できることも教えてくれます。
家庭での練習は大切で、その積み重ねで子どもに必要な力がついていきます。この場合も、強制したり叱ったりしてもよいことはないので気をつけて。子どものペースを大切に、寄り添うようにゆっくり付き合っていきましょう。
子どもの伸びしろを楽しみに
言葉の気がかりは保護者のかたにとっては大きなもので、ついそこに目がいきがちですが、子どもの個性にはさまざまな側面があります。
アインシュタインは言葉の発達がとても遅く、両親はとても心配していたそうです。妹は対照的におしゃべりで、言い返せないアインシュタインはかんしゃくも起こしていたとか。大人になっても言葉での伝達には苦労したそうですが、多くの業績を残しました。
アインシュタインの例でもわかるように、どの子にも苦手なことがある一方で必ず優れた面もあるので、子どものそうした面を見つけて自信を持たせていくことが重要です。結果的に言葉の面でも良い影響があるでしょう。
もうひとつ例をあげると、家ではふつうに話せるのに、学校ではまったく話せないという「場面かんもく」の子どもが、成人して歯科医になった例もあります。コミュニケーションも必要な職業ですから、成長の過程で症状が緩和されたのでしょう。
子どもが安心して、前向きに過ごせるようにするためには、保護者のかたの安心も大切です。子どものサポーターを増やすという考え方で、必要性を感じたらまずは相談先を探し、一人で抱え込まないようにしてくださいね。
まとめ & 実践 TIPS
子どもを叱ったり、話すように強要したりしても、効果がないうえに悪影響になることも。子どもが困っている時や保護者のかたが不安な時は、早めに相談先を探してみましょう。そうすれば気持ちが楽になりますし、子どもの成長にもつながります。
- 育児・子育て