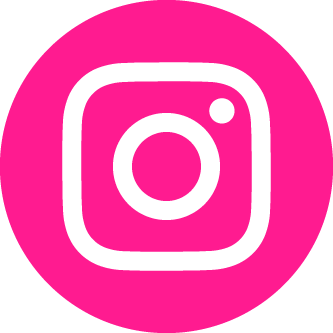《授業中に座っていられない子》に親ができること【親野先生アドバイス】
- 育児・子育て
「授業中に座っていられない」「じっとしていられない」などと聞くと不安になります。指摘を受けた時、親として何ができるか、どのように向き合えばいいかを教育評論家の親野智可等先生にお聞きしました。

子どもの状況を把握して相談を
授業中に落ち着きがない、集中できないようだ、といった場合、実際の子どもの様子には大きな幅があります。他の子に比べると多いという程度だったり、教科や先生によって変化したりすることもあり、成長とともに落ち着いてくる子も少なくありません。
また、授業中の姿は学年によっても変わりますし、学年や学期の初め、保護者参観日などに多少落ち着きがないのは普通のことだともいえます。参観日の様子が気になったとしても、帰宅後すぐに叱っては本人の自信ややる気をそいでしまうので控えましょう。
一方で、クラスが落ち着いてきても授業中座っていられない、すぐに立ち歩いたり教室を出たりしてしまう、授業をストップさせてしまうというような時は、何らかのサポートが必要な場合があります。まずはお子さんの状況をよく把握するようにしましょう。
どの程度の時間なら座っていられるのか、教科や教室で様子に変化があるかなどを学校の先生にたずねたり、家庭での学習や好きなことをしている時の様子に注目したりしたうえで、状況をよくするために専門家に相談するとよいと思います。
たとえば地域の保健センターや子育て支援センター、発達障害者支援センターのほか、発達支援を行う民間の機関や小児科、心療内科、児童精神科など、相談先はさまざまあります。公的機関は自治体によって名称が異なるので、まずは市区町村の福祉課などの身近な窓口を探して問い合わせてみてください。
ひとりで思い悩まないようにしよう
相談をする時は、なるべく複数の専門家の話を聞くことをおすすめします。専門分野や人が異なれば診断が変わることもあり、得られるアドバイスも変わります。
保護者のかたの中には、専門機関に相談すると大げさなようで気が引ける、もし発達障害と診断されたらと思うと抵抗を感じるという人もいるかもしれません。でも、不安を抱えてひとりで悩むのはつらいことで、状況も改善しづらくなります。
経験豊富な専門家に話を聞いてもらえる、そうした窓口とつながっているという安心感を持ってほしいと思います。また、子ども自身は十分がんばっているのに叱られてしまうことも多く、本人も傷付き、保護者のかたの自己肯定感も下がっていきます。
大切なのは、お子さんが今よりも過ごしやすく、成長しやすくなる方法を探すこと。具体的なアドバイスで関わりやすくなりますし、うまくいかないのは努力不足ではないとわかれば、保護者のかたの気持ちも少し楽になるのではないでしょうか。
サポート開始が早いほど負担も軽くなる
部分的に苦手なことや生活の中で困難な場面がある、いわゆるグレーゾーンの子どもも、専門家の診断によって何らかのサポートが必要とされれば、授業中の支援をはじめ、発達のトレーニングや関わり方のアドバイスなどを受けられるようになります。
発達障害と診断された場合は、それによってさまざまな行政のサービスが受けやすくなり、経済的な支援もあります。
こうしたサポートは早く始めるほど負担が早く解消され、効果も上がります。近年は発達障害やグレーゾーンの子どもが増加し、面談や受診の件数が多くて予約が数か月先になることもあるので早めに問い合わせておきましょう。
理解を深め心の支えになる情報も
今は本やインターネットなどでも多くの情報にふれることができます。さまざまな形で情報を取り入れることは、子どもへの理解を深めるので、よいことです。
我が子と似ている子どもの様子を紹介する体験談や漫画などが、家庭での関わりのヒントを与えてくれるかもしれません。特に、親子の姿に共感できるコンテンツは、心の支えになることもあります。
また、発達障害がある子が特別な能力を併せ持つことがあるように、ある面で苦手があっても別の面で能力が高いことがあります。幅広い情報が、我が子のそうした一面に気付くきっかけをくれるかもしれません。
ただ、個人的な体験談や部分的な情報は、我が子には当てはまらない場合も多いもの。参考にしてもうまくいかないと、「なぜダメなのか……」と親子で苦しい期間が続いてしまうことも。やはり子どもの様子を直接見てくれる専門家のアドバイスを受け、それに加えて情報を増やしていくのがよいと思います。
どんな親も、日々のふれあいの中で少しずつ子どもへの理解を深め、子どもの成長に応じてまた関わり方を変えていきます。我が子をよく観察し、必要なサポートを受け、情報を取り入れながら、楽しく過ごせる方法を見つけていけるといいですね。
まとめ & 実践 TIPS
本やインターネットなどの情報も役立ちますが、ひとりで思い悩まず、負担を軽くする方法を探しましょう。サポートが必要な場合もあるので、なるべく早く相談を。複数の専門家に話を聞いてもらい、アドバイスを受けることで親子ともに楽になることが多いです。
- 育児・子育て