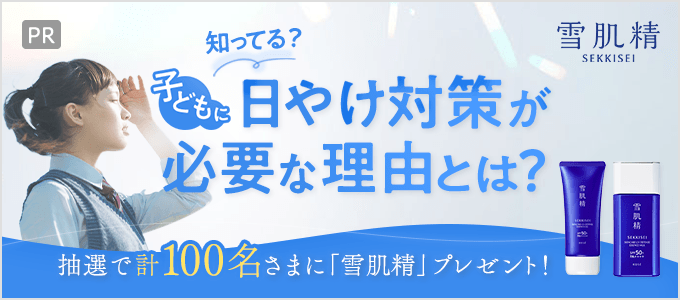2学期に備えて課題の棚おろしを [中学受験 6年生]
お気に入りに登録
 保護者の役割は、お子さまの成長に応じてベストのタイミングで働きかけ、環境を整えていくこと。6年生を対象に、2学期を見据えて夏休み後半に取り組むべき課題について取り上げます。
保護者の役割は、お子さまの成長に応じてベストのタイミングで働きかけ、環境を整えていくこと。6年生を対象に、2学期を見据えて夏休み後半に取り組むべき課題について取り上げます。
■総復習の意味は、2学期に向けた課題の整理
夏休みの後半、6年生の子どもたちや保護者に学習の感触を聞くと「疲れた!」というかたが非常に多いですね。これは当然かと思います。夏休みの課題は「苦手克服」と「総復習」であることを前回もお伝えしましたが「総復習が終わらない!」「苦手がまったく克服できていない!」と焦っているかたも多いのではないでしょうか。
しかし、ここで焦りは禁物です。「夏休みは受験の天王山」などと盛んにいわれますが、あまり気にしなくてかまいません。夏に総復習を行う意味は、2学期に向けて課題を整理するため。とりあえず、この夏にやるべき問題がコンパクトにまとまった問題集を1冊、なるべくやりきってください。これが、2学期以降も受験のバイブルになります。「その1冊を、受験まで大切に使っていこうね」とお子さまにもぜひ伝えてください。
■夏に取り組んだ問題集で「優先順位」を付ける
2学期以降は、時間との戦いになります。志望校に応じて、優先順位をいかに付けるかが極めて大切なのです。夏休みに取り組んだ問題集を見直し、できている単元、できていない単元に印を付けるなどして、2学期に取り組むべき課題を整理してください。
お子さまに対しては「大丈夫だよ」「苦手なところも、ゆっくり取り組んでいけば間に合うからね」という姿勢が基本。「課題が多すぎる!」と保護者がまいってしまっていては逆効果になります。
マスターしている単元、得意な分野については「ここは得意だね」「こういうところが武器になるね」ということを、お子さまにしっかり伝えてあげてください。最近増えている総合問題や適性問題では、得意分野を糸口に解答の手がかりを得たり、自分の考えを深めたりすることが大切になります。
さらに、その問題集を塾や家庭教師の先生に見せて、志望校に応じて「ここは必要」「このレベルの問題はやらなくていい」などと優先順位を付けてもらいましょう。志望校に応じてコーチングしてもらい、課題が減ると子どもの不安も軽減されますし、意欲も違ってきます。
■「やりきった!」という達成感を味わって
このように、夏休みに総復習や苦手克服に取り組む意味は、2学期には何に力を入れるべきか判断する「材料」を得るため。夏休み明けの時点で、志望校の合格ラインに達している子はほとんどいません。9月から12月までの間に、3か月間かけて徐々に力を上げていくイメージを持ってください。課題が明確になると、不思議と実力はそこに追いついてくるものです。入試問題は、夏の時点ではまだ解けなくてかまいません。取り組むのは冬休み以降でいい、くらいのつもりでゆったりとかまえておきましょう。
夏休み後半に大切なのは、「この夏は、やりきった!」「やればできるんだな」という達成感を持たせてあげることです。夏期講習を受けたり、塾の合宿に行ったりなど、さまざまなイベントを経験して、子どもたちの中では自然と受験ムードが高まっています。子どもたちのやる気をくじかず、意欲を高めるためにも「ダメなところ」を指摘せず、がんばったところを認めてあげてください。また、疲れが出やすい時期ですので、8時間以上の睡眠と、バランスのよい食事を心がけるなど、体調管理にも気を配ってあげてください。
8月は、「やりきった」自信と、意欲を充電する時期です。課題を明確にし、荷物を軽くしてあげて、時間が勝負となる2学期に備えましょう。













![2学期に備えて学習環境の見直しを [中学受験 5年生]](/_shared/img/ogp.png)