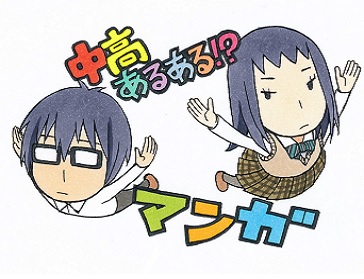自治体によって違う、学校教育の特色ある取り組みとは?
お気に入りに登録
グローバル化や情報化が進む中で、日本や地域を支えていく人材を育てるために、多くの地方自治体が学校教育を充実させ、人づくりに重点を置くようになっています。今回は、中でも対応が急がれている英語教育と情報通信技術(ICT)環境の整備について、特色ある取り組みをご紹介します。

さまざまな形で英語力アップを支援
英語教育については、2011(平成23)年度から小学5・6年生での「外国語活動」が必修化されました。文部科学省では小学3年生からの英語活動の必修化を検討していて、英語教育はさらに強化されていきそうです。
そうした動きを受け、岡山県総社市では、公立幼稚園でも英語活動を始めています。外国人指導助手(ALT)が、幼稚園に隔日に訪れて、子どもたちと一緒に遊ぶというものです。幼少期から英語に慣れ親しみ、英語を話す姿勢を育むことをねらいとしています。小中学校にはALTを常駐させ、幼稚園から継続して外国人と日常的にふれあえる環境を整え、幼小中一貫した英語教育を行っています。
公立中学校と県立高校とでは管轄する自治体が異なりますが、両者が連携して英語教育を進めているのが、石川県七尾市です。すべての市立中学校と市内にある県立高校とが連携し、中高合同で英語教員の研修会を開いています。また、中学校と高校とが同じ外部検定試験を行い、子どもの英語力を中高一貫して統一の指標で測れるようにしました。
留学支援に特化した奨学金制度を整える地方自治体もあります。熊本県では、高校卒業後に海外難関大に進学を希望する者や高校時代に留学したいという生徒に、留学資金を支援しています。さらに、ネイティブスピーカーの講師による講座も開き、留学に向けて英語力アップも支援しています。
教育の情報化は、機器の整備と人材育成の両面で進める
英語教育と並んで、各自治体が力を入れているのがICT環境の整備です。授業でのタブレット端末の活用が進められていますが、すべての子ども1人に1台を配備しようとすると、多額の費用がかかります。そこで、最低1クラス分のタブレット端末を配備して、クラスが持ち回りで使えるように整備している自治体が目立ちます。
例えば、滋賀県草津市は、小中とも1学級35人としていることから、およそ3学級ごとに35台の割合でタブレット端末を配備しました。埼玉県戸田市では、2013(平成25)年度から順次、公立小・中学校1校当たり40台のタブレット端末の配備を進めています。さらに、両市とも、電子黒板や書画カメラなどはすべての教室に配備して、タブレット端末は毎日使えなくても、授業で日常的にICTを活用できるようにしています。
単に機器の整備をするだけでなく、先生方のICT機器活用力を高めることにも力が入れられています。栃木県那須塩原市では、まず、ICTを活用した授業づくりを研究する小学校を指定し、1学級分のタブレット端末、無線LANなどを配備しました。さらに、ICT機器のトラブルシューティングや授業での利用法をアドバイスする専門の支援員を常駐させ、ICT機器が授業でどのように活用できるのか、実践例を積み上げています。今後、市内各校に研究校での実践例とセットでタブレット端末を配備し、先生方がスムーズにICT機器を活用できるようにしようというわけです。
地方自治体は、地域の事情に合わせて、限られた予算の中で工夫して教育をよりよくしようとしています。教育施策に関する情報発信を積極的に行う地方自治体もありますから、お住まいの自治体のホームページを、チェックしてみてはいかがでしょうか。
*ここで紹介する情報は2016年1月時点のもので、変わることがあります。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 「人間力」で学力を向上させて志望大学に合格! ある学校の興味深い取り組みとは?
- 貧困・ひとり親家庭への支援が急務
- 急がれる教育のIT化、自治体間格差がブレーキに?
- ベネッセグループが「第 15 回 EDIX(教育総合展)東京」 に出展 Next GIGA に向けて「すべての児童・生徒のよりよい学び」と、それを支える学校現場の校務 DX と働き方改革を支援します —自治体・学校・有識者らとともに、教育現場の変化の最前線を紹介— | パブリシティ
- 子育て家庭への支援が急務 「苦しい」世帯が約7割も
- 教育の情報化の自治間体格差解消を 文科省が通知‐斎藤剛史‐
- 【お金の教育マンガ17】習い事と学校の違い
- 発達障害は「身近な存在」 充実した支援が急務-斎藤剛史-
- 「情報教育」に依然大きい地域格差