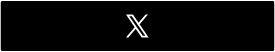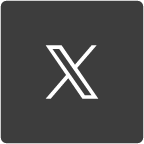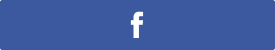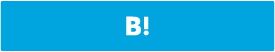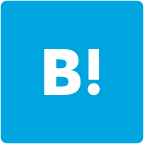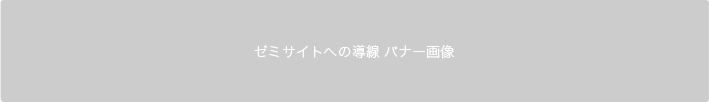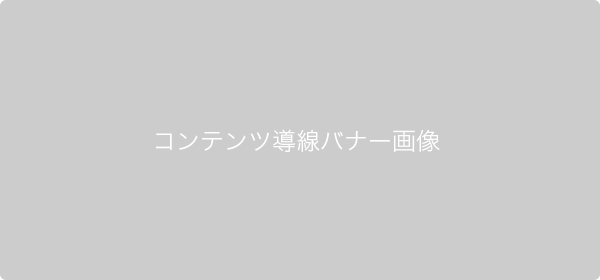日本の大学教育 相変わらず家庭の負担頼み‐渡辺敦司‐
お気に入りに登録
 年末を迎え、来年度の政府予算案も固まってきました。しかし教育分野に関しては、学校の先生の数や、国立大学に対する運営費交付金を削減しようという論議があったことは、これまで紹介してきたとおりです。とりわけ大学の授業料などの高さは、保護者にとって目の前にある頭の痛い話でしょう。先日にも取り上げた経済協力開発機構(OECD)の「図表でみる教育2015年版」からは、大学・短大など高等教育への進学を、依然として家庭の負担に頼っている日本の姿が、改めて浮かび上がってきます。
年末を迎え、来年度の政府予算案も固まってきました。しかし教育分野に関しては、学校の先生の数や、国立大学に対する運営費交付金を削減しようという論議があったことは、これまで紹介してきたとおりです。とりわけ大学の授業料などの高さは、保護者にとって目の前にある頭の痛い話でしょう。先日にも取り上げた経済協力開発機構(OECD)の「図表でみる教育2015年版」からは、大学・短大など高等教育への進学を、依然として家庭の負担に頼っている日本の姿が、改めて浮かび上がってきます。
国別に特色をまとめた報告書(カントリーノート)<外部のPDFにリンク>)によると、日本は「学生の大多数が私立教育機関に在学している数少ないOECD加盟国の一つ」です。2013(平成25)年の在学率は、国公立21%、私立79%でした。これに対して、OECD平均は各69%、31%と、むしろ国公立の割合が高くなっています。しかも授業料に関しては、「国公立でも私立でも、特に高額の授業料を請求されている」「データのあるOECD加盟国で最も高額な国の一つ」とされています。
私立を中心とした高等教育機関自体も、授業料収入に多くを依存しています。その結果、高等教育の私費負担割合は66%と、OECD平均(30%)の倍以上の高さとなっています。
保護者の方々の学生時代には、まだ国公立の授業料は、私立に比べて、ずいぶん安かったことと思います。しかし、その後の国の財政難により、国立大学の授業料などを年々上げてきたため、国公私立の差は縮まっています。
高等教育への進学率が上昇するにしたがって、授業料を上げざるを得ないのは、ある意味で仕方のないことかもしれません。ましてやアクティブ・ラーニング(AL)をはじめとした丁寧な教育方法を通じて、学生一人ひとりに社会で活躍できる汎用的能力を育てようとするなら、どうしてもコストを掛けなければなりません。とりわけ近年では、グローバル人材の育成への期待が高まっていますから、昔以上にコストが増えることは避けられないでしょう。
しかし日本はもともと、高等教育に対する私費負担の割合が高い国です。進学率の上昇も、家庭の負担によって成り立っているということになります。
国内では「みんなが大学に行く必要があるのか」「これだけ多くの大卒がいて、価値はあるのか」という主張もあります。しかし、OECDの統計で見ても、高等教育を修了した25・34歳の所得は、同年齢層より36%高くなっています(OECD平均は41%)。
メリットは個人にとどまりません。国の成長を促すのは、労働力の高さだからです。高等教育進学率の上昇は社会も恩恵を受けるのだから、公費による支出を増やすのも「先行投資」という考え方もできます。しかし日本のように教育費をますます「自己責任」にしてしまっては、OECDが懸念する世界的な教育格差が、日本でも広がってしまうかもしれません。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 「国際バカロレア」が日本の教育を変える!?‐渡辺敦司‐
- 「行きたい大学はあるけれど、うちの子の成績では厳しい…」その時、保護者はどうすればいい?
- 4歳~5歳の子どもの「書きたい気持ち」を伸ばすコツって?
- 日本のICT教育に「危機意識」を 世界に後れ、地域格差も拡大-渡辺敦司-
- 国立大に通うといくらかかる?学費やそれ以外の費用は?授業料等減免と給付型奨学金も
- 子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき どう対応する? 不登校に悩んでいる保護者のかたへ [やる気を引き出すコーチング]
- 日本の英語教育も「世界標準」に? 外部試験の導入論議きっかけ‐渡辺敦司‐
- 【専門家監修】受験料だけじゃない!大学受験にかかる費用総額は約40万円!?
- 【Q&A】中学受験の国語「得意な子」と「苦手な子」の特徴は? 苦手克服の勉強法と読解のコツ