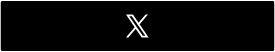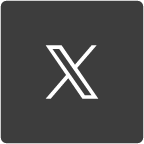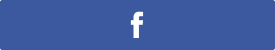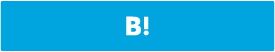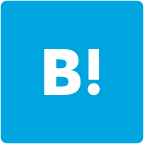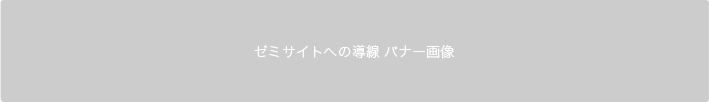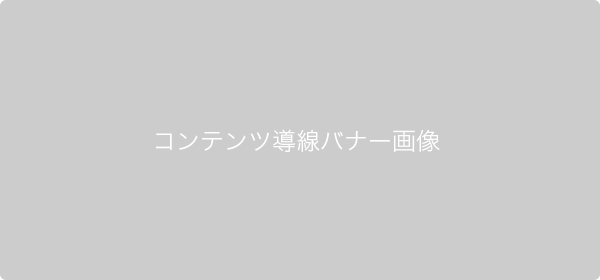桜の歌人・西行。桜になにを見ていた?
桜といえば、平安時代末期の歌人・西行を連想する人も多いのではないでしょうか。西行にとって桜とは、どういう意味を秘めていたのか、お伝えします。

西行ってどんな人?
西行は元永元年(1118年)に生まれ、俗名は佐藤義清(さとうのりきよ)といいました。武門の家柄でしたので、武士として生活し、妻子もあったのですが、23歳のときに、「花の寺」といわれるほど、山が桜の木に覆われた京都西山の勝持寺(しょうじじ)で出家しました。出家した理由はさだかではありませんが、友人が亡くなったとか、失恋したといった理由が推測されています。
出家したあとは、各地に小さな小屋を作って隠者のように暮らし、諸国を巡る旅にも出ました。そこで多くの和歌を作り、西行は生涯で約2090首の歌を残しました。そして、そのうちの230首で桜を詠んでいます。
「和歌を一首詠むのは、仏像を一体彫るのと同義」と西行が言ったことからもわかるように、歌作りは仏道修行の一環でもあったようです。
西行が各地で詠んだ歌
京都、吉野…各地で西行は歌を作りました。奥州や伊勢へ足を伸ばしたこともあったようです。西行は、出家した京都西山の勝持寺で、次の歌を詠んでいます。
“花見にと 群れつつ人の 来るのみぞ あたら桜の とがにはありける”
これは「桜の花を見にと人々が大勢やって来ることだけは、独りで静かにいたいと思う自分にとって、惜しむべき桜の罪であるよ」と解釈されています。
西行が毎年のように出かけていた吉野でも、たくさんの歌が生まれました。
“吉野山 こずゑの花を 見し日より 心は身にも そはずなりにき”
(吉野山に咲く梢の桜の美しさを見た日から、桜にあこがれる自分の心は、身には添わなくなってしまったことだよ。)
“花を見し 昔の心 あらためて 吉野の里に 住まんとぞ思ふ”
(桜の花にあこがれて浮かれ歩いた昔の心を思い出し、改めて昔のように吉野の里に住もうと思うよ。)
“今よりは 花見ん人に 伝へおかん 世を遁れつつ 山へ住まへと”
(世を逃れ心やすらかに桜をめでることを知った今から後は、桜の花をめでる人に、自分のごとく世を逃れ山に住みなさいよと伝えておこう。)
最も有名な西行の歌は、次のものだといってよいでしょう。
“願わくは 花のしたにて 春死なん そのきさらぎの 望月の頃”
西行はこの歌に「どうか、春の、桜の花の咲く下で死にたいものだ。あの釈迦が入滅なさった二月十五日頃に」という願いを込めました。そして、文治六年(1190年)二月一六日にこの世を去りました。
西行にとって、桜とは、恋焦がれる対象、高貴なものや天上へのあこがれ、生命への賛歌であったなどと、いろいろな説があります。西行の歌を読んで、その真髄に触れてみてはいかがでしょうか。
参考:
井筒清次『おもしろくてためになる桜の雑学事典』(日本実業出版社)
西行の歌の注釈は『山家集』(新潮日本古典集成)による。