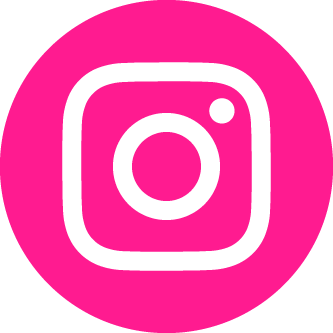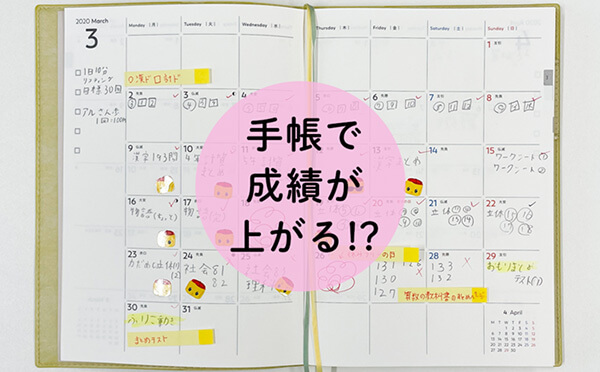息子のペースを尊重すべきでしょうか【前編】[教えて!親野先生]
お気に入りに登録
でも、これが親子の苦しみの始まりなのです。
この親の願いが、結果的に子どもを悩ませ苦しめ、親自身も悩み苦しむことにつながるのです。
「人より早くならなくてもいいから、せめて人並みには……」と言っても、その「人並み」というのができないのです。
親は、たいした要求をしていないつもりでいます。
でも、要求されるほうにしてみればすごく難しいのです。
親にとっては低い壁に見えても、子どもにとってはすごく高い壁なのです。
人は誰でも、大人も子どもも、自分ができないことを少しでもできるようにするということはとてつもなく難しいことなのです。
大人にとっても、自分にできないことをできるようにするのは難しいことです。
親は自分の課題についてはすっかり忘れて、子どもにはいろいろなことを求めます。
そして、日々叱ることが多くなります。
叱られることが多くなると、子どもはストレスがたまります。
それは、必ずどこかで出るようになります。
叱られることが多くなると、子どもは何事にも自信がもてなくなります。
場合によっては、一生残るトラウマになることもあります。
叱られることが多くなると、子どもは親の愛情を疑うようになります。
親子関係にヒビが入ったり、親を恨んだり疎んじたりということにもなりかねません。
言い続けても、叱り続けても直りません。
それをはっきり理解すべきです。
今あなたが困っているマイペースなその子のことを、ちょっと頭に思い浮かべてみてください。
あなたが、これからずっと言い続ければその子は直ると思いますか?
とてもそうは思えないはずです。
それに、世の中には私を含めてマイペースな人間は無数にいます。
大人でも子どもでもいます。
会社に行けばどの職場にも必ず何人かはいますし、学校に行けばどのクラスにも必ず何人かはいます。
でも、そういう人たちがそれでものすごく困っているかというと、そんなことはないのです。
私自身も、それで特に困ることなどありません。
いざとなれば何とかやるのですから。
普段は食事に長い時間がかかる私でも、現役教師の時には給食を食べるのは早かったです。
教師は非常に忙しいので、ゆっくり給食を食べていることはできないのです。
けんか中の子どもの話を聞いたり、その日のうちに返さなければならない連絡帳に返事を書いたり、次の授業の準備をしたりと、とにかくやることは山のようにいっぱいあるのです。
ですから、マイペースの私でも必要なときにはそれに応じて対応できるのです。
このように、誰でもいざとなれば何とかやるのです。
マイペースな子どもたちも、いざとなれば何とかやるのです。
学校生活のなかで、マイペースで実質的にすごく困ることなどないのです。
私が教師をしていたときもマイペースな子は何人もいましたが、それですごく困るということなどありませんでした。
それは、親の心配のなかにだけあるものなのです。
実態のない恐れです。
それが必要以上に膨らんでしまっていることが多いのです。
家でも学校でも、そういう子には、親や教師がその度に促してやればいいだけのことです。
「がんばれ、がんばれ」「もう少しだから、急ごうか」「もうちょっとだから、やってしまおう」「3時30分までにやろう。用意、始め!」「ストップウオッチで測ってみるよ」「タイマー10分セットしたよ。用意、ドン」
このように言ってやればいいのです。
しかも、できるだけプラス思考の言い方で促すことが大事です。
そのとき、「何度言ったらわかるの!」「なんで、そんなに遅いの!」「そんな遅いと学校に行けないよ!」などと、余分なことを言わないことです。
どうせ、言ってもムダなのですから。
 『親力革命』「親」であることにふと迷ったときに読む本(講談社)
『親力革命』「親」であることにふと迷ったときに読む本(講談社)
Benesse教育情報サイトの人気コンテンツ「教えて!親野先生」が一冊の本になりました。子育ての悩みは多様に見えて、実は意外と似ているものです。『親力革命』のなかに、今のあなたの、または将来の悩みを解決するヒントが隠されているかもしれません。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 学校のことを話さない……小学生の我が子への対応法や注意すべきポイント
- 入試から高校入学まで 第3回 「学力のイメージ」を変えてください[高校合格言コラム]
- 【理科が苦手】好きになるために家庭でできることは?
- 手帳の使い方次第で時間管理力・計画性が身につく!? 子どもが手帳を使う5つのメリットと身につく力とは
- 入試から高校入学まで 第1回 引き続き学力アップに努める[高校合格言コラム]
- 絵日記・日記 書くテーマの見つけ方、表現を膨らませるためには?
- マイペースタイプの子が「成績のいい子」か「成績の悪い子」になる分かれ道! 大人になっても使える勉強法
- 入試から高校入学まで 第2回 勉強のリズムは維持[高校合格言コラム]
- 暑いところで遊ぶとすぐに顔が赤くなる。原因と対策法は? 小児科医が回答!