【5月の高1生は要注意!】ありがち失敗体験談&「さりげなく」が効く保護者の声かけ例
- 大学受験

高校に入学したばかりのころの緊張がほぐれ、お子さまも高校生活に少し慣れてきたのではないでしょうか。
5月には、多くの高校で最初の中間テストが行われます。
高校で初めての中間テストでいい成績を残し、今後の学習に弾みをつけたいもの。
しかし、高校生活に慣れてきたとはいえ、まだまだ高校式の学習や生活が身に付いていないお子さまもいらっしゃることでしょう。
そこで今回は、この時期によくある失敗を先輩大学生に教えてもらいました。
また、保護者のかたが、どんな声かけをすればよいのか、あわせて紹介しますので、高1の5月を上手に乗りきる参考にしてください。
あるある失敗 その1 部活や行事で忙しく、勉強を後回しにしてしまった!
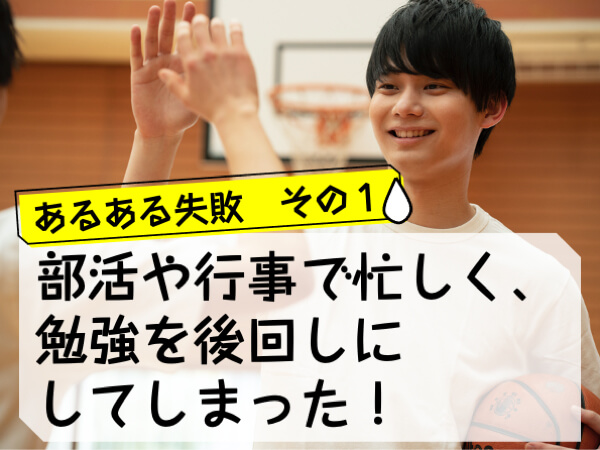
高校で部活を始めると、その練習などで大いに忙しくなります。
また、一部の高校ではこの時期に学園祭や体育祭などの行事が行われる場合もあり、その準備をしなければならないことも。
そうなると、練習や準備で疲れ果て、家に帰っても睡魔との戦いになってしまい、とても勉強どころではありません。
部活の大会に向けた本格的な練習が始まったため、勉強時間があまり取れなくなりました。おかげで苦手教科はかなり酷い点数に…。時間がなくても苦手なところは重点的にやっておけばよかったです。
(岐阜県 KY先輩 神奈川大経営学部)
学園祭が始まるとクラスの学園祭準備の居残りはもちろん、部活動の出し物の準備もあり、放課後に勉強できる時間がほとんど確保できませんでした。おかげで定期テスト1週間前になって焦って勉強していました。
(千葉県 TK先輩 明治大国際日本学部)
部活は週6日。まとまった勉強時間がとれず、テスト前に慌てて勉強することが多かったです。短時間でよいので、毎日少しずつ暗記するだけでも、精神的には余裕が出ると思います。
(岡山県 YN先輩 兵庫県立大工学部)
学校の行事や部活が忙しい時は、時間の使い方や、メリハリをつけた学習が重要になってきます。
たとえば、以下のような声かけを参考にしてみてください。
・部活(行事の準備)、がんばっているね。
・どうやって勉強を進めるか、自分で決めた?
まず、お子さまが日々学校でがんばっていることを認めて応援しましょう。
部活や行事にも全力を注ぐことで、「やりきった」という気持ちから、勉強へと切り替えやすくなります。
また、日々の学習について、何をどれくらいやるのかルールを自分で決めてそれを達成することで、自信がつき今後の学習の糧となります。
もしまだ自分でルールなどを決めていない場合は、ルールを決めることを促すとよいですね。
あるある失敗 その2 高校生活にも慣れてきたし、それにまだ高1だし大丈夫…と油断してしまった!
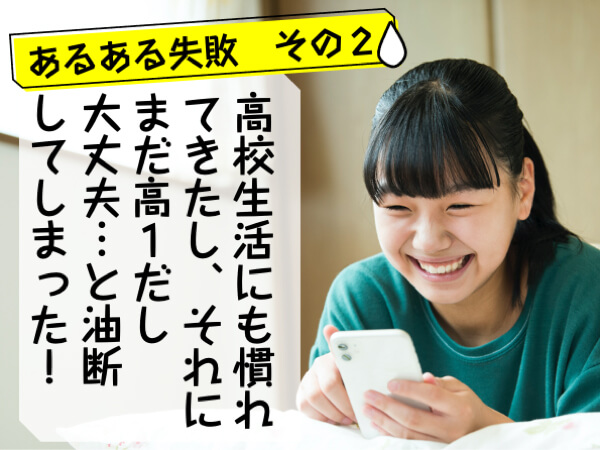
少しずつ高校生活に慣れてくると、学習に油断が出てくることも。
また、大学受験まではまだ時間があるため、学習をつい後回しにしてしまいがちです。
テスト前の2週間が、課題だけで手一杯になってしまい、基礎が頭にまったく入っていないままテスト本番を迎えることになってしまいました。余裕をもって勉強計画を立て、予定通りにいかなかった分の埋め合わせをする日を決めておくとよいと思います。
(茨城県 KM先輩 北海道大医学部)
まだ1年生だからと考えて、きちんと勉強しないでテストを受けたため、苦手な教科の点数が伸びず成績もあまり良くなかったです。推薦入試は高校1年生の成績も含まれるのでしっかり勉強した方がいいです。
(神奈川県 KH先輩 昭和薬科大薬学部)
高校生活にも慣れてきて少しサボりがちに。本が好きだったので学校の図書館の小説を読みあさっていました。取り返せるくらいではあったのですが成績はダウン。やりたいこととするべきことのメリハリをもう少しつけるべきでした。
(沖縄県 WY先輩 鹿児島大理学部)
推薦入試(総合型選抜・学校推薦型選抜)では、学習成績の平均値(評定)によっては出願自体ができないこともあるので、高1から良い成績をとっておくことに越したことはありません。
それでいて、高校生活に慣れてくると油断しがちなので、気を引き締めて取り掛かることが重要です。
お子さまに油断している様子が見られたら、たとえばこんな声かけをしてみましょう。
・高校や大学で一番やりたいこととか、勉強したいことってある?
・(お子さまが◯◯を学びたい、などと言ったら)それって面白いね! どんな大学で学べるのかな。
やりたいことがあれば、自然とそれに向けてがんばれます。
しかし、まだやりたいことがなかったり、絞りきれていない高校生も多いもの。
普段の会話のなかで、高校や大学でやりたいことに自然と気付いたり、見つけたりするきっかけを与えるように意識してみるのがオススメです。
あるある失敗 その3 わからないことをそのまま。苦手ばかりがんばる…勉強のバランスが取れなかった!
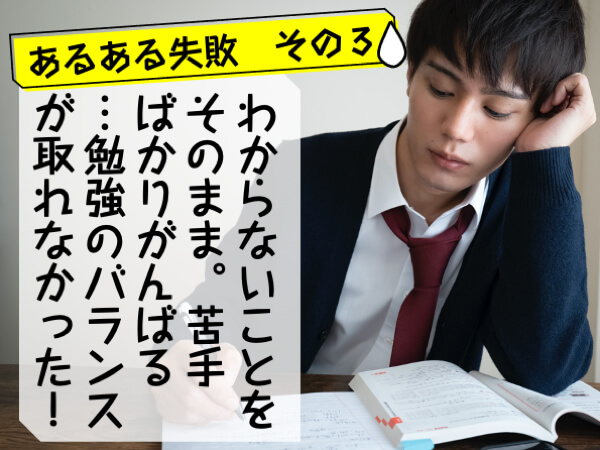
苦手な勉強は誰でもやりたくない。
ただ、放置したままでいると、その苦手はどんどん大きくなっていきます。
特に数学などは積み上げ型の教科です。習った知識を使って問題を解いていくので、どこかでつまずくと、その知識を使った学習でもつまずいてしまいます。
また、反対に苦手ばかりに注力してしまい、全体的な成績が下がってしまうケースもあるようです。
数学でわからないところをそのままにしていたところ、どんどん内容が難しくなってますます苦手に。2年生になってから高1の内容を復習し直すのに結構時間がかかってしまいました。
(愛知県 TY先輩 日本赤十字豊田看護大看護学部)
テスト勉強の計画を立てたものの、やりたい勉強を詰め込みすぎて予定通りに終わらないものばかりでした。予備日は必ず作っておくべきです。
(福岡県 YN先輩 西南学院大人間科学部)
突出して苦手な科目に時間をかけすぎて、それ以外の科目は一夜漬けでなんとかする…と思っていたら、結局寝落ちしてほとんど何もできないままテスト本番を迎えました。きちんと学習計画を立てるべきでした。
(山口県 FS先輩 香川大経済学部)
どの科目に力を入れるか、自分の苦手は把握していても、時間配分まではうまくいかないこともあるでしょう。
また、高校1年生の5月の段階では、まだ学習のペースがつかめず、スケジュールも上手に立てられなかったりします。
こんな時は保護者のかたのサポートが有効です。
たとえば以下のような声かけをしてみましょう。
・苦手な◯◯をやるなんて、すごい!
・勉強のやり方がわからない科目ってある?
そもそも、大人でも苦手なことはやりたくありません。
高校生が苦手な科目に取り組むこと自体が、すごいこと。そうした様子が見られたら、大いにほめてください。
また、学習のペースがうまくつかめていない様子が見られたら、まだ学習方法自体を模索中なのかもしれません。
人によってやりやすい学習方法は違うもの。話を聞いて試行錯誤の手助けをするのも手です。
お子さま自身が考え、決めて、実行するサポートに徹する気持ちが大切です。
失敗を高校生活や大学受験の力に変えて
新学期が始まって約1か月。
まだまだうまく生活をコントロールできないこともあるでしょう。
ここでしっかり経験を積み、生活や学習に上手に取り組むことができるようになれば、今後の高校生活の大きな力になります。
そして、その力は大学入試に立ち向かう力にもつながります。
お子さまのことを信じて見守りつつ、さりげない声かけ、サポートをしていきましょう。
- 大学受験















