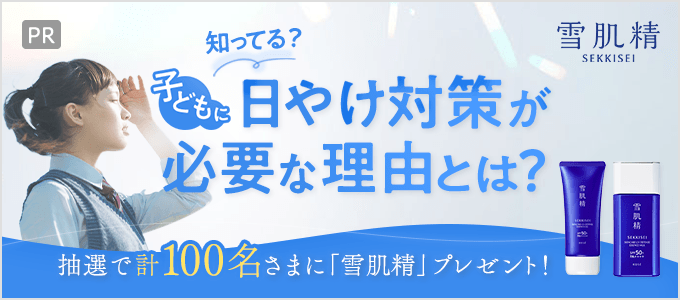3つの部品で正解を導く! 「なんとなく違う」減点を防ぐ採点基準
お気に入りに登録
塾に行かずに受験する家庭はもちろん、塾での勉強を自宅学習で補うためにも保護者の協力は欠かせないが、悩みもつきものである。国語の記述問題で解答・解説を見て、子どもの答えと微妙に違う場合、どうやって点数を配分したらよいのか。小4男子の保護者から寄せられた相談に、平山入試研究所の小泉浩明氏が明快なアドバイスをくれた。
***
【質問】
文章問題で解答・解説を見て、子どもの答えと微妙に違う場合、○(マル)か×(バツ)か、または△(サンカク)なのか、悩む場合があります。このような場合、どうしたらよいのでしょう?
【小泉氏のアドバイス】
まず知っておかなければならないのは、答案の記述は「理由+キーワード+文末」の3つの部品から成り立っていることです。「文末」は「なぜですか?」に対する「~から。」、「キーワード」は「答案のカギになる言葉」、「理由」は「キーワード」に対する理由です。それぞれの部品に対して、文末10%、キーワード40%、理由50%などと点数を分配していきましょう。答案の部品が他にも必要な場合があります。「誰が(何が)」とか「誰に対して(何に対して)」などです。これらは、答案によって絶対に必要だったり、不要だったりします。必要な場合のみ、配点を変えて計算すれば良いでしょう。
次は減点の基準です。キーワードが2つあるのに1つしか書いていない場合には、4点中2点しかあげられません。気持ちなどをあまり明確に表現できていない場合などには、かなり減点します。方向性が違う場合は、減点というよりも答案全体を0点にすべきです。また、誤字脱字や、「てにをは」を含む言い回しがおかしい場合の基準も必要です。
それぞれの基準を決めると、かなりしっかりした採点ができるようになります。お子さまの書いた各々の部品を模範解答の部品と比べる時、お子さま自身もなぜ減点されたのかを十分に納得できると思います。「なんとなく違う」減点と、「ここがこう違うから」の減点では、後者のほうがはるかに説得力があるのです。「何らかの基準を持つ」ということが大切なのです。













![算数の図形の問題で、補助線を見当違いのところにひいて、長く考えていることが多い[中学受験]](/_shared/img/ogp.png)