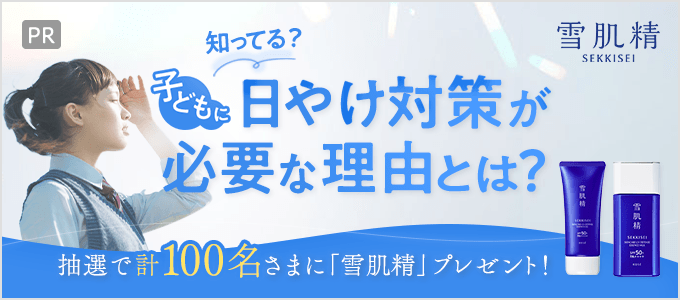第8回 「私立中学」向きの子どもと「公立中高一貫校」向きの子ども
お気に入りに登録
今回は小学4、5年生の保護者がこれから後、国私立中学「受験」と公立中高一貫校「受検」のどちらに軸足を置いて力を注ぐのか、方向性を決める判断基準の1つをお話しします。
判断の根幹は親の価値観、生き方にあります。次に私立学校の授業料等の費用を継続して支払い可能な経済力があるか否かにあります。それらを踏まえたうえで、さらに子どもの能力、気質、性格をどのように見るかの判断が必要です。
30年以上にわたる中学受験指導の経験から、受験偏差値上位校に合格する子どもには以下に記す5つの要素が存在しています。
5つの要素
| (1) | 抽象的論理思考ができる子ども。 |
| (2) | 物事を完璧(かんぺき)に処理せずにいられない子ども。ここまで練習してやったのだから100点でなければ自分が納得しない子どもです(内的達成基準または絶対的位置基準)。 |
| (3) | 負けず嫌いで、競って上位にはい上がろうとする気質をもった子ども。自分の見える範囲で1番になろうとがんばります(外的競争基準または相対的位置基準)。 |
| (4) | 素直、まじめ、集中力が継続する子ども。 |
| (5) | 塾の費用を賄える経済力があり、テストやスケジュール管理など惜しみなく協力支援ができる親の子ども。 |
これらのすべてが備わっている子どもは、そんなにいるものではありません。
受験競争を勝ち上がり、私立中学に入学する子どもは、(1)(2)(3)のうちの少なくとも2つと(5)を備えています。(4)があればさらに有利です。普通の子どもは(1)ができていません。塾の指導を通して抽象的論理思考をつけることはできますが、限界があります。もともとの素質や幼児からの親のかかわり方と家庭教育の質によってかなり限定されてしまいます。抽象的論理思考の芽がある子どもは、塾の適切な学習指導を受けることによって放物線を描くように大きく伸びる場合があります。その芽のない子どもは緩やかな直線的上昇にとどまりますから、二者の差はますます広がるばかりです。「こんなに勉強しても成績が伸びないのは、どうしてだ」という親がいますが、そもそも素質がないか、素質があっても伸びる芽を育む家庭環境に恵まれなかったというしかありません。
公立中高一貫校受検では当然(5)はあるに越したことはありませんが、なくても大丈夫です。(1)と(4)の存在は重要です。(2)と(3)はなくてもかまいません。それよりも、私立中受験の子ども以上に公立中高一貫校の受検生は、知的な興味関心が豊かで、疑問をもって探究する意欲と行動力の存在が望ましいといえます。
抽象的論理思考が備わらない子どもが多いわけですから、その子の親はどのように方向性を定めればよいのでしょうか。経済力があり協力支援を惜しみなく使える親は、私立中受験を考えたほうが無難です。学校選択を誤らなければ大学受験に有利に働きます。(4)と(5)がない子どもの場合は、「ダメでもともと」という気持ちで公立中高一貫校受検にチャレンジするか、地元の公立中学校に進学して子どもの成長を待つことになるでしょう。(2)(3)(4)のうち2つが存在している子どもなら、コツコツと努力を積んでいきますから、親の協力のもと適切な教材を選択し、効果的な学習活動を今後続けていけば公立中高一貫校合格への道が開けます。