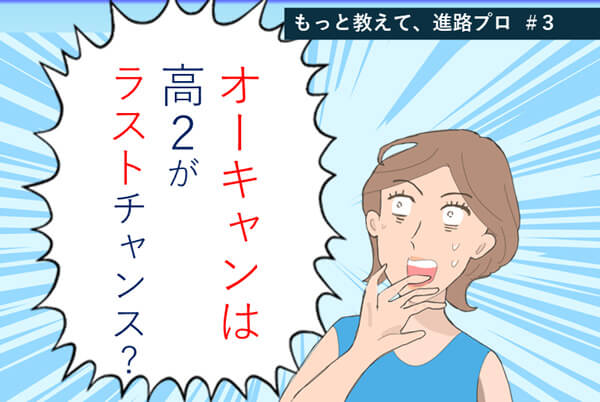指図もダメ?[中学受験]
お気に入りに登録
受験に関する本や塾の先生方からさまざまな情報を得ることは、非常に重要なことである。中学受験に関する本や雑誌はたくさんあるし、受験のテクニックやノウハウを教えてくれる研究会なども多い。
ちなみに私もそういった研究会をやらせていただいているが、すばらしい内容のものも多々あると思う。
問題は情報を取捨選択することで、お子さまが使えるものとそうでないものに分類し、有効なものだけを選んで参考にしていくことが大切であるということ。
それからもう一つ。教務的な情報に限って言えば、お子さまに対してはあくまでもアドバイスであって、指図ではあってはいけないということだ。
たとえばお子さまが塾で習った「相似の解き方」と、お母さんが受験雑誌で読んだ「相似の解き方」が違ったとする。
そんな時に母親のほうから「この方法でやりなさい」と言われると、受験生としてはムッとするであろう。
なぜなら、「受験した経験もないのに、その方法が良いとなんでわかるのか?」という気持ちになるからである。
もちろんご両親が中学受験を経験している場合もあろうが、そんな場合でも「お父さんが受験したのは随分前だから、もう古いんじゃないの?」という思いはお子さまにあるだろう。
それほど塾とお子さまの信頼関係は強いのであり、そのくらい強くなければ困るのである。
この強い絆を断ち切るほどの教務的な信頼感をお子さまがご両親にもつためには、よほどしっかりした経験や知識がご両親になければならない。
しかしそこまでの経験や知識がないのに、親の権威で無理に押し付けようとする場合がある。非常に顕著な例は、「お父さんは理系で数学が得意だった」ということで、小学校の学習段階では習っていない「方程式」で受験の算数を教え出す場合だ。
かくてお子さまの算数は支離滅裂になり、お父さんの権威も地に落ちることになる。無理なことを強いると、親子関係が気まずくなってしまう例であろう。
いろいろな知識がたまってくると、つい使ってみたくなるものだ。
ましてお子さまが試験の結果に苦しんでいると、つい「算数では、最後の問題でも小問1はやさしいことが多いのよ。とにかく手を付けなさい」と言ってしまいがちだ。
確かに正しいことなのだが、お子さまにとってはやはり耳障りな指示に聞こえる。
こんな場合は指示ではなくて、アドバイスにしておくべきであろう。つまり「手をつけたほうが良いみたいよ」と言うこと。
非常に控えめだが、かえって控えめなほうが「やってみようかな?」という気になるものだ。
そして万一その方法をお子さまが採用しなくても、無理強いしてはいけないのである。
ちなみに私もそういった研究会をやらせていただいているが、すばらしい内容のものも多々あると思う。
問題は情報を取捨選択することで、お子さまが使えるものとそうでないものに分類し、有効なものだけを選んで参考にしていくことが大切であるということ。
それからもう一つ。教務的な情報に限って言えば、お子さまに対してはあくまでもアドバイスであって、指図ではあってはいけないということだ。
たとえばお子さまが塾で習った「相似の解き方」と、お母さんが受験雑誌で読んだ「相似の解き方」が違ったとする。
そんな時に母親のほうから「この方法でやりなさい」と言われると、受験生としてはムッとするであろう。
なぜなら、「受験した経験もないのに、その方法が良いとなんでわかるのか?」という気持ちになるからである。
もちろんご両親が中学受験を経験している場合もあろうが、そんな場合でも「お父さんが受験したのは随分前だから、もう古いんじゃないの?」という思いはお子さまにあるだろう。
それほど塾とお子さまの信頼関係は強いのであり、そのくらい強くなければ困るのである。
この強い絆を断ち切るほどの教務的な信頼感をお子さまがご両親にもつためには、よほどしっかりした経験や知識がご両親になければならない。
しかしそこまでの経験や知識がないのに、親の権威で無理に押し付けようとする場合がある。非常に顕著な例は、「お父さんは理系で数学が得意だった」ということで、小学校の学習段階では習っていない「方程式」で受験の算数を教え出す場合だ。
かくてお子さまの算数は支離滅裂になり、お父さんの権威も地に落ちることになる。無理なことを強いると、親子関係が気まずくなってしまう例であろう。
いろいろな知識がたまってくると、つい使ってみたくなるものだ。
ましてお子さまが試験の結果に苦しんでいると、つい「算数では、最後の問題でも小問1はやさしいことが多いのよ。とにかく手を付けなさい」と言ってしまいがちだ。
確かに正しいことなのだが、お子さまにとってはやはり耳障りな指示に聞こえる。
こんな場合は指示ではなくて、アドバイスにしておくべきであろう。つまり「手をつけたほうが良いみたいよ」と言うこと。
非常に控えめだが、かえって控えめなほうが「やってみようかな?」という気になるものだ。
そして万一その方法をお子さまが採用しなくても、無理強いしてはいけないのである。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 指図もダメ?[中学受験合格言コラム]
- 早稲田大学 スポーツ科学部(1) スポーツビジネスを通じて世界で活躍する人材を育てる[大学研究室訪問]
- 江戸川大学 メディアコミュニケーション学部 こどもコミュニケーション学科(2)言葉を信頼する人間を育てるために [大学研究室訪問]
- 「知らない人について行っちゃダメ」の危険な落とし穴 子どもを犯罪から守るために伝えるべき「最も重要でわかりやすい」ポイント【専門家監修】
- 青山学院大学 教育人間科学部 心理学科(1) 音楽と心の関係を科学的に探究する[大学研究室訪問]
- 津田塾大学学芸学部 国際関係学科多文化・国際協力コース(1) 自分のテーマを、自分の言葉で語れる--大学でそんな力を付け、世界の舞台へ[大学研究室訪問]
- トマトはダメでもケチャップは好き 小学生の食べ物好き嫌い事情
- 東京工業大学 地球惑星科学専攻(1)新しい分野だからこそ学生にも「世界初」の可能性が[大学研究室訪問]
- 淑徳大学 総合福祉学部 社会福祉学科 (1) 社会福祉士を育成しながら 現場の経験を生かして社会保障政策などを研究[大学研究室訪問]