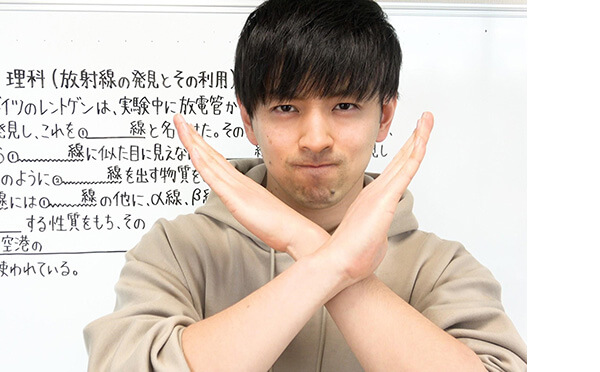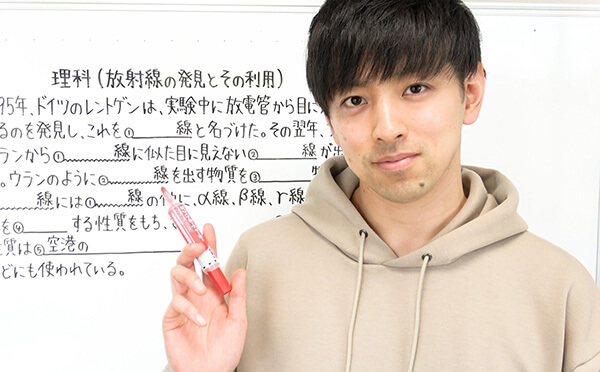大学教授に聞く 学習能力の向上に役立つ「ディベート」とは?
お気に入りに登録
学習能力の向上に役立つとして、教育現場で注目されているディベート。ディベートとはどのようなものなのか、日本ディベート協会の専務理事、全国高校英語ディベート連盟の副理事長であり、立教大学経営学部教授でもある松本茂先生に教えていただきました。

福沢諭吉や宮沢賢治も行っていたディベート
中・高校生のみなさんは、学校の授業の中でクラスメイトとディスカッションをしたことがあると思います。意見の一致や情報の交換を目的としているディスカッションに対し、ディベートでは、「わが校は制服を廃止すべきである」といった論題に対して肯定(Yes)の立場をとる話し手と、否定(No)の立場をとる話し手が、聞いている人たちを論理的に説得するために議論をするのです。
ディベートは、古代ギリシャにさかのぼり、紀元前から行われてきました。日本で現在行われているような形式のディベートが行われたのは、明治維新のころです。福沢諭吉が外国から、民主主義とともにディベートを日本に持ち込み、三田演説会(福沢諭吉らを中心に発足した演説や討論の会)でディベートをしたという記録が残っています。
また、作家の宮沢賢治も、花巻農学校で教師をしていたころに、授業にディベートを取り入れ、そのうえ、社会問題について生徒とともにディベートを行ったそうです。
議論をすることで、新しい発想を知ることができる
ディベートというと、何か特別なもののように聞こえるかもしれませんが、決してそうではなく、私たちが暮らす社会のあちこちで頻繁に行われているものです。
たとえば、検察側と弁護側が裁判長らを説得するために議論する裁判、政治の世界における党首討論、学術会議での討論などもディベートの一種です。
また、企業では、新製品の開発するときに、市場のニーズやコストなどを調べて「本当に商品化すべきか」といった議題で議論することもあります。そのため、社員にディベート研修を課する企業、あるいは社内でディベート大会を行う企業などもあります。
ディベートを成立させるために必要な要素は、「論題」「ディベーター(議論をする人)」「聴衆(議論を聞く人・評価する人)」の3つです。
論題とは、ディベートにおけるテーマのことです。「ディベーター」とは、ディベートにおける話し手のことです。議論の聞き手となるのが「聴衆」あるいは「審査員」です。
ディベートの基本的な進行形式(フォーマット)
実際にディベートを行う際には、進行形式(フォーマット)を決めます。フォーマットはさまざまですが、以下の4つが含まれることが多いのです。それは、「立論(りつろん)」「質疑応答(しつぎおうとう)」「反論(はんろん)」「反駁(はんばく)」です。
立論では、「論題を採択すべきである」「論題は採択すべきでない」という主張とその理由(論点)を述べ、証拠となる資料を提示します。
立論のあとに質疑応答を行います。質疑応答の目的は、相手の立論の内容の不明な点を明らかにしたり、大事なポイントを改めて確認したりすることです。わからないことを、わからないままにしておかないことが大切です。また、ディベートの上級者になると、質疑を通して、反論の糸口を見つけることもできるようになります。
質疑の次に行われるのが、反論です。立論で出てきた議論に対して、反論することです。立論の中で出てきた主な議論や証拠資料に対して、反論をします。
そして、反論の後に行われるのが反駁。この中では、相手の反論によって弱まった立論の議論を建て直します。相手側の反論で否定された論点に対して、再度反論をして、よりわかりやすく立論に議論を立て直し、補強します。
立論、質疑応答、反論、反駁。この4つを肯定側と否定側が同じ時間配分で行い、その後、審判がディベートの勝ち負けを判定し、講評を行って終了となります。
取材協力:日本ディベート協会 japan-debate-association.org/
全国高校英語ディベート連盟(HEnDA) http://www.henda.jp/Pages/default.aspx
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 大学教授に聞く 「ディベート」をする意義とは?
- 【自由研究】生ごみでたい肥をつくり、有機農業について調べる <中学生>
- 「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]
- マイクラで子どもの能力が伸びるのはなぜ?Minecraftカップ2020全国大会の審査員に聞いてみた
- 【自由研究テーマ 中学生】スポーツドリンクで燃料電池をつくり、燃料電池について調べる
- 入学祝いのお返しは、いつ何を贈ればいい?入学内祝いの相場とマナー
- グリット(やり抜く力)は、環境や才能に関係なく自分で伸ばすことが出来る能力 ボーク重子さんに聞く!これからの子どもを幸せにする「非認知能力」の育み方~Lesson6 グリット(やり抜く力)
- 【自由研究テーマ 中学生】温度やしつ度によるカビの生え方のちがいを調べる
- 入学式にどんなバッグを持っていけばいい?サブバッグは?持ち物とマナーを知っておこう