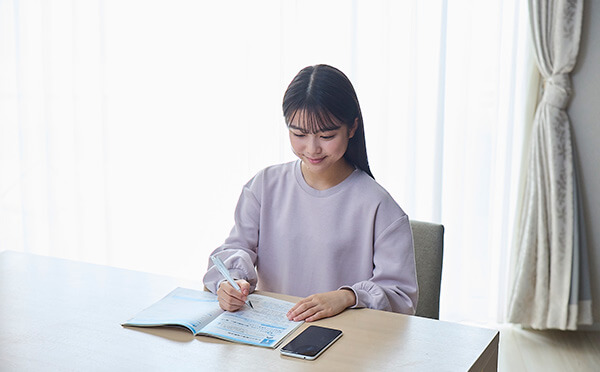定期テスト勉強、範囲発表前でも半数近くが、2週間前には準備開始
お気に入りに登録
アンケート期間:2013/06/12~2013/06/18 回答者数:1,916人
アンケート対象:本サイトメンバーの中学1年生~高校3年生の保護者のかた
※百分比(%)は小数点第2位を四捨五入して表示した。四捨五入の結果、各々の項目の数値の和が100%とならない場合がある

今年度最初の定期テストの結果が戻ってくる頃、全国の中学生、高校生のご家庭に、お子さまがどのようにテスト対策を行ったのか、また保護者がどのように関わったのかを伺いました。そこで明らかになった、「勝ちパターン」と「負けパターン」を、お見せします。
範囲が発表されなくても、2週間前には準備開始!
定期テスト勉強は、テスト何日前から始めればよいのでしょうか。多くのお子さまは1週間前くらい、または2週間以上前から始めているようです(図1参照)。
【図1 お子さまが定期テストの準備を始めるのはいつですか?】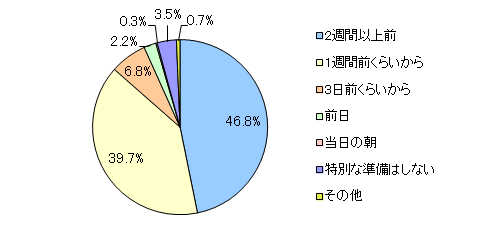
なぜその時期から始めたのか、理由も聞きました。「1週間前くらいから」始めた人が挙げた理由は、その頃に「部活が休みになるから」、「範囲が発表されるから」。この2つの意見が断然多く見られました。
一方、「2週間以上前」と答えた保護者の理由で多かったのは、「学校から2週間分の計画表をもらうから」、「進研ゼミのスケジュールに合わせて」、「塾の定期テスト対策授業が始まるから」というものでした。
部活が休みになったり、範囲が発表されたりするのが1週間前だとしても、学校やテスト勉強のプロのおすすめは、2週間前からのスタートであることがうかがえます。また、「そのくらいからやらないと間に合わないから」「範囲をひと通りこなすために必要だから」など、お子さま自身の判断で決めているケースが見られるのも特徴的です。
後悔したくないなら、開始時期は大切です。このアンケートでは、テストの準備を始めた時期に加え、それが保護者から見て満足のいくものだったのかどうかも尋ねています。開始時期に「とても満足」と答えた人の多くは、2週間くらいかそれ以上前から準備をした人です。1週間前からという人はほとんどいませんでした。反対に、「とても不満」と答えた人のうち、45%は1週間くらい前から始めた人でした。1週間の準備期間では、後悔が残る結果となってしまいがちのようです。テスト準備は、たとえ範囲が発表されていなくても、自主的に2週間程度前から始める、そういった姿勢が重要だといえそうです。
なかには、「自分は短期集中型だから」というお子さまもいるかもしれません。1週間前から始めて、その分2週間前から始める人の倍やればトータルでは同じ……理論的にはそういえるかもしれません。しかし、テスト準備を遅く始める人ほど、1日の学習時間が多いどころか、むしろ短い傾向にあるということもわかりました。たとえば、テスト対策中に1日3時間以上勉強する人は、2週間前くらいから準備を始めるお子さまでは36.9%いますが、1週間くらい前からのお子さまでは27.1%にとどまります。
1日の勉強時間、3時間未満ではあとで悔やむことに……
テスト対策中の1日の勉強時間について、もう少し詳しく見ていきましょう。
【図2 定期テスト対策中の家庭での平均勉強時間】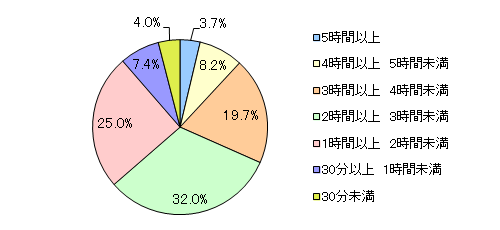
1日平均「2時間以上 3時間未満」の人の割合が最も多く32.0%、次に多いのは「1時間以上 2時間未満」で25.0%となっています(図2)。この時間数を、保護者はどのように評価しているのでしょうか。
【図3 お子さまのテストの取り組み時間について、どのように考えていますか? (取り組み時間別)】
取り組んだ時間別に、その時間数に対する保護者の満足度を見てみると、当然のことながら、取り組み時間が少ないほど、それに満足する割合も低くなっています。「2時間以上 3時間未満」では、「とても満足」と「まあ満足」を合わせて45.8%にとどまり、「やや不満」と「とても不満」の合計を下回ります。「3時間以上 4時間未満」で初めて、「満足」のほうが上回るようになります。
2学期制は出題範囲が広いが、時間を余計にかけているわけではない
「定期テストに関して日頃感じていること」を自由に回答してもらうと、2学期制の学校の保護者のかたが、出題範囲が広くて子どもの負担が大きいのでは、と懸念する内容が多く見られました。定期テストの回数は、2学期制で年間4回、3学期制で5回というのがスタンダードのようです。
そこで、テスト準備をいつから始めるか、テスト対策を1日あたり何時間行うか、2学期制の学校の生徒と3学期制の学校の生徒で比べてみました。その結果、いずれも大きな差は見られませんでした。つまり出題範囲は確実に広いのに、ほとんどの子どもたちは、3学期制の学校と同じ程度の準備期間、勉強時間だけで乗りきってしまっています。よいのか悪いのかはわかりませんが、それが実態なのです。
保護者の出番! 夜食作り、山かけ、願かけ……?
最後に、「定期テストの対策について、お子さまに協力していることはありますか?」という質問に寄せられた声ご紹介したいと思います。
教科の内容を教えているという保護者が多かったのは、「時事問題」「英語」の2つ。「時事問題に対応するため、NHKのニュースを毎朝見る(高2の保護者)」という保護者もいます。
さらに踏み込んだ協力をしている保護者もいます。
●範囲と提出物の紙を見せてもらい、そこから出そうなところを教える(中1の保護者)
●やることとスケジュールを(子どもと)一緒に考える(中1の保護者)
しかし、「反抗期なので何もできない」(高1の保護者)とあきらめかけている保護者も多いのではないでしょうか。そのような場合には、もっとさりげない、こんな協力の仕方ならどのご家庭でもできそうです。
●弟や妹が邪魔しないよう早めに寝かせる(高3の保護者)
●リビングのテレビを消しておく時間を長くする(中2の保護者)
食事面での配慮は多くの保護者が挙げていました。
●食事をいつも以上にバランスよく、消化がよいものにするよう、心がけている(中3の保護者)
●運の付く食べ物を食べさせる(高3の保護者)
●朝食には(子どもの)好きなものを出す(高1の保護者)
また、「協力」というより「願かけ」に近いかもしれませんが、子どもがテスト勉強に励む間は、自分も家事をがんばるという保護者もいました。
●勉強タイムになったら、親は家事をし、子どもたちは勉強するように切り替える(中2の保護者)
●(子どもの)勉強中は家事や新聞、本、ペットの小屋や水槽掃除など、自分も遊ばず用事をする(中2の保護者)
ピリピリしがちな定期テスト期間、お子さまに「ちゃんと勉強しなさい」とプレッシャーをかけるより、がんばる親の姿を見せるほうが、伝わるものがあるのかもしれません。今度の定期テストで、参考にされてみてはいかがでしょうか。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 【高校生】テスト前、高校生は毎日何分・どこで・どんなふうに勉強している?リアル調査
- 【体験談】迷った時の参考に。高校の芸術、何を選択する?実際はどう?
- 定期テストではいい点を取れるのに、模試や実力テストで実力を発揮できない理由
- 高校からも自宅で成績UP!塾なし勉強法【PR】
- 「五月晴れ」って何? もしかして、間違った認識をしているかも?
- 第3回 幼児の生活アンケート・国内調査 速報版[2005年]
- 大学受験をも左右する!? 新高1生が知っておくべき、正しい1学期の過ごし方とは?‐村山和生‐
- 「初めてのブラジャー選び」は小学生から!何歳から?保護者が知っておきたいバストのこと
- 第2回 大学生の学習・生活実態調査報告書 [2012年]