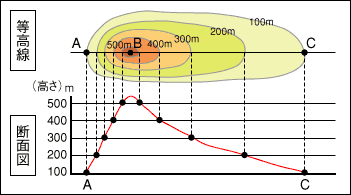【社会】等高線の間隔って何を表しているの?
お気に入りに登録
お子さまや保護者のかたが疑問に思われる頻度を★★★で示しています。
(頻度が高いほど★が多くなります。)
(頻度が高いほど★が多くなります。)
★★
等高線とは、地図上の土地の高さを表すもので、海面からの高さが同じ所を結んだ線を上から見たものです。地図に慣れていない場合、等高線を読みとる際に断面図を利用するとよいでしょう。
下の等高線とA-Cの断面図を見ると、等高線の間隔が狭いA-Bは急な斜面であり、等高線の間隔が広いB-Cは緩やかな斜面であることがわかります。このように等高線から断面図をかいてみると、等高線の間隔と土地の傾きには深い関係があることを理解できるはずです。
等高線の間隔と土地の傾きは、「広い=緩やか」、「狭い=急」という公式で暗記するのではなく、断面図で理解することが大切です。
4年生の後半から、等高線からわかる土地の高低と土地利用の関係まで考察する学習を行います。中学校になると地形図を使って地域の規模に応じた調査を行うようになります。等高線を断面図といっしょに理解しておくことは、地理的事象を多面的・多角的に考察する基礎として大切です。また、慣れてくれば、登山道などで楽なルートを選ぶことができるなど、実生活でも大いに役立ちます。