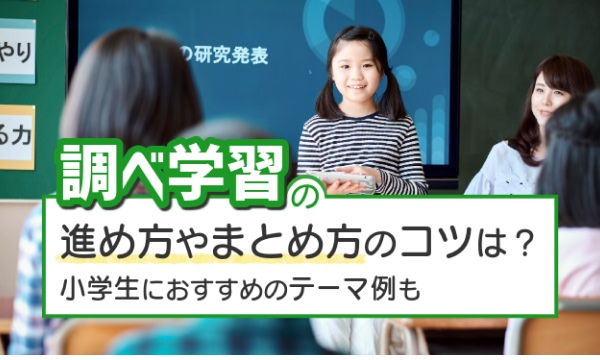【社会】3000分の1の地図と2万5000分の1の地図は、どっちが詳しい?
お気に入りに登録
お子さまや保護者のかたが疑問に思われる頻度を
★★★で示しています。
(頻度が高いほど ★が多くなります。)
(頻度が高いほど ★が多くなります。)
★
地図には、「3000分の1」とか「1:3000」などの数字がかかれています。これらを縮尺といいます。また、ものさしのようなメジャーは、「チャレンジ」では「縮尺を表すものさし」と呼んでいます。縮尺とは、地図上で実際の距離をどれだけ縮めたかを表したものです。
下に3枚の同面積の地図を用意しました。「400分の1」の地図を見ると、田中さんと井上さんの家の様子がよくわかります。「800分の1」の地図になると、田中さんと井上さんそして、郵便局を含めた8戸まで地図には載りますが、詳細はわかりません。また、「3000分の1」の地図になると、田中さんの家も井上さんの家も住宅地として表されてしまいます。つまり、縮尺の分母が小さい400分の1の地図が、地図上の建物や道路などが大きく、最も細かい部分まで表現できる地図ということになります。
中学校になると、身近な地域を地図を使って調べる学習をしますが、調査に使う地図の縮尺を、目的に合わせて選ぶ力が必要となります。詳細な地域の様子を調べるには、分母の小さい縮尺の地図を、県の地形の様子を調べるには、分母の大きな数の地図をといった選ぶ力が必要です。縮尺の考え方を、ぜひ小学生のうちに身につけさせたいものです。
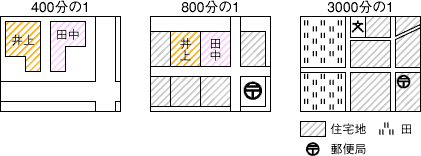
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 作文が苦手で、文章を書くとどうしてもワンパターンになってしまう[中学受験]
- 【社会】等高線の間隔って何を表しているの?
- 教育フォーカス│【特集25】主体的な学びの実現 ~「主体的な学び研究会」2019年度活動報告書 ~│エピソード 研究会メンバーのICEとの出会い|東京都立小山台高等学校 坂田 匡史
- マネすることはずるくない! 作文は借りてきた言葉でつくるもの
- 算数・数学の「思考力問題」が解けるようになるには?対策のポイントを解説
- 教育フォーカス│アクティブ・ラーニングを活用した指導と評価研究~授業レポート~│[第2回]自律的活動力を育てる~東京都立戸山高校SSH及び家庭基礎の実践[3/4]
- 「知らない人について行っちゃダメ」の危険な落とし穴 子どもを犯罪から守るために伝えるべき「最も重要でわかりやすい」ポイント【専門家監修】
- 今求められる「学習者目線の学び」とは?3人の教育関係者が語る《学び続けるために必要なこと》
- 教育フォーカス│【特集25】主体的な学びの実現 ~「主体的な学び研究会」2019年度活動報告書 ~│東京都立小山台高等学校 坂田 匡史 関連記事