98%のお子さまが健康!家庭ごとの取り組みは?
お気に入りに登録
健康維持のために心がけていること
このようにお子さまが健康であるためには、家庭でどんなことを心がけているのでしょう。回答者の皆さまには、項目ごとにあてはまるものを選んでいただきました。
【図3 お子さまの心身の健康のために、ご家庭で心がけていることはありますか】
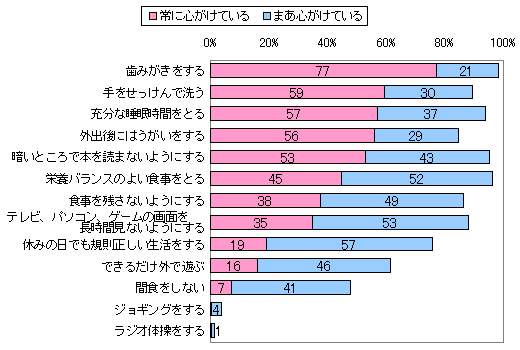
「常に心がけている」割合が最も高いのが「歯みがきをする」で77%。他を大きく上回っています。
そのあとに「手を石けんで洗う」(59%)、「十分な睡眠時間をとる」(57%)、「外出後にはうがいをする」(56%)と続きます。
比較的、毎日の習慣付けのしやすいものが上位に来ているようです。
逆に割合が低かったのは「間食をしない」(7%)、「ジョギングをする」「ラジオ体操をする」(各0%)。
「ジョギングをする」「ラジオ体操をする」は、子どもたちの日常にそぐわないからでしょう。また、「間食をしない」は「とても」と「まあ」を合わせると40%を超えています。
これは、気をつけてはいるものの毎日続けることは難しいといった背景がうかがえます。やったほうがよいとわかっていてもなかなかできないことは、どうしてもあるものですよね。
【図3 お子さまの心身の健康のために、ご家庭で心がけていることはありますか】
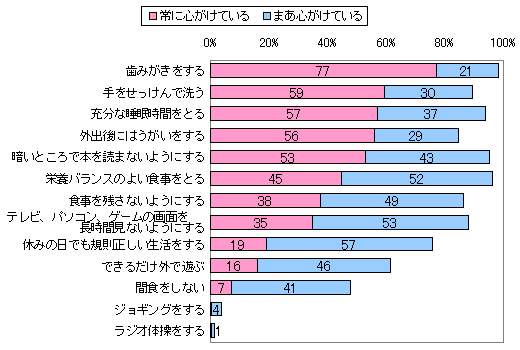
「常に心がけている」割合が最も高いのが「歯みがきをする」で77%。他を大きく上回っています。
そのあとに「手を石けんで洗う」(59%)、「十分な睡眠時間をとる」(57%)、「外出後にはうがいをする」(56%)と続きます。
比較的、毎日の習慣付けのしやすいものが上位に来ているようです。
逆に割合が低かったのは「間食をしない」(7%)、「ジョギングをする」「ラジオ体操をする」(各0%)。
「ジョギングをする」「ラジオ体操をする」は、子どもたちの日常にそぐわないからでしょう。また、「間食をしない」は「とても」と「まあ」を合わせると40%を超えています。
これは、気をつけてはいるものの毎日続けることは難しいといった背景がうかがえます。やったほうがよいとわかっていてもなかなかできないことは、どうしてもあるものですよね。
家庭ごとの工夫
最後に、皆さまが家庭で心がけていることの具体的な内容を伺いました。家族で一緒に取り組んでいる、こんな相乗効果があったというものを中心にご紹介します。
〈生活習慣、食事、運動など、主に身体面のケアを心がけている〉
〈主に心の面のケアを心がけている〉
皆さまがお子さまをしっかり見つめ、お子さまに合うことを工夫して取り組んでいる様子が伝わってきました。「健康を維持する」というのは結果としてそうなっていることが多く、何かを試みてすぐに効果が表れるとは限りませんし、同じようなことをしているつもりでもうまくいかない場合もあります。常日頃のお子さまに対する目配りがいちばん大切で、ときには根気よく、ときには臨機応変に、お子さまと向かい合っていくことで成し遂げられるものなのでしょう。……アンケートを拝見しながら、そんなことを感じました。
〈生活習慣、食事、運動など、主に身体面のケアを心がけている〉
- ●朝、自宅を出るまでの30分間はテレビを消すことにしました。すると、時計を見ながら自分で準備をするようになり、余裕をもって学校に行くようになりました。(小3)
- ●食事をしっかりとってほしいので、間食を加減している。また特に朝食をとってほしいので、時間のない朝はバナナやミニゼリーなどのデザートをつけている。子どもはデザート食べたさにがんばって食べきることが多い。(小1)
- ●徒歩15分のところに、大型ショッピングモールがあります。上り下りの坂道ですが、家族で行くときはできるだけ歩くようにしています。効果ははっきりわかりませんが、行く道で会話をすることにより、普段聞けないようなことが聞けたりします。(小5)
- ●運動が苦手でなかなか外に出ようとしないので、夏休みを利用して毎朝一緒にウオーキングをし、休日は父親と自転車で遠乗りしたりした。早起きの習慣がつき、睡眠も十分取れるようになった。学校の休み時間も外遊びをよくするようになった。(小5)
〈主に心の面のケアを心がけている〉
- ●接するときはいつも笑顔で。家族でよく笑いあうようにしている。(小学校入学前)
- ●なるべく家族で時間を合わせて食事をしたり、まだ甘えたい盛りなので妹を預け二人でお茶しに行ったりして、スキンシップを取っている。(小2)
- ●お手伝いをさせて、家族の一員であることの自覚を促すようにしている。最近では、自分からやることを言い出してくれるようになった。(小3)
- ●年齢的に思春期に差しかかるころかなと思います。メンタルなことで生活に乱れが出ないように、常に会話を絶やさないように心がけています。(小6)
- ●中学生女子なのでダイエット志向と反抗期が関係して、親の思いどおりにはいきません。そんななか、「よく食べよく眠り無茶をしない」という形で話をしながら、子どもが健康を自分自身で考えられるようにしていきたいです。(中学生)
皆さまがお子さまをしっかり見つめ、お子さまに合うことを工夫して取り組んでいる様子が伝わってきました。「健康を維持する」というのは結果としてそうなっていることが多く、何かを試みてすぐに効果が表れるとは限りませんし、同じようなことをしているつもりでもうまくいかない場合もあります。常日頃のお子さまに対する目配りがいちばん大切で、ときには根気よく、ときには臨機応変に、お子さまと向かい合っていくことで成し遂げられるものなのでしょう。……アンケートを拝見しながら、そんなことを感じました。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 夢を語れない子どもが増加!? 子どもの夢をはぐくむ保護者のサポートとは?
- 子どもが納得する「家庭のルールの違い」の伝え方
- 出願準備は意外と大変!? 保護者が押さえたい注意点は?【大学入学共通テスト編】
- 今求められる「学習者目線の学び」とは?3人の教育関係者が語る《学び続けるために必要なこと》
- 恥ずかしがりやで授業中に手をあげるなど積極性がありません[教えて!親野先生]
- 【進路のプロが教える!新課程の共通テスト(2)】スピード&読解力がカギ!英語・国語・数学の特徴を徹底解説
- 8割以上の保護者が高校生の進路選択をサポート!? 子どもがうれしいと感じるサポートとは?【進路意識調査より】①
- 幼児期に始めたい健康教育【前編】健康教育の大切さを改めて知ろう
- 親野先生に聞いた!3学期にしておきたい目標設定と次年度への準備とは?













![恥ずかしがりやで授業中に手をあげるなど積極性がありません[教えて!親野先生]](http://benesse.jp/common/images/teacher/pct_mother.gif)










