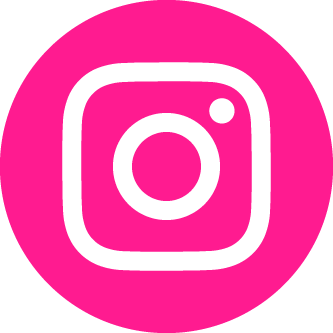不登校気味の子 新学期に向けた心の充電法【親野先生アドバイス】
- 育児・子育て
学校に行きたがらなくなっている子に対して、節目の春休みに家庭でできることは? 新学期を前向きに迎えるために知っておきたい子どもの気持ちや家庭での関わりについて、教育評論家の親野智可等先生にお聞きしました。

春休みは安心できる世界を満喫させる
学校に行きたくないと思っている子にとって、春休みは、気がかりや煩わしさ、プレッシャーから解放されてホッとできるとき。家庭でも、穏やかな雰囲気を大切にして、なるべく自由に過ごせるようにしてあげましょう。
親としては、次の学年は登校できるだろうか、心機一転、悩みごとが解消されるだろうかなど、次の学年に向けて気持ちが落ち着かないかもしれません。実際に、クラス替えや担任替えで子どもの気持ちが変わり、学校に行くようになることもありますが、それはその時になってみないとわからないこと。
「4月からは学校に行けるといいね」「いいクラスだといいね」などと親の気持ちで語りかけると、子どもは学校のことが頭から離れず、リラックスできません。春休みは子どもにとって、ようやく訪れた休息期間です。まずはその安心感を満喫させてあげましょう。
プラス思考の振り返りで絆を深める
年度の節目には、この先のことを考えるよりも、終えた1年を「よい1年だった」とポジティブに振り返るといいでしょう。無理に学校のことを持ち出さなくても、生活の中で楽しかったことや成長したことがあるはずです。
家族での外出、新しい趣味、快適な時間やわくわくした体験などを思い出すと、その時の気持ちや感覚も思い起こされます。続けられたこと、がんばったことがあれば、思い出しながらたくさんほめてあげると、そこに新たな喜びも生まれます。
作ったものや集めたものを並べたりして「すごいねえ」と話したり、家族で出かけた写真を見ながら「また行きたいね」と話したりするのもいいですね。学校に行かない、行きたくないというのは、子どもの中のひとつの側面でしかありません。もっと大切な時間があることも、会話をとおして感じられるのではないでしょうか。
楽しい時間で心の充電をする
ゆっくり過ごし、思い出を振り返るのに適した春休み。同時に、楽しく過ごせる時間を積極的につくることも大切です。子どもが行きたいと思う場所に出かけたり、好きなことに没頭したり、今を楽しく過ごすことで子どもの心のエネルギーが充電されていきます。
広い公園や自然の中でゆっくりできる機会をつくったり、見たいもの、したいことを体験しに親子で出かけたりするのもいいですね。広々とした場所で深呼吸すれば、保護者のかたもきっと気持ちよく過ごせると思いますよ。
そして、どんな時も大事なのは親がやらせたいことを優先しないこと。子ども自身がやりたいことや本当に楽しめることができれば、子どもは元気が出てきます。
子どもはひとりで遠くに出かけたり、欲しい道具や材料を買ったりすることができません。こうした相談なら、前向きに、丁寧に話ができます。どうしたいのか、したいことのために何が必要なのかを聞き、家庭で協力できることを考えましょう。
熱中する時間が気持ちを強くする
好きなことに熱中する時間は、心の充電になるだけでなく、多くの成長の機会も与えてくれます。好きなことなら少々思うようにできなくてもがんばれますし、工夫もします。すると粘り強さや、課題を見つけて工夫する力が育ちます。
また、何かに夢中になっていると、多幸感を生む脳内ホルモンのドーパミンがたくさん分泌され、意欲や集中力が高まります。達成感や、だんだん上達していく実感を得て、自信も付きます。こうした自分に対する肯定的な気持ちが、多少イヤなことがあってもがんばれるメンタルを育てていくのです。
これは学校に行きたくないのに行かなければいけないと苦しんだり、行けない自分はダメなんだと落ち込んだりするのとは真逆です。ネガティブな思考は意欲も活力も奪ってしまいますが、家庭での充実した時間は子どもの思考を前向きにして、いきいきとさせてくれます。
さらに、好きなことを応援してくれる保護者のかたへの感謝の気持ちや信頼感も生まれます。いつも味方でいてくれる家族の存在は、子どもにとって何よりも安心できる心の支えになるのです。どうか、リラックスして楽しい春休みを親子で過ごしてくださいね。
まとめ & 実践 TIPS
春休みは子どもにとって、プレッシャーから解放されてやっとひと息つける休息時間。新学年への期待や不安を口にするのは控えて、リラックスさせてあげましょう。同時に、楽しく過ごせる充実した自由時間をつくり、心のエネルギーチャージができるとよいですね。

- 育児・子育て