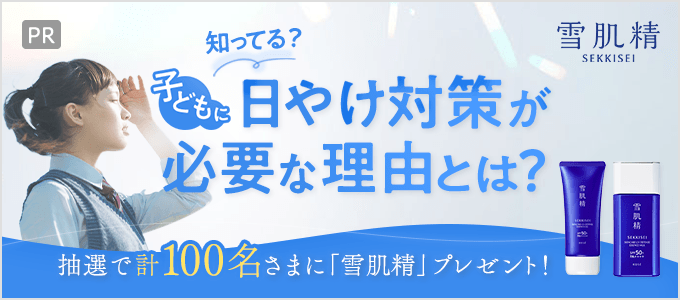9月からの受験生活 「できる子」のちょっとした違い[高校受験]
お気に入りに登録
■「できる子」のちょっとした違い
今回からは、9月以降の受験生活について、踏み込んだお話をしていきます。 去る2013年8月8日、大学入試センターのシンポジウム「入試研究から見た高大接続」をのぞいてきました。皆さまにはまだ関係ない、と思われるかもしれませんが、基調講演の1つに「高校1年次の勉強時間」というものがありました。大学入試センターの准教授のかたが中堅校と進学校の生徒の勉強時間を調べた結果と、その報告です。これは高校受験生にも当てはまるなと思いながら聴きましたので、簡単にまとめてみます。
去る2013年8月8日、大学入試センターのシンポジウム「入試研究から見た高大接続」をのぞいてきました。皆さまにはまだ関係ない、と思われるかもしれませんが、基調講演の1つに「高校1年次の勉強時間」というものがありました。大学入試センターの准教授のかたが中堅校と進学校の生徒の勉強時間を調べた結果と、その報告です。これは高校受験生にも当てはまるなと思いながら聴きましたので、簡単にまとめてみます。
・中堅校の生徒は「指定校推薦」での進学を希望する割合が高く、進学校の生徒は「一般受験」での進学を希望する割合が高い
・中堅校の生徒と進学校の生徒では、勉強時間そのものに差がある
・「指定校推薦」希望の生徒は、テスト期間中の勉強時間が多くなる
・「指定校推薦」希望以外でも、中堅校の生徒はテスト期間中の勉強時間が多くなるが、ふだんの勉強をコツコツやっていないため、学習の「基礎体力」が付かない傾向がある
・進学先希望が明確な生徒ほど、勉強時間が長い
・将来の仕事希望が明確な生徒ほど、勉強時間が長い
・進学校の生徒は、細切れ時間を活用することがうまい
・進学校の生徒ほど、部活・趣味と勉強の切り替えが上手
・中学時代にあまり勉強せずに、ある程度の高校に合格できたという成功体験がある生徒は、大学受験においても考えが甘い
当たり前といってしまえば当たり前のことばかりですが、この当たり前のことが重要なのです。
たとえば、「推薦入試」で高校へ行こうと思っている生徒は、内申点を上げようとしています。そのため、上記で示した「指定校推薦」希望の生徒のように、テスト期間の勉強が中心になりがちです。しかし、これでは「学習の『基礎体力』が付かない」のです。中学校の学習範囲をひと通り復習する、苦手な教科・単元を克服する……といった原点に帰った本来の受験勉強をきちんとするように持っていってください。
進学校の生徒の「細切れ時間を活用することがうまい」ことや、「部活・趣味と勉強の切り替えが上手」なども参考になります。部活を引退した生徒が陥りやすいケースは、せっかく自由になる時間が増えながら、なんとなくダラダラ過ごしてしまい、有効に使えずに終わってしまうことです。学校から帰ってから夕食までの時間、あるいは塾に出かけるまでの時間、夕食後からお風呂に入るまでの時間、朝出かけるまでのちょっとした時間……そうした半端に空いた時間にできることを、お子さまと一緒に考えてみてください。
「できる子」と「できない子」の差というのは、案外ちょっとしたところから生まれるのだということを知っていただきたいと思います。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 小学校英語・教科化3年目の授業やテストはどんな内容? 中学校に向けて保護者ができるサポートとは?
- 特集
- 【入試直前の過ごし方】「あれもやってない」「これもやってない」と心配に…最後の最後に大事なことは?
- 遠距離通学のメリット・デメリットは? [中学受験]
- 小中高生の保護者の約8割は「わが子に実際の場面で使える英語力を身につけさせたい」…ではどうしたらいい?
- 国語で、問題文の大切なところに線を引いたりするなどの、コツやテクニックがわからない[中学受験]
- 【中1】中学生の夏休みにオススメな学習計画の立て方
- 【体験談】「部活をやる意味って何?」大学生が語る部活から学べる4つのこと
- 次の教育の目標「ウェルビーイング」って? 入試に出るかも…














![9月からの受験生活 我が子の将来、大胆に発想[高校受験]](/_shared/img/ogp.png)