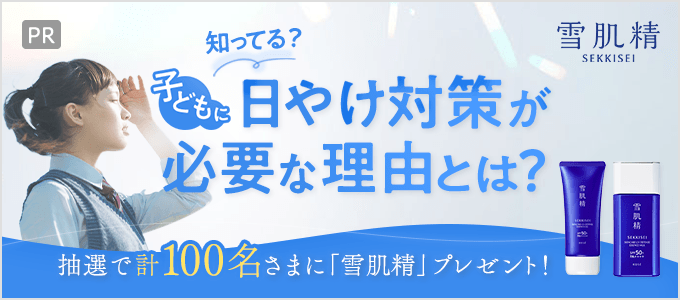高校受験内申対策 保護者による「知恵」がマイナスになることも
お気に入りに登録
高校受験において、入学試験とともに重要なウェイトを占めるのが中学校での「内申」だ。保護者としては、どうにかして子どもの内申をあげようと、いろいろな“策”を練るが、必ずしもそれは正しいことだとはいえないという。安田教育研究所の安田理氏はこう話す。
***
「コンサートに行ったら音楽の先生に、展覧会に行ったら美術の先生に、スポーツ観戦に行ったら保体の先生に『必ずそのことを報告するのよ』『授業では、わからなくてもいいから挙手するのよ』『なんでもいいから先生に質問に行くようにしなさい』などという保護者のかたがいますが、そんな『知恵』は、長い目で見ればお子さまの成長にはむしろマイナスです。
合格だけを考えると、保護者としては自分が打てる手はすべて打ちたくなります。その心情はわからないでもありませんが、長い人生を考えると、合格よりもっと大切なことがあります。子どもを育てるということは、一人前の社会人として責務をきちんと果たす人間にするということです。そうした観点から考えた時に、お子さまの人間性の成長にマイナスになるようなことはしないほういいと思うのです」
また、中には「先生が内申を恣意的に付けているのではないか」と不安を持っている保護者もいるかもしれない。そんな不安に対し、安田氏はこう説明する。
「学期ごとにお子さまが持ち帰る『通知表』をご覧になっていると思います。『学習の記録』の欄には、5段階で付けられる『評定』の欄と『観点別学習状況』の欄があります。この『観点別学習状況』には『関心・意欲・態度』『思考・判断・表現』『技能』『知識・理解』の4つの欄があり(教科によって少しずつ表記は異なっており、国語には5つの欄があります)、A・B・Cの3段階で評価が記入されます。『観点別学習状況』の評価が、オールAなら5とか、Aが2つか3つで残りがBなら4とか、オールBなら3とか、BとCが混じっていれば2とか、学校ごとに事前に決められているのです」
内申にはしっかりとした基準があり、それに従って点数が付けられているとのことだ。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 【声掛け】進研ゼミ教材に取り組めていないとき
- 定期試験、保護者が協力できること[内申対策、保護者ができること 第3回]
- 第3回 幼児の生活アンケート・国内調査 速報版[2005年]
- 逆上がりは「できなくていい」?運動能力低下のなかで
- 受験勉強、お父さまの見守り方とは[内申対策、保護者ができること 第4回]
- 2023年8月6日(日) 国語教育実践改革会議主催 第16回全国国語教育研究大会ご案内 「改めて『主体的・対話的で深い学び』を問う~成果と課題、そして展望」
- 国立大合格者に聞いた夏休みの学習時間、最も多かったのは「1日10時間」
- 「内申」に対して否定的な発言は慎しむ[内申対策、保護者ができること 第2回]
- 顔から手足が生えた絵(頭足人間)とは?なぜ体がないの?保護者はどんな声をかければいい?













![定期試験、保護者が協力できること[内申対策、保護者ができること 第3回]](/_shared/img/ogp.png)