顔から手足が生えた絵(頭足人間)とは?なぜ体がないの?保護者はどんな声をかければいい?
- 育児・子育て

お子さまが描いた絵を見て、顔から直接手足が生えていることに驚いたり、子どもらしい表現にほほえましく感じたりしたことはありませんか?
「頭足人間」と呼ばれるこの絵は、世界中の子どもが同じように描く特徴的なものです。なぜ頭足人間を描くのか、体はどう描けるようになっていくのか、子どもの発達段階も踏まえて、和洋女子大学の佐藤有香教授にお話を伺いました。
頭足人間を描く理由

頭足人間とは、顔から直接手足が生えたような人間の絵のことです。2~4歳ごろの幼児によく見られるもので、文化に関係なく世界中の子どもが共通して描く表現です。
子どもは胴体を認識しにくい
子どもが頭足人間を描く理由には、胴体の認識が子どもには難しいことが関係していると考えられています。
幼児が重点的に認識しているものは「顔」です。そのため、大人が「顔」と思っているものを、子どもは「体も含めたその人全部」として認識している可能性が高いといわれています。
では、胴体はないのに、手足を描くのはなぜなのでしょうか。それは、腕や足は日常生活でよく動かすため認識しやすいためです。つまり、頭足人間を描くことは、子どもが 「人間には手足がある」 ということを理解し始めた証拠といえるでしょう。
頭足人間からどう体を描けるようになっていく?
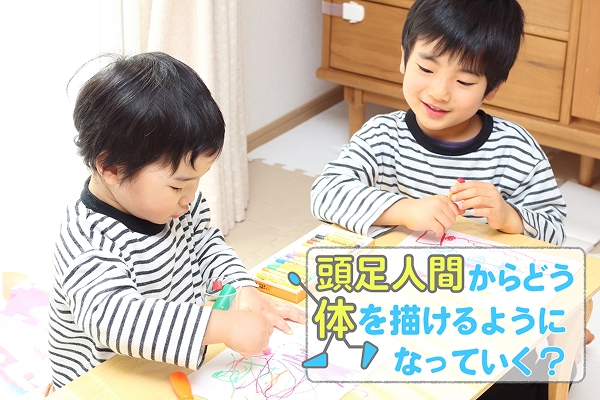
胴体が描かれるようになる時期には個人差がありますが、一般的に年長~小学校入学前にかけて徐々に描かれるようになるといわれています。胴体が描かれるようになるまでのプロセスを、年齢ごとの発達段階と合わせて見てみましょう。
子どもの絵の発達段階のめやす
・9か月ごろ:お座りが安定することに伴い、クレヨンを握り、腕を動かして点を描く。
・1歳ごろ:ひじを使って手の動きをコントロールできるようになる。それに伴い、殴り書きで横や縦の線を描くようになる。
・2歳前後:手首のコントロールの発達と、目と手の協応(異なる器官を同時に適切に動かすこと)が進むことで、円を描けるようになる。
・3歳ごろ:丸の中に目や口を描くようになる。直線で手足を描くことも見られるように。手足の有無は子どもによって異なり、どちらか一方だけの場合もある。
・4~6歳ごろ:髪の毛や鼻といった細かい部分を描き始める。その後、胴体を描くようになる。ただし、最初の胴体は寸胴(ずんどう)で、肩や首がないが、徐々に肩や首が加わる。服の概念も理解し、ドレスやネックレスなどの装飾を描く子も増える。
頭足人間から胴体が描かれるより先に、手足のバランスが取れるようになるのが一般的です。胴体が現れたな、首ができたな……とお子さまの成長を絵をとおして見守っていくのも楽しいですね。
子どもが描くのが楽しくなる! 保護者のかたができる声かけの工夫

子どもが頭足人間を描くのは、世界中の多くの子どもが経験するごく自然な発達過程の一部です。この時期の絵は、今しか見られない成長の記録。保護者のかたも楽しんで受け止められるといいですね。
大切なのは子どもの「描きたい」という気持ちに寄り添うこと。子どもは子どもなりの思いを持って「表現したい」と思っています。「こう描いたら?」「体はどこかな?」といった先を急ぐようなアドバイスではなく、子どもが描いたことに喜びを感じられ、「もっと描きたい」と思えるようにしたいですね。
評価ではなく描こうと思った思いに寄り添う声かけを
では、お子さまが描くことに楽しさや喜びを感じられるようにするために、保護者はどのような声をかけてあげればいいのでしょうか。いくつか声かけ例をご紹介します。
・子どもが表現したものへの気付きを伝える
◦「これ、ママかな」
◦「これは手を描いてくれたんだね。うれしいな」
・子どものイメージしたものを尋ね、深掘りする
◦「これは何かな?」と描いたものについて尋ねる。大人からはわからなくても、意外と細かな設定があったりもするもの。表現したかったものを理解できるといいですね。
◦目の前のものを観察して描くだけでなく、家族で出かけたことを思い出して絵に描いていることも。お子さまの答えに対して、「◯◯なところを描いてくれたんだね」と補ってあげましょう。
・前と比べてすてきだと思う変化を伝える
◦「腕だけじゃなくて、足が生えてきたね」
4歳くらいになると、子どもは他の子の絵と比較するようにもなるものです。それに伴い、「私はうまく描けない」と感じ、苦手意識が芽生えやすい時期でもあります。だからこそ、保護者は「上手・下手」で評価しないことが大切です。もっと表現したい、表現するのは楽しいと思えるようにしましょう。そのためには、大人が頭足人間を楽しむ気持ちを持てるといいですね。
まとめ & 実践 TIPS

頭足人間の時期は期間限定の貴重なもの。大人から見ると「足りないパーツがある絵」かもしれませんが、子どもは豊かな想像力で描いています。たくさん気付いて、質問して、表現する楽しさを感じられるようにしたいですね。
- 育児・子育て














