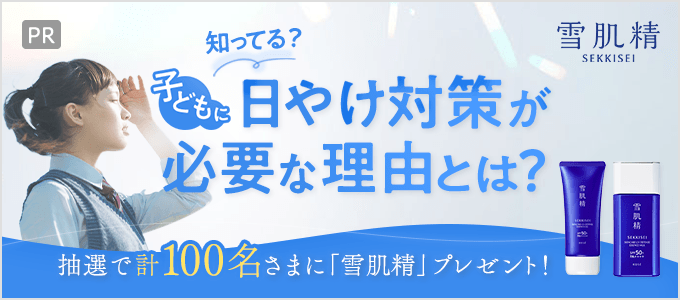保護者が子どもの努力を認めることこそが高校入学後の「原動力」[受験、こんな時はどうする? 第4回]
お気に入りに登録
思い描いていた学校とは違う場合
最近の高校受験は父親の参加も増えて、一家の総力戦、ビッグイベントになっています。それだけに、家中でがんばったのだから、お金もこれだけ使ったのだから……と、期待も大きくなります。
ですが、第一志望校にスンナリ進めないケースもたくさんあります。受験勉強を始めた当初に思い描いていた学校とはレベル的にも違う学校に入学することになることもあるかもしれません。
保護者のかたにすれば、いろんなことを犠牲にしてやってきていればいるほどショックは大きく、中には、知人と顔を合わせるのが嫌で外出しない、そうしたかたも出てきます。
「近所の人に興味本位に子どもの入学先を聞かれるのがいやだ」「校名を言いたくない」「我が子を入れたかった学校の制服を見たくない」……そうした心理状態に陥ってしまうのです。
ですが、保護者のかたがいつまでもこうした思いを引きずっていると、「親をこんなにも悲しませてしまった」と、自分が不合格だったこと以上にお子さまを苦しませることになります。入学する学校にも誇りを持てず、それは入学後の友達関係、学校生活にも尾を引き、勉強に身が入らないことにもつながります。
今回の結果は、あくまで高校受験の結果でしかありません。人生の結果ではないのです。
進学先が希望していたところではなくても、お子さまがここまで努力してきたこと自体をほめてあげてください。保護者のかたがお子さまの努力を認めることこそが高校入学後のお子さまの「原動力」になるからです。
入試が終わった今、頭の中から偏差値は消してください。毎週のように見てきた偏差値表は、今すぐシュレッダーにかけましょう。
「学歴」「勤務先」で人を見ない
今回の結果から、ほんのちょっとの差(わずか2、3問の違いかもしれません)で「明」と「暗」がこれほど違うのかという思いを持たれたのではないでしょうか。
これからの生活で、今回のこの実感をぜひ大切にしてください。
人はどうしても、学歴、勤務先……といったわかりやすいもので人を判断してしまいます。ですがそれらは、今回のように、紙一重のことで分かれるものなのです。そうであるならば、そうしたものでは人を過大評価も、過小評価もしない--今回の経験からそうした姿勢を持っていただきたいと思います。
お子さまが進学先に劣等感を持たなくてすむのは、保護者のかたが日頃からこうした見方をしているかどうかにかかってきます。
私はしばしばいろいろな高校の先生とお話しする機会があります。そうした時よく話題に出ることに、最近入学してくる生徒の自尊感情の低さがあります。受験生活の中で、勉強の成績だけに価値を置かれ、テストの点が悪かった、塾のクラスが下がった……そうしたことを言われ続けてきたことの蓄積が自尊感情の低さにつながっています。
これまでは、なんとしても「合格」させたいという思いから、お子さまの弱点にばかり目がいっていたと思います。ですがこれからはお子さまのいいところばかりを探し、それを評価してあげてください。
結果はどうであれ、この受験生活を通じてお子さまにはきっと受験を始める前にはなかった力がついているはずです。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 子どもが「学校行きたくない」と言ったら、どうする?【第2回】~保護者に心掛けてほしいこと~
- 子どもの「幸せ」につながる読書って?
- こんな保護者にならないでください 入学までをどう過ごす?[高校受験]
- 親野先生に聞いた!子どもが本を読むようになるヒントとは
- 正確に話せなきゃダメ?小学校英語の「パフォーマンステスト」を成功させるカギとは
- 過ぎたことは振り返らず、次に向けて前を向く 受験、こんな時はどうする?[高校受験]
- 【国語が苦手】好きになるために家庭でできることは?
- 【第1回 最先端の教育実践者が語る座談会】小中学生としての9年間、大人も子どもも「〇〇しないといけない」からの脱却を
- 学校では今 【第6回】「1年生になったら」~小学校入学時に保護者が心がけたい「3つ」のこと-小泉和義-














![こんな保護者にならないでください 入学までをどう過ごす?[高校受験]](/_shared/img/ogp.png)
![過ぎたことは振り返らず、次に向けて前を向く 受験、こんな時はどうする?[高校受験]](/img_o/kj/juken/201202/20120209-1.jpg)