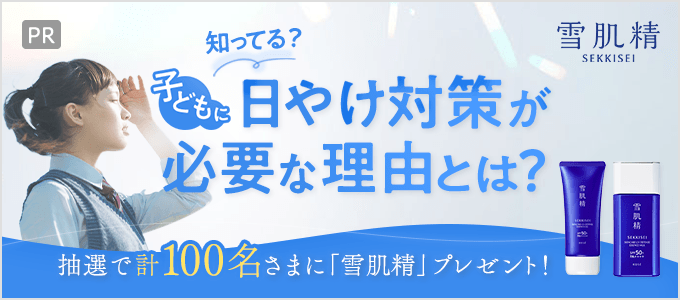数字以上に、中身に関心を 受験校をどう決めるか[高校受験]
お気に入りに登録
■情報化・ランク付けの影響
ある私学の校長がこのようなことを言っていました。
「高校受験の世界がどんどん情報化され、その情報も単純化が進んでいる。そのような流れに沿って、学校側も耳目に届きやすい言葉やスローガンで自らをくくってしまう。そうしたことで、学校教育本来の持つ役割が捨象されてしまっている。受験はヒートアップしているが、学校側の内実は、むしろどんどんやせ細っているのではないか」。
週刊誌・ビジネス誌・子育て情報誌が頻繁に大学合格者ランキングを扱うことで、いつの間にか「大学に合格させる力=私立高校の教育力」ととらえる保護者が多くなっています。実際に、前年春の大学合格実績が翌年の受験者数にすぐ跳ね返る傾向が、このところ年々顕著になってきました。受験者数に響くとなれば、学校側も難関大学に合格させることに力を入れざるをえません。
実際に、保護者向けの説明会では「国公立・早慶上智に50%合格させます」「国公立・最難関私立大学に現役合格を目指します」といった勇ましいマニフェストを発表する学校が多くなってきました。
■公立高校も学校が競争させられている
私立高校だけではありません。今、公立高校の世界でも、大学合格実績を上げることに大変力を入れていて、都府県の教育委員会自体がその都府県の実績を上げるために特定の学校を「進学指導重点校」(東京都の名称)、「進学指導特色校」(大阪府の名称)といったものに指定しています。このような動きは、東京都や大阪府に限りません。埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、広島県、大分県……など、首都圏を中心に年々広がってきています。
難関大学への合格実績によって「指定」が外されたりもするので、いや応なく高校自体が競争させられるようになっています。
このように、行政も大学合格実績にこだわっているのですから、保護者の意識もますます「高校=大学への通過点」となっていくという「循環回路」に入っています。
いい大学に進ませること自体は意味のあることですし、それは私も否定しません。が、勉強だけの生活は、その後の本人の人生を考えるとどうでしょうか。
■数字以上に、中身に関心を持って
高校は、「通過点」としてではなく、前回お話ししたように、在学する3年間そのものに大きな意味があるのです。そのような学校生活の部分にも着目していただきたいと思います。
それは、難関大学合格者数・偏差値という数字からはわかりません。保護者のかたご自身が、その学校の教育の中身を深く知ろうとすることでしか可能になりません。数字以上に、学校の中身に関心を持っていただきたい……切にそう思っています。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 日本大学 文理学部 国文学科(1) 『あまちゃん』の「方言コスプレ」から社会が見える[大学研究室訪問 学びの先にあるもの 第14回]
- 子どもが言うことを聞かない!?そのルールを作ったのは親です。「モデルなき時代」に出来ることとは
- 私立高校の受験校をどう決めるか 志望の度合い、内申点で、受験パターンを決める[高校受験]
- 東京学芸大学 教育学部 初等・中等教育教員養成課程 社会科教室 (2) 好きなことを学んで高めた専門性が社会に出たときの武器になる[大学研究室訪問 学びの先にあるもの 第2回]
- 言うことを聞かない子どもが2週間で変わる!?親がとるべき戦略とは?
- 私立高校の受験校をどう決めるか 公立高校が第一志望の場合には[高校受験]
- 立正大学 文学部 社会学科(1) 「地域安全マップづくり」で子どもも学生も育つ[大学研究室訪問 学びの先にあるもの 第13回]
- 難易度が下がるという入試予想と仕上げの学習方法[中学受験]
- 私立高校の受験校をどう決めるか 私立高校入試のバリエーション[高校受験]













![私立高校の受験校をどう決めるか 志望の度合い、内申点で、受験パターンを決める[高校受験]](/_shared/img/ogp.png)