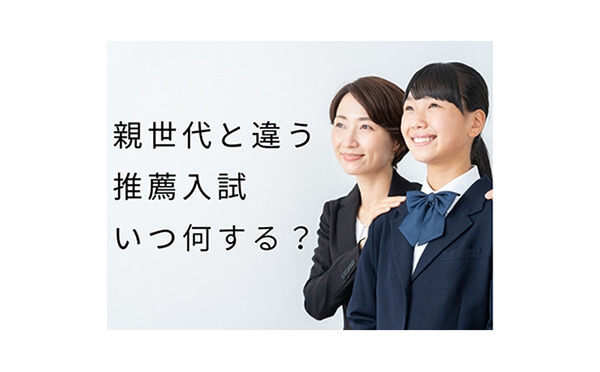志望校と選定時期 [中学受験]
お気に入りに登録
志望校は、受験勉強の開始時または実施中に目標として、また、入試が迫ってきた時点で合格を勝ち取るために設定する。目標としてきた志望校が実際に受験する志望校となる場合のほうが多いかもしれないが、生徒の学力では目標としてきた志望校に合格することが易しすぎるか難しい場合は、途中で志望校を変更することになる。
目標として志望校を設定するのは、いつが多いか考えてみよう。志望校がなければ、目標がない受験となり、子どもも親も前向きに受験勉強に取り組みにくい。本来は、目標とする志望校があって塾を選ぶべきだ。塾の合格実績を見るとわかるが、塾によって指導の仕方が異なるためか、合格している学校に特色がある。志望校を考えずに塾を選ぶと、志望校を決めたあとで転塾することにもなりかねない。
しかし、現実的には塾に入ってから志望校を決めるケースも多いようで、その場合は、塾のカリキュラムのスタート時が2~3月だとすれば、塾に入ってから目標としての志望校を決める時期は4月前後になるようだ。その理由の一つとしては、受験勉強に限らず、スタート時に目標を設定するのは一般的だということが挙げられる。また、塾に通っている場合は、6年生の4月になると模試があるので、具体的な志望校を記入しなければならなくなる。その時点で志望校を選定することもあるだろう。
4年生から塾に入って中学受験をスタートさせる受験生が多いので、4年生の4月に早々と目標となる志望校を定めるケースもあると思うが、受験生の保護者にアンケートを行うと5年生の9~10月に志望校を決めたがケースが最も多い。5年生の秋になれば、学力も安定してくるので、現実的な志望校を考えることができ、9~10月は学校説明会が集中する時期で、最終的にはこの時期に目標とする志望校を確定することができる。
さらに学年が高くなって、合否判定が重視されるようになれば、入りたい目標の志望校ではなく、入れる可能性がある志望校を設定する必要がある。6年生の夏休みが天王山となり、2学期以降の学力の伸び如何で決まる。その時点で、志望校の合格判定模擬試験の結果が思わしくなければ志望校の変更も考えるべきだ。学力とかけ離れた学校を志望校にすることは、子どもに不安感を持たせることとなり、学習意欲を維持していくことが難しい。模試を受験するたびに、合格判定で否定的な判定を受けることは、子どものやる気を低下させることになる。
しかし、大幅に志望校ランクを落とすと、子どものプライドを傷つけ、やる気をそぐことにもなる。高すぎる目標を掲げることは、大きなリスクが伴う。初めからランクの高過ぎる志望校を設定するよりも、子どもの学力が伸びれば手が届く偏差値の学校を目標として設定し、学力の向上とともに志望校ランクを上げるとよい。志望校ランクを上げることで子どもがチャレンジしようという気持ちになるようにしてあげることがポイントだ。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 志望大決定が早いほど合格率アップ? 知っておきたい進路目標のポイント3つ
- 親と子、両者のために! 早寝早起きのススメ【後編】規則正しい生活のポイント
- 社会の資料の読み取りが苦手な小学生・・・問題演習だけでは克服できないので注意!
- 高校生が第1志望大を決めた時期はいつくらい?保護者はどうサポートすればいい?
- 子どもの自己肯定感がグンと高まる声かけと接し方のちょっとしたコツ【体験談あり】
- 計算練習だけでよい?今の子どもたちが算数・数学を楽しく取り組めるようになるために育みたい力とは?
- 進路が決まらない!そんな時に、高校生と保護者がやるべきこと【体験談あり】
- 健やかな成長に欠かせない早寝早起きの生活習慣がよい理由
- 【中学受験】結果は公立中学を選択することに…なかなか気持ちが切り替えられない保護者のかたへ