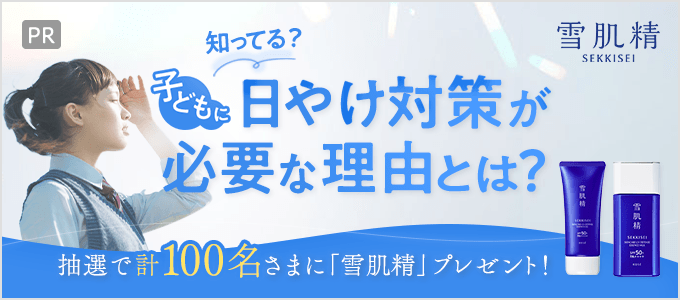「模試」は志望校決定の有力な材料[模擬試験の上手な活用の仕方 第1回]
お気に入りに登録
秋からは本格的な模擬試験のシーズンが始まります。模擬試験はこれから志望校を決めていく時の大切な材料です。お子さまにどう取り組ませ、また保護者はその結果にどう向き合えばよいのでしょうか。
![「模試」は志望校決定の有力な材料[模擬試験の上手な活用の仕方 第1回]](/img_o/kj/juken/201008/20100805-1.jpg)
(1)「模試」は志望校決定の大事な材料
模試への意識の差は大きい
受験生の間でも、模擬試験に対する意識に大きな差があります。「模試は本番に慣れるための単なる練習の場」という意識の受験生から、「私立高校の推薦基準に模試での偏差値も使われるから、なんとしてもいい成績を取ってやる」という情報通の受験生まで、意識の差にはものすごく大きいものがあります。
「私立高校の推薦基準に模試の偏差値も使われる」というのは、あくまで一部の私立高校と塾とが相談するケースであって、中学校と私立高校の正式な入試相談で使われるわけではありません。ですから、神経質になる必要はないのですが、受験生の中にはここまで模試に真剣に取り組む生徒がいるということは知っておいたほうがいいでしょう。
ただ志望校を決める時には、絶対評価になった調査書の成績だけでは判断できないことも事実です。模試を受けて示された「学校ごとの合格の可能性」「偏差値」というものが志望校を決めるうえで最も有力な材料であることは確かです。ですから、模試で好成績を挙げておくことが、その後の志望校選択の幅を広げることにつながります。このことを、ぜひお子さまに話してください。
3回くらいは受けておきたい
15歳くらいだと、模試の成績はなかなか安定しません。よほど優秀な子どもでない限りは、回ごとに問題が違い、お子さまの得意・不得意とマッチしたり、ミスマッチしたり、模試当日頭がさえていたり、集中力がなかったり……そんなことで力が100%発揮できることもあれば、60%しか出せないこともあります。
ですから先のような模試の偏差値を求める私立高校は、1回の偏差値だけでなく、2回なり3回の偏差値を求めます。また子どもの学力が上向いているのか、下降線をたどっているのかを知るためにも、9月から12月の間に最低3回は受けるようにしたいものです。模試が公立高校向け、私立高校向けと分かれている場合には、両方を受けておくとよいでしょう。
いつ、どの模試を受けるか。また志望校が決まっていて、そこが模試会場になっているなら、本番の慣れのためにもぜひその会場で受けたいものです。そうしたことまでをにらみながら、模試のスケジュールを組んでください。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 模試の結果が思わしくなかった場合[模擬試験の上手な活用の仕方 第4回]
- 『これからの幼児教育』2024度 秋号 【特集】全国調査から見えてくる 保育の課題と未来へのヒント|これからの幼児教育
- 中高生の保護者のかた必見!テストの復習をより効果的にする4つのポイント!
- 偏差値表で高校入試事情を把握する[模擬試験の上手な活用の仕方 第3回]
- 幼児期の家庭教育国際調査【2018年】
- 定期テスト対策 高校入試に影響する中3の内申点UP術【数学編】
- 注目すべきは成績よりも答案[模擬試験の上手な活用の仕方 第2回]
- 第2回 大学生の学習・生活実態調査報告書 [2012年]
- 教えて! 野田クリスタルさん「なぜ独学プログラミングでゲームが作れるようになったの?」














![模試の結果が思わしくなかった場合[模擬試験の上手な活用の仕方 第4回]](/img_o/kj/juken/201008/20100826-1.jpg)
![偏差値表で高校入試事情を把握する[模擬試験の上手な活用の仕方 第3回]](/img_o/kj/juken/201008/20100819-2.jpg)
![注目すべきは成績よりも答案[模擬試験の上手な活用の仕方 第2回]](/img_o/kj/juken/201008/20100812-1.jpg)