「うちの子、友達がいないみたい」と気になったら。カギは「肯定的に感じられる居場所」づくり
- 育児・子育て

小学校高学年ごろからは、子どもが友達やグループの仲間との関わりを通じて、大きく成長する大切な時期です。我が子の友達関係を温かく見守りたいと思う一方で、「トラブルになっていないかな?」「うちの子、友達がいないみたい……」などの悩みを持つ保護者のかたもいらっしゃるかもしれません。
今回は、友達・仲間との関係がお子さまに与える影響や、保護者のかたが心掛けたい関わり方について、東京都立大学 人文社会学部教授の酒井厚先生監修のもと、ご紹介します。
仲間との関わりが子どもの成長につながる理由

子どもが成長する過程で、仲間との関わりは、性格や社会的スキルの形成に、少なからず影響を与えることがわかっています。
特に小学校高学年ごろになると、親よりも仲間と過ごす時間が増え、学校や習い事、地域活動などを通じて、仲間との関係が深まります。
「クラスの仲良し女子グループ」や「サッカークラブの仲間」といった、自分がいつも一緒にいる仲間グループを通じて、「自分がどのような存在か」を考え始め、「仲間といる時の自己認識(社会的アイデンティティー)」を形成していくのです。
「社会的アイデンティティー」が子どもに与える影響とは?
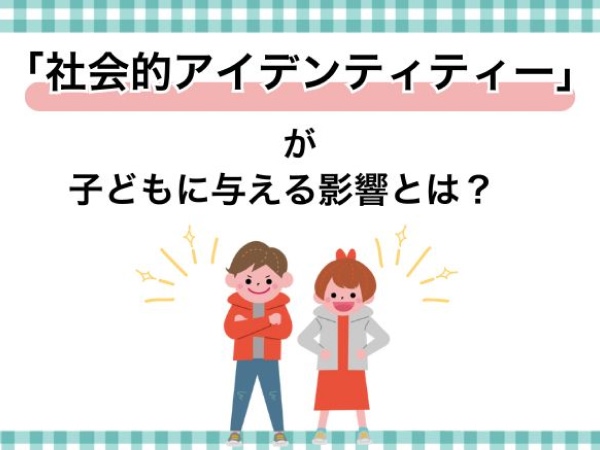
所属している仲間との関わりの中で形成される「社会的アイデンティティー」は、成長を通じて「自分らしさ」を表す個としてのアイデンティティーへと発展していきます。また、それが子どもの自己肯定感につながることも考えられます。
たとえば、自分がこの仲間グループの中でどんな存在かを意識してふるまうようになれば、それが個性の一つになっていき、周囲の仲間とお互いの特徴を認め合うことを通じて、他者を理解したり自分に自信を持ったりすることにつながっていきます。しかし、仲間グループでの関係にネガティブな要素があると、こうした自分を理解し他者とうまく関わることを学ぶ機会は失われてしまう恐れがあります。
また、良好な仲間関係には、子どもが安心して過ごせる「自分を肯定的に感じられる居場所」があることが大切です。
子どもの仲間関係で保護者ができるサポートは?

小学校高学年ごろになると、保護者のかたがお子さまのすべての行動を把握することは難しくなるでしょう。それでも、保護者のかたは、見守りながら関わることが大切です。
子どもの生活状況を把握する
まずは、お子さまが日々どんな生活を送っているのかを、きちんと知っておくことが大切です。たとえば、普段からよく遊ぶ友達の名前や遊ぶ場所、何をしているのかといった基本的なことを把握しておくと、仲間とのトラブルにも対応しやすくなります。
また、遊びに行く前に、行き先や一緒にいる友達を保護者のかたに伝える習慣を、小さいうちから身に付けておくと安心です。お子さまの友達の保護者のかたと交流を持つことができれば、情報共有がしやすくさらに安心できるでしょう。
過干渉を避ける
お子さまを思うあまり、すべての行動を管理しようとすると、反発心を生む可能性があります。「どこで誰と何をしていたの?」のように根掘り葉掘り聞き出すのではなく、「今日はどうだった?」などと、間接的にさり気なくその日の様子を聞くようにするとよいでしょう。また、お子さまの話には興味を持って聞いてあげてください。
友達との関わりをサポートする
お子さまが友達関係で困っている場合は、遊べる環境や習い事などを通じて、新しい友達との出会いを提供するのもおすすめです。保護者のかた同士が仲良くなることで、お子さまたちも自然に関係を築きやすくなります。
「友達はいらない」と言う子どもにはどうしたらいい?
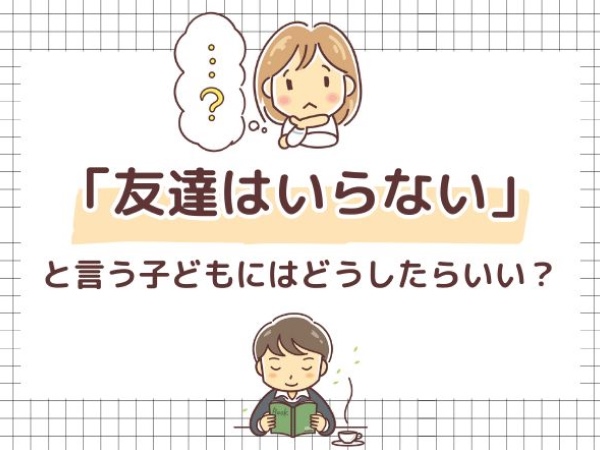
なかには、「友達がいなくても平気」と考えるお子さまもいるでしょう。その場合の対応ポイントを3つご紹介します。
気持ちを尊重する
「友達がいないのはダメ」や「友達は絶対必要」という考えを押し付けず、お子さまの気持ちを受け入れてあげましょう。一人でも楽しめているのであれば、それを肯定してあげることが大切です。
ただし、「友達がいることで楽しいこともたくさんあるよ」という、ポジティブなメッセージはぜひ伝えてください。そうすることで、気の合う仲間と出会えた時に、自然と「仲間に入りたいな」と思えるかもしれません。
寄り添いときっかけづくり
一人でいることを好むお子さまでも、寂しそうな様子が見られることもあります。そんな時は、友達の代わりに保護者のかたやきょうだいと一緒に遊び、楽しい時間を共有するとお子さまの気持ちが軽くなるかもしれません。
また、趣味や興味を通じて、お子さま自ら「友達をつくりたい」と思うきっかけをつくってあげるのもよい方法です。
焦らなくてOK
保護者のかたが焦ってしまうと、その焦りがお子さまに伝わりプレッシャーになることがあります。無理に友達をつくらせる必要はありませんし、「友達はいらない」という気持ちが、一生続くとは限りません。
「友達っていいものだよ」と、友達のよさを伝えながら、いずれよい出会いが訪れると信じ、温かく見守りましょう。
ネット社会での仲間関係は?

近年では、SNSなどを通じたネット上の仲間関係が増えています。危険視されがちなオンライン上のコミュニケーションですが、共通の趣味を持つつながりは、子どもの成長によい影響を与えることもあります。
必ずネットリテラシーの教育を行ってから
ネットでは情報が断片的に伝わりやすく、誤解やトラブルにつながることも多くあります。お子さまが安全にインターネットを活用できるよう、ネットリテラシー教育をしっかり行いましょう。
特に、「個人情報は言わない」「悪意のある書き込みをしない」「困ったことがあったらすぐに相談する」などの基本ルールは、お子さまにきちんと伝えておきたいですね。
顔を合わせないからこその利点も
小学校高学年ごろになると、自分を知っている人に、直接言いづらい悩みが出てくるかもしれません。対面で相談できないことでも、顔を合わせないですむオンラインでなら打ち明けられる場合もあります。
誰かに聞いてもらうだけで、心が軽くなることもきっとあるでしょう。お子さまが誰と関わっているかを把握しながら、オンラインでつながることの利点を認めつつ、現実での関係も大切にするよう促すのがおすすめです。
子どもが友達・グループの仲間関係で悩んでいそう……そんな時はどうする?

お子さまの悩みに気付くことは簡単ではありませんが、「イライラしている」「興味を持っていたものに取り組めなくなった」など、小さなサインが出ていることもあります。もしかすると、友達や仲間関係に悩んでいるのかもしれません。
そんな時は、まずお子さまに声をかけてみましょう。「〇〇さんとはどうなっているの?」といった直接的で子どもが嫌がるような聞き方は避け、「最近どう?」「ちょっと元気ない?」などと聞いてみるのがおすすめです。
それでもお子さまが話しづらそうな時は、「言いたくなったら話してね」「私はいつも味方だからね」と、頼れる存在であることを伝えてみてください。
また、日頃から「何かあったら相談してね」「いつでも話を聞くからね」と伝えておくとよいでしょう。最終的に、お子さまが困った時に「相談しよう」と思える関係を築くことが大切です。
まとめ & 実践 TIPS

お子さまが友達・グループの仲間との関わりを通じて成長する時期、保護者のかたは見守りつつサポートを提供することが求められます。「友達はいらない」と考えるお子さまには、気持ちを尊重しながら、よさを伝えられるといいですね。温かく寄り添いながら、お子さまが安心して友達・仲間と関係を築けるようサポートしていきましょう。
編集協力/海田幹子、Cue`s inc.
- 育児・子育て















