わざと嫌がること、悪いことをして保護者を困らせる子どもの心理とは?「試し行動」について知ろう
- 育児・子育て
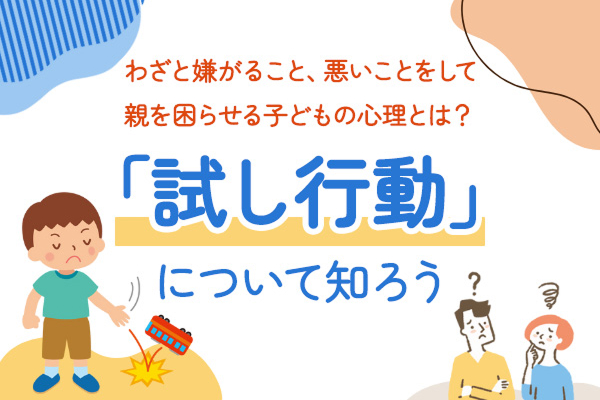
わざと食べ物をこぼしたり、スプーンを投げたり、きょうだいをたたいたり……「もしかして、悪いことをしてみせている?」と感じたら、それは「試し行動」かもしれません。
試し行動が続くと、「どうしてそんなことばかりするの?」「愛情不足なの?」と不安になる保護者のかたもいるでしょう。
そこで今回は、発達心理学の専門家である川村学園女子大学の菅井洋子先生に、「試し行動」をする子どもの心理やその対処法ついてお話を伺いました。
試し行動とは?

試し行動とはどんな行動?
試し行動とは、相手の顔色をうかがいながら、注意を引こうとする行動のことです。
たとえば、相手が自分を見ているのを確認したうえで、
- 食べ物やスプーンを落とす
- 物を投げる
- きょうだいをたたく
といった行動が当てはまります。
相手の注意を引きたいための行動なので、食べ物を落としたり、物を投げたりする行動がよくないことは理解しています。保護者のかたを困らせるとわかっているけれど、それでも「こっちを見てほしい」と強く思う時にしてしまうのが、試し行動なのです。
試し行動が見られるのは何歳ごろ?
試し行動が見られる年齢には個人差があり、保護者のかたのとらえ方によっても違うため、一概に「〇歳から見られる行動」とはいえません。
ただし、試し行動をするためには、そもそも適切な行動や道具の正しい使い方などを理解している必要があります。そのため、試し行動が見られるのは、さまざまな行動ができたりものの使い方がわかったりする1歳半~2歳以降になるでしょう。そして、試し行動は、子どもに限らず大人になっても見られる場合があります。
「どうしてするの……?」試し行動をする子どもの心理とは?

試し行動をする子どもの心理とは?
子どもの試し行動には、相手との関係の中で「安心感を得たい」や「愛着を形成していきたい」という思いが込められています。保護者のかたを困らせてしまうような行動かもしれませんが、「私のことをもっと見て」「どんな私でも受け止めて」という、子どもからのメッセージなのです。
これを聞くと「試し行動をする我が子は愛情不足なのかしら……」と不安に思う保護者のかたもいるかもしれません。しかし、「今一緒にごはんを食べたいな」や「今自分を見てほしいな」のように、急に保護者のかたに注目してもらったり、愛情が欲しくなる時があります。
試し行動があるからといって、愛情不足に直結するわけではないので安心してくださいね。
子どもが試し行動をしやすい時はどんな時?
愛情不足ではなくても、子どもが自身が求めている相手と満足な時間が持てていないと感じた時には、試し行動をする可能性は高まります。たとえば、きょうだいが多かったり、保護者のかたが忙しかったりして、なかなか自分に注意が向かない状況では、試し行動が起こりやすいかもしれません。
試し行動を受けとめてもらい安心感が得られると、子どもの自己肯定感や感情のコントロールといった非認知能力が育っていきます。「試し行動を受け止めてもらえた」という経験を積み重ねていくことは、子どもの人格形成にとって大切なことといえるでしょう。
試し行動は愛着形成の一つのチャンスととらえ、できる限りお子さまの気持ちを受け止められるといいですね。
試し行動はどう対応したらいい?

気持ちを受け止め、共感する言葉かけを
試し行動には、自分が求める相手と「一緒にいたい」や「自分を見てほしい」という思いが込められているので、まずは子どもの気持ちを受け止め、共感する言葉かけやスキンシップを行うことが大切です。
一方で、試し行動をした子どもに対して、無視をしたり子ども自身を否定したりすることは、好ましい対応ではありません。また、試し行動そのものが危険やけがを伴うものであれば、気持ちを受け止めたうえで行動をやめるようにその理由を説明する必要があるでしょう。
また、普段から
- 子どもと関わる時間をできるだけ持つ
- 子どもの名前を呼ぶ
- 「できたね」「すごいね」など共感する声をかける
- そばに行けない時は、目と目でやり取りをする
などの行動で「あなたに注意を向けているよ」と示すことも大切です。
試し行動の具体的な対応策
(1)ご飯の最中に、保護者のかたを見ながらスプーンを投げた場合
まずはスプーンを投げた理由を読み取る必要があります。「一人でご飯を食べるのが寂しい」「今日はご飯を食べさせてほしい」など、何かしら試し行動の理由があるはずです。「スプーンおちちゃったね」「一緒に食べよう!」のように優しく声をかけてあげましょう。
第一声に「スプーンを投げちゃだめでしょ!」と言いたくなる時もあるかもしれませんが、お子さまの気持ちを受け止めたうえで、「スプーンがないと食べられないね」と事実を伝え、行動を抑えるだけではなく子どものメッセージを考えながら、安心できるように伝えることが大切です。
(2)保護者のかたを見ながらきょうだいをたたいた場合
保護者のかたの顔色を見ながら、きょうだいをたたく姿を見せていると感じた場合、「お姉ちゃん(お兄ちゃん)なんだからちゃんとしなさい!」「たたいちゃだめでしょ!」のように言うのではなく、まずそのような行動をとおして子どもが伝えたいメッセージは何かを考えながら、子どもに「どうしたの?」と声をかけてみるといいでしょう。
少し立ち止まって、お子さまとの関係性を振り返ることも大切です。ただ、保護者のかたも自分のことを客観視することは難しいため、他のご家族のかたに聞いてみたり、話しあってみたりすると、気付くことがあるかもしれません。
試し行動の対応に難しさを感じた時は?

「試し行動が続くけれど、愛情不足なのかな?」
「子どもの気持ちを受け止めてあげたいけれど、つい感情的になってしまう時がある……」のように、保護者のかたも日々忙しく、受け止めてあげたくても余裕が持てず、つい感情的になってしまうこともあるかもしれません。
試し行動が続くお子さまの対応に悩んだ時は……
・パートナーやご家族に相談する
・自治体の子育て相談を活用する
・子育て相談をしている小児科を頼る
などの方法を取ってみてください。
自治体の子育て相談では、対面だけでなく電話やSNSなど、自治体ごとにさまざまな場や相談方法が選択できるようになってきています。一人で抱え込まず、信頼できる相談先を探してみてくださいね。
まとめ & 実践 TIPS

試し行動は、「もっと自分を見て」「どんな私でも受け止めて」という、子どもの思いや気持ちからくる行動です。試し行動の存在を知っているだけで、「もしかしたら我が子はもっと注目してほしいのかも」のように、子どもの声に出せていない気持ちに気付けるかもしれません。
「これは試し行動かな?」と感じた時は、まずはお子さまの気持ちを受け止めてあげましょう。お子さまの心に寄り添いながら、よりよい信頼関係を築いていけたらいいですね。
編集協力/海田幹子、Cue`s inc.
- 育児・子育て














