第一次反抗期はいつ?子どもの自我の芽生えと葛藤を受けとめてあげよう
- 育児・子育て

「イヤ!」「自分で!」など、自己主張が激しくなる「第一次反抗期」。「イヤイヤ期」や「魔の2歳児」などとも呼ばれ、あまりの反抗に困ってしまう時もあるかもしれません。第一次反抗期はいつ、どうして訪れるのでしょうか? 今回は、発達心理学の専門家である川村学園女子大学の菅井洋子先生に、第一次反抗期とその対処法についてお話を伺いました。
第一次反抗期って何? いつから始まる?

子どもの成長過程で、反抗期は第一次反抗期と第二次反抗期の2種類あります。第一次反抗期は早いと1歳を過ぎたあたりから2、3歳の時期にかけてあらわれることが多く、一方、第二次反抗期は思春期にあらわれます。
第一次反抗期のことを、日本では「イヤイヤ期」や「魔の2歳児」、海外では「the Terrible Twos(テリブル・ツー)」などと呼ばれ認知されています。子どもによって反抗の程度や開始時期に差はありますが、基本的に、第一次反抗期はほぼすべての子どもに見られる現象なのです。
保護者のかたから見ると「イヤイヤ期」や「反抗期」だとしても、お子さまの視点からは「自分でやってみたい期」「自己主張期」「自我の芽生え期」などと言い換えることができます。「イヤイヤ期が近づくと怖いな……」というイメージを持たれるかもしれませんが、反抗期は子どもの発達にとってとても大切なことなのです。
第一次反抗期はどうしてあらわれるの?

第一次反抗期は自我の芽生えと葛藤のあらわれ
第一次反抗期は、多くの場合で「一人でできる・やりたい」という自我の芽生えと、「一人でできない自分」という現実との葛藤(かっとう)から生まれます。
歩けるようになったり、指先が器用に動かせるようになったり、1歳を過ぎたあたりから子どもができることは増え、行動範囲が大きく広がります。できることが増えると、「自分一人でできる」という自信と誇りが芽生える一方で、当然まだ自分一人ではうまくできないこともたくさんあるのが現状です。
そして「自分一人でできない」時、その状況をうまく伝えられないと、ひと言「イヤ!」と言ったり、癇癪(かんしゃく)を起こしたりといったことにつながるのです。保護者のかたにとっては大変な時期かもしれませんが、「イヤ」と言えるくらい自己主張ができるようになったという成長の証(あかし)ともいえます。
第一次反抗期は、ずっと続くわけではありません。3歳から4歳後半ころに、自分を主張する自己主張が急に増えるとともに、3歳から小学校に入るころまでに少しずつ自分を抑える自己抑制がみられるようになり、自分の感情や行動をコントロールすることができるようになっていきます。
先生や保護者、友達といろいろなやりとりをして、時には失敗しながら、自分をコントロールする力が養われていき、次第に第一次反抗期は落ち着いていくのです。
反抗期が見られないけれど大丈夫?
反抗期が成長の証と聞くと、「うちの子、イヤイヤ期が見られないのだけれど大丈夫……?」と心配する保護者のかたもいらっしゃるかもしれません。前述したとおり、程度差はあるものの第一次反抗期は基本的にほぼすべての子どもに訪れます。
「イヤイヤ」が見られない場合は、「イヤ」とは別の自己主張であらわれているかもしれませんし、まだその段階ではないのかもしれません。第一次反抗期の時期や表現のしかたには個人差があるのです。
お子さまに目立った反抗が見られなくても、心配しすぎず見守ってあげましょう。
第一次反抗期の子どもとどう向き合ったらいい?

第一次反抗期の子どもの行動には、言葉では伝えられない隠れた主張があることがほとんどなので、子どもが何を伝えたいのかを理解して、身体の動き等から理解し受けとめることが大切です。
言葉がわかる年齢であれば、「どうしたの?」「自分でやってみたいの?」「お手伝いしようか?」などと聞いてみてください。子どもの主張が理解できたあとは、できるだけ子どもに寄り添った対応がとれるといいでしょう。
ただ、ひと言「理解することが大切」とはいっても、子どもの考えをくみ取るのはとても難しく、試行錯誤が必要になるかもしれません。子ども自身を否定してしまうことや急に強い口調で言うことは、子どもの「自分でやってみたい」という気持ちを押さえつけてしまうことにつながります。できるだけ子どもの気持ちに寄り添った声をかけられるといいですね。
【Q&A】第一次反抗期の子どもへの対応策

Q1.「子どもがやりたかったことを先回りして、子どもが泣いてしまいました」
A:子どもの気持ちに共感してから、次回チャレンジすることを話すのがおすすめ
「お菓子の袋を子どもが自分で開けたかったのに、先に開けてしまった」
「大きなクッキーを子どもが自分で割って食べたかったのに、先に割ってしまった」など
子どもが自分でやりたかったことを、保護者のかたが先回りしてしまうことはよくあります。
もとに戻せる場合は、もう一度戻して子どもが自分でチャレンジできるようにしてみるといいですね。もとに戻せない場合は、「自分で開けたかったんだね」のように、まずは子どもの気持ちに共感することが大切です。そして、「次はやってみようね」と先を見通し、言葉でわかりやすく伝えることで、気持ちが落ちつくこともあるでしょう。
Q2.「買い物でおもちゃ売り場に寄ってしまうと、『買って買って!』と泣き叫んで動きません」
A.前もって買えないことを伝えておくのがおすすめ
その場に欲しいものがあるのに、「これは買えないよ」と言われてもなかなか理解できないものです。また、子どもの要求すべてを受け入れることはできません。
年齢にもよりますが、「今日はおもちゃ屋さんじゃなくて、野菜を買いにスーパーに行こうね」「おもちゃ屋さんに行って、誕生日の時に買うおもちゃを見てみよう。楽しみだね」と、出かける前に「欲しいものがあっても今日は買わない」ということを伝えておくことがおすすめです。
前もって「行かない」「買わない」と聞いておくことで、行きたくても、欲しいものがあっても、先を見通して気持ちが落ち着くこともあるかもしれません。
Q3.「公園に行くとなかなか帰ってくれません……声をかけるだけで『イヤ!』と言われてしまいます」
A.早めに帰る時間を伝えることで、子どもに帰る心づもりをする時間をつくることがおすすめ
声をかけるだけで「イヤ!」と反応できるということは、先を見通す力があるというあらわれなので、お子さまの成長が感じられますね。しかし、決めた時間に帰りたいという保護者のかたの気持ちもとてもよくわかります。
帰る時間になって「さあ、帰ろう」と言っても、子どもは帰る心の準備ができていないため、「イヤ!」「まだ帰らない」と言われがちです。そこで対策としては……
・「イヤ」と言われるのを見越して、帰りたい時間の10分前に声をかける
・公園の時計を使って「あの針が12にきたら帰ろうね」と伝える
など、前もって帰る時間を知らせ、家に帰ったら何をするかを家に帰りたくなるように伝えることが大切です。
何回もくり返し同じルールを伝えることで、子どもの中でルーティン化するため、すんなりと帰れるようになるかもしれません。
第一次反抗期の子どもの対応に難しさを感じた時は?
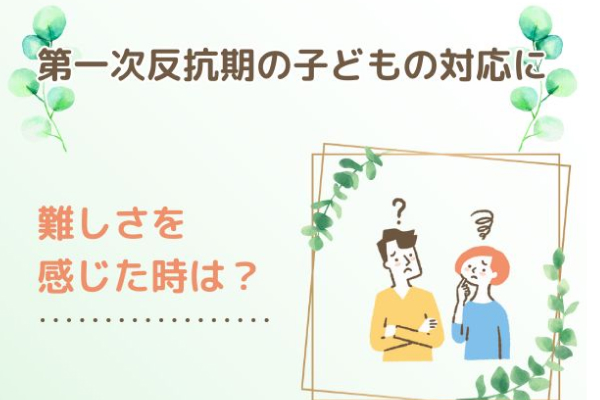
「子どもに寄り添ったほうがいいのはわかっているけれど、感情的になってしまう時がある……」など、第一次反抗期の子どもへの対応に難しさを感じる時もあるかもしれません。
そのような時は、
・パートナーやご家族に相談する
・地域の園や子育てセンターに行ってみる
・自治体の子育て相談を活用する
・子育て相談をしている小児科を頼る
・月齢の近い子ども、少し年上の子どもの姿を見てみる
・子育て中の保護者のかたに相談する
などの方法がおすすめです。
自治体の子育て相談では、対面だけでなく電話やSNSなど、自治体ごとにさまざまな相談方法が選択できるようになってきています。一人で抱え込まず、信頼できる相談先を探してみてくださいね。
まとめ & 実践 TIPS

「自分でやってみたい!」という自我の芽生えと、「自分一人でできない」という葛藤から起こる第一次反抗期。お子さまの言葉で伝えられない主張を読み取り、できる限り気持ちに寄り添った対応をすることがおすすめです。第一次反抗期は、ほとんどの子どもに見られる現象ですが、個人差が大きく始まる時期や程度もさまざまです。「子どもに寄り添いたい」と思うものの、難しい時もあるでしょう。この時期のみの子どもの姿を、家族に相談してみたり、自治体の子育て相談を頼ってみたりして、無理せずお子さまの成長を見守れるといいですね。
編集協力/海田幹子、Cue`s inc.
- 育児・子育て














