好奇心が走り出す!天体への興味から「探究的な学びを拓く」3つのアクション

お子さまが星座や星空に興味を示した時、どんなふうに声をかけたらよいでしょうか。
「見に行かない?」と誘ってみるのも素敵ですが、「もう少し一緒に調べてみない?」とアプローチしてみてはいかがでしょうか。
星座や天体は、天文学だけではなく実はさまざまな学問の扉を開くきっかけになります。
この記事では、国立天文台 天文情報センター長の渡部潤一さんにご協力いただき、星空への興味から探究的な学びを拓(ひら)くヒントをご紹介します。
保護者のかたもお子さまと一緒に、夜空が語るロマンに思いをはせてみませんか?
「探究的な学びを拓く」アクション1:「そもそも星座ってなに?」を深掘りしてみる

「そもそも星座ってなに? なんのためにあるの?」
夜空を見上げて、スマートフォンの星座アプリなどを活用しながら「今日はおおぐま座が見えるみたいだよ」などと一緒に話す中で、お子さまからこんな質問が飛んでくるかもしれません。
星座はもともと、古代の人々が夜空の星々を線で結んで動物や道具、英雄の姿などに見立てたことから始まりました。
現在知られている星座は、メソポタミア文明から始まってギリシャ文明へ伝えられ、ギリシャ神話と結びついて世界に広まったとされています。
では、星座はなぜできたのでしょうか?
それは、遊牧民の生活と結びついています。
古代メソポタミア(ティグリス・ユーフラテス川流域)地方の人々は星の動きによって方角を知り、移動する時の方角を決めていました。
また農耕においても、星座は重要な役割を果たしていました。
日本ほど四季の変化が明確でない西アジアやエジプトなどでは、星座は季節や時間の推移を知るツールとして活用されていたのです。
国立天文台の下記のサイトなどで星座の成り立ちについて調べてみると、お子さまが古代の歴史に興味を持つきっかけになるかもしれませんね。
「探究的な学びを拓く」アクション2:「自分の星座」を調べてみる
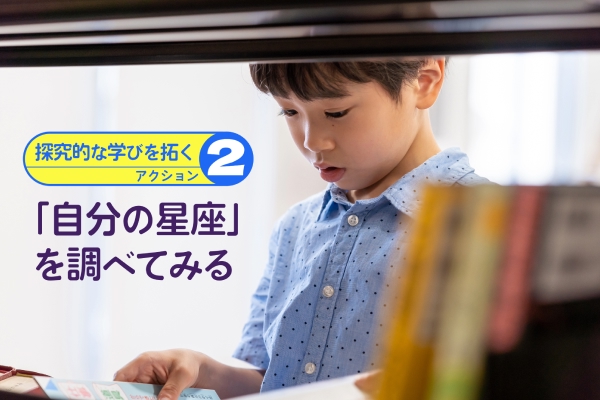
小学生になると、テレビやウェブサイトで目にするなどして「12星座占い」に興味を持つようになるお子さまも少なくないはず。
現在知られている「黄道12星座」は、太陽が1年かけて通る道「黄道」に位置する12の星座のことで、「生まれた時に太陽がどの星座の近くにあるか」でその人の星座が決まります。
星占いをきっかけに「自分の星座はなんだろう?」と調べることは、季節ごとに移り変わる星座に対する興味のきっかけになります。
また、「自分の星座を実際に見てみたい」とお子さまが言い出したら、太陽の動きについて知るチャンス。
実は、誕生日に自分の星座を見ようと思っても、太陽があるため見ることができません。
たとえば3月下旬から4月下旬生まれのお子さまは「おひつじ座」ということになりますが、おひつじ座が実際に観測できるのは秋から冬にかけてです。
「どうして時期がずれるのか一緒に調べてみようか?」と声をかけてあげてもよいですね。
お子さまの星座は、下記の国立科学博物館のウェブサイトから調べることができるのでご活用ください。
「探究的な学びを拓く」アクション3:「天の川」と「北斗七星」について調べてみる
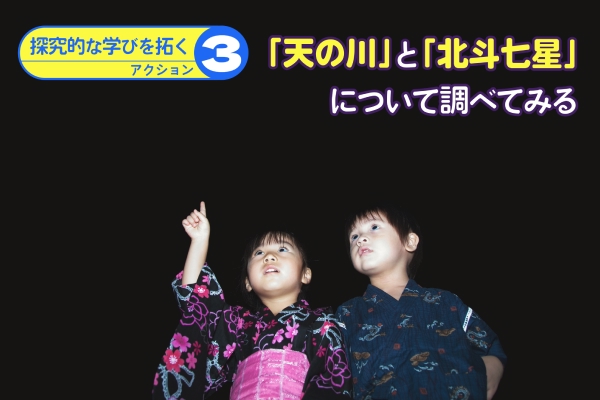
街灯の少ない自然豊かな場所へ天体観察に出かけると、普段よりたくさんの星々を見ることができます。
満天の星空で特に目立つのは、やはり夜空を横切る星々の集まり「天の川」ではないでしょうか。
天の川というと、日本では七夕伝説(七夕の夜にカササギが橋を架け、織り姫と彦星が出会う)を思い浮かべる人が多いかもしれません。
「亡くなった人の魂(たましい)を天国へ導く川」という伝説が伝わっている地方もあります。
一方、ギリシャ神話では、ゼウスの妃(きさき)であるヘーラ女神の胸からほとばしり出た乳が天の川になったと伝えられています。
また古代エジプトでは「天のナイル川」、バビロニア地方では「天のユーフラテス川」、インドでは「天のガンジス川」と呼ばれ、土地を潤す川の水が天からやってきたと考えられていました。
一方ロシアでは、鳥が南に渡る時に方角を知らせる「鳥の道」と呼ばれています。
同じ天の川でも、国・地域によって伝わる話が異なることがわかると、「その国・地域が何を大切にしてきたのか」が見えてきそうですね。
星座にまつわる伝説・神話に関しても、渡部さんによれば近年はヨーロッパだけでなくアジアなどさまざまな国にも言い伝えや伝承があることがわかってきました。
たとえば、冬から春にかけて観察しやすい北斗七星(おおぐま座の一部)には、ギリシャ神話やアイヌの民話、アメリカのネイティブアメリカンによる伝承など多くの逸話があります。
お子さまと保護者のかたが手分けして調べて、どんな違いがあるかを話し合うのもよさそうです。
一例として下記の日本気象協会のウェブサイトにも、北斗七星にまつわる各地域の伝承が紹介されているので、調べてみてはいかがでしょうか。
北斗七星は天の帝の乗り物? 北極星は王子さまの化身? 日本とアジアの星物語(春編)(季節・暮らしの話題 2016年02月28日) - 日本気象協会 tenki.jp
まとめ & 実践 TIPS
天体への興味をきっかけに、保護者のかたがちょっとした声かけやサポートをしてあげることで、お子さまは星のことだけではなく理科や地理、歴史といったさまざまな世界にも興味・関心を広げることができます。
「勉強」と思ってしまうとつまらないので、「知ることで星を見るのがもっと楽しくなるかも」というワクワクを大切に、お子さまと一緒に探究の扉をたたいてみましょう。














