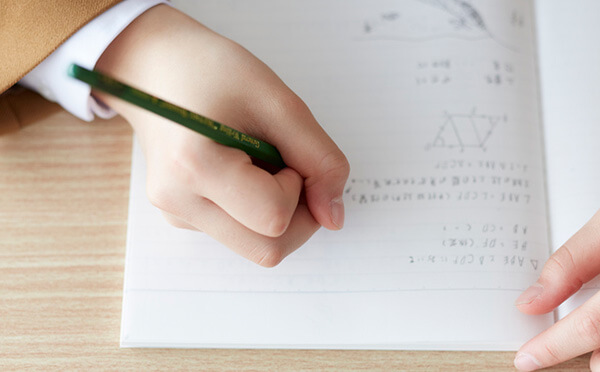【定期テスト対策】あなたはどちらのタイプ?「まとめノート」をつくる派、つくらない派
お気に入りに登録
定期テスト対策のひとつ、まとめノートづくり。合格した先輩たちに話を聞くと、「役立つからぜひ!」と言う人と、「ほかの対策をした方がいい!」と言う人がいるようです。いったいどっちが正しいの!?

まとめノートづくりは効率が悪い!?
定期テスト対策の「定番」といわれている勉強法のひとつが、まとめノートづくり。ご存じの通り、授業で習ったことや自分の苦手なところ、わからないところを、教科書や資料などを見てノートにまとめ直す作業のことです。まとめることがそのまま試験範囲の復習になるので、学校の先生の中にもすすめている人が多いようですね。
ただ、このまとめノート、「つくらなくていい」という意見があるのも確かです。もちろん、「ただ面倒くさいから」ではありません。「まとめノートづくりは効率のいい勉強法とは言えない。その時間をほかの勉強に使ったほうが有効だ」と話す人が、志望校に合格した先輩たちにも少なくないのです。
それぞれのメリットとデメリットは?
ではいったい、テスト対策としてより良いのはどちらなのでしょうか。まとめノートをつくる勉強法、つくらない勉強法それぞれのメリット(長所)、デメリット(短所)を挙げてみましょう。
■まとめノートを<つくる>と…
【メリット】
・知識が整理されて、深く理解できる。
・苦手な部分を強調するなど、自分専用にアレンジできる。
・後日、復習するときにすぐに見直せる。
【デメリット】
・時間がかかる。問題演習が後回しになる。
・見た目にこだわって、ノートづくり自体が目的になってしまう。
・ただ写しているだけで、勉強した気になってしまう。
内容を整理したり、足りないところを調べたりと、つくる過程で理解が深まるのがまとめノートのいいところ。定期テストが終わったあとも、模試や受験のときの復習にも便利です。ただし、つくるのにどうしても時間がかかるので、テスト直前の対策としては向いていません。また、頭を使ってつくらなければ、勉強としての効果は見込めません。
■まとめノートを<つくらない>と…
【メリット】
・教科書やプリントを何度も読み返せる。
・問題演習に時間をかけられる。
【デメリット】
・理解できていないまま問題を解いても効率が上がらない。
・角度を変えた問題を出されると対応できないことがある。
・後日、復習するときに見直しがしづらい。
まとめノートをつくる時間を省く分、教科書を何度も読み返したり、問題をたくさん解いたりすることができます。より実戦的な方法と言えそうですが、教科書の内容が難しくてわからない場合、基礎をしっかり理解できていない場合などは、問題を解いても効果が上がりません。模試や受験前に復習するときに、すぐに見直せない点もマイナスです。
弱点を補う方法を知っておこう
どちらの方法にも一長一短がありますね。結局、自分のタイプによって、また対策する科目によって、特徴を理解したうえで使い分けるのが賢いやり方と言えるでしょう。
■まとめノートを<つくる>なら…
書くことによって理解が進むタイプの人、また、そういう科目には有効です。時間に余裕をもち、必要な科目、単元に絞ってつくることが大切。問題文や本文はコピーを貼ったり、教科書の内容がまとめられた教材を使ったりするのもひとつの手です。ノートをつくって終わりではなく、問題を解いて理解を確かめることを忘れないでください。
■まとめノートを<つくらない>なら…
教科書(のコピー)や授業用ノートに、自分が理解しやすくなるような補足や足りない情報を書き込んで、「これを見れば復習できる」という状態にしておきましょう。当然ですが、まとめノートをつくらず、問題も解かない、ということでは対策になりません。必ず問題を解き、わからないところがあれば教科書や授業用ノートに戻りましょう。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 先輩を勝利に導いた「合格する」効果的な暗記方法ランキング
- 成績アップ!勉強ノートの作り方と書き方の注意点は?東大式ノート術も紹介
- いつもどこか間違える?! ひらがなをきちんと覚えてもらうための対策
- おもしろくて、ためになる! 博物館の歩き方【前編】見学編
- 子どもの力を伸ばす効果的な勉強法とは? 「計画立て」と「振り返り」
- 不登校の本当の原因は、親が聞いているものと違うかも。そんな時の親の対応は[不登校との付き合い方(6)]
- 学習習慣の定着には、時間の「可視化」がカギ!ウィズコロナで学びを止めないために(1)
- 定期テスト前に役立つ「授業ノート」の取り方
- 東大王のクイズ軍団QuizKnockメンバーにノート法を聞いたら、こだわりは違うけれど大切にしているものは共通だった