小学生の図形問題 二次元と三次元はどうやって理解させる?
お気に入りに登録
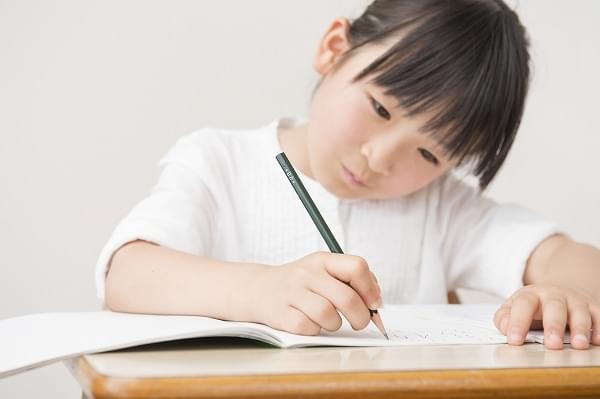 図形問題は子どもには理解しづらく、どのように勉強させるかは、よくある相談だ。そこで、ベネッセ教育情報サイトでは、平山入試研究所の小泉浩明氏にわかりやすい図形の理解の仕方について伺った。
図形問題は子どもには理解しづらく、どのように勉強させるかは、よくある相談だ。そこで、ベネッセ教育情報サイトでは、平山入試研究所の小泉浩明氏にわかりやすい図形の理解の仕方について伺った。
***
【質問】
立体的な図形の理解に時間がかかります。さいころや箱などを実際に見ながらだと、イメージがわくようです。簡単な計算はほぼ間違いなく解くことができます。(小学3年生の保護者)
【小泉氏からのアドバイス】
立体図形に強くなる、すなわち空間認識能力を高めるには、立体図形に慣れ親しむことが大切です。日常的な遊びも含めて、立体を身近に感じる作業をされるとよいでしょう。
たとえば、飲み終えた牛乳パックを展開してみてもいいですね(ナイフやハサミの取り扱いに注意しましょう)。これは、立体を平面にする作業です。飲み口の部分の折り方が、面白いかもしれません。あるいは、立方体のお豆腐をいろいろなところから切ってみましょう。こうした展開図や断面図は、実際の入試にもよく出てきます。実際に体験してみることで、立体図形に対する理解が深まることと思います。
次に、立体図形の絵を描いてみるのもよいでしょう。これは、三次元のものを二次元にする作業です。お手本は、問題集などにある絵や図を参考にするとよいと思います。絵画を描くわけではないので、実線、波線を使い分けて見えない線も図に描いてください。最初のうちは不格好な図になってしまうかもしれませんが、何回か描いていくうちに、平面に描いた図が立体に見えてくると思います。たとえば、立方体を描く場合、正面を向いている正方形以外は、長さを短くしないと立方体らしく見えません。この辺りに最初はとまどうかもしれませんが、要領がわかれば上手に描けるようになってきます。
また、平面を立体化してみるのもよいでしょう。たとえば、動物の写真集から、馬の絵を選んで、紙粘土などでできるだけ忠実に立体的に再現してみるのです。1枚の写真だけではわかりづらければ、いろいろな方向からの写真があればさらによいでしょう。馬の粘土像を作るわけですが、これは平面を立体化する作業になります。最初はなかなかそれらしい像が作れないと思いますが、慣れてくると小学生でもかなり上手になると思います。
出典:立体的な図形の理解に時間がかかります[中学受験] -ベネッセ教育情報サイト
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 低学年のころは勉強が得意だったのに……高学年での成績の伸び悩みを解消するには
- 麻布中の入試国語問題「友情」「家族」「生命・死」などが頻出
- 【高1保護者応援】教えて!進路プロVOL.6「テスト後こそ保護者の出番!?」
- 線分図や面積図など、どの図をどの問題で使えばいいのかがわかりません
- 国語も算数も問題を解くのが遅い!対策するなら志望校頻出の不得意分野から
- 言い換えるだけ!定期テスト前に中高生のやる気を引き出す声かけ5選
- 【高校受験】「偏差値が下がった」=「学力が低下した」ではない?!保護者が知っておきたい入試直前対策
- 中学受験に役立つ読書感想文への取り組み方(1) コツは中学入試によく出る作家の本を選ぶこと! おすすめの本4選と、国語力を高める書き方
- 【もっと教えて! 進路プロ】入学後に後悔しない大学・学部選びとは?















![算数「立体」[中学受験]](http://benesse.jp/common/static/kj/common/images/chu/tukamu17/01.gif)








