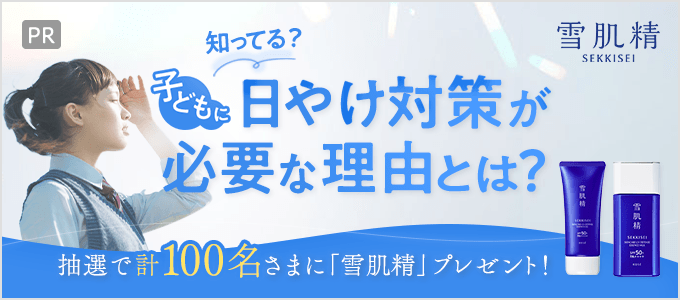首都大学東京 都市環境学部 自然・文化ツーリズムコース [大学研究室訪問]
お気に入りに登録
日本が転換期を迎えた今、大学もまた大きく変わりつつあります。そんな時代に、大学や学部をどう選び、そこで何を学べば、お子さまの将来が明るく照らされるのでしょうか。首都大学東京の小崎隆先生が学生育成のために重視していることなどをお聞きします。
1年生で経験できるワールドワイドなエコツーリズム体験

学生たちのカザフスタンへのエコツーリズムツアー
エコツーリズムを実際に学生に体験させたいと、1年生の基礎ゼミという教養科目と関連させてカザフスタンのアラル海周辺地域への研修旅行を行いました。長期休業期間を利用して希望者のみ13名ほどが2週間ほど滞在しました。
学生たちはアラル海でどんな問題が起きているのかを知る由もありません。そんななか、現地の漁業関係者や農業関係者などの家に泊まって話を聞くリアルな機会を設けました。
感想を書かせたところ、「教科書では得られない経験だった」「本物に触れることで大変な衝撃を受けた」といった前向きなコメントが寄せられました。私は、環境問題とどう自身がつながっているのか、自分ができることとは何なのかを考える機会にしたいという思いでした。海外へ初めて行く学生などもいましたが、私の予想以上に皆、世界の問題をとらえようと自ら調べ、頭を使っていました。
石垣島でフィールドワークを続け、多面的な学びを得た学生も
ゼミ生の中には、自分の頭で考えて環境問題に挑んだ者もいます。昨年卒業したゼミ生は、石垣島を研究の対象としていました。石垣島では、畑の土壌が海に流れ出しサンゴが死滅するということが問題になっています。
この環境問題に対し、シカクマメという豆を海の手前の畑に植えると、根や葉が繁茂し土壌の流出が止まるということは知られていました。彼はそれを農家の方々に伝えて、シカクマメを植えるように促します。しかし、何に使えるかわからない豆を大切な畑に植えてくれるはずがありません。
そこで、彼はシカクマメの商業的利用について調査を始めます。結果的に、たんぱく質が多いので味噌(みそ)づくりに有効だとわかり、観光客に人気が出そうな、味噌アイスクリームにして販売することを提案したのです。
土壌侵食問題をクリアし、サンゴを守るということが彼の関心でしたが、プロジェクトを進めていく中で環境の問題だけではおさまらない知識と実践が必要になっていきました。農業や文化の理解、商業・マーケティング、観光業……ありとあらゆる学びから得た知識を彼はつなげていったのです。
実際に社会の中で自分が取り組むべき課題を見つけたら、文系だから数学ができない、理系だから歴史はわからないなどとは言っていられません。問題を解決するために調べ抜き、知識を得て、知見をつなぎ合わせていくことが必要になってくるのです。その力が教養というものなのではないでしょうか。
関心を育てる授業を実践
幅広い教養と同時に大学で育んでいくべきなのは、学生の興味・関心だと思っています。
そのために、私はあえて授業の中で「まだ解明されていないこと」を紹介します。「実はこの原因はまだわかっていないんだよね」「この部分は研究者も意見が分かれていてね」と、学生たちに検討材料を投げかけています。
学生たちから毎授業後アンケートをとっているのですが、「この部分が不思議だ」「もっと詳しく調べたい」など、興味・関心の種が育っていることを実感できる言葉が寄せられています。
社会問題を自分ごととしてとらえ、多様な領域に関心を向け、教養をつなぎ合わせて考えられる人間を、社会はこれから求めているのではないでしょうか。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- まなびのかたち│【 多様な学びを促す学校の“場”づくり】第2回 学びに向かう場づくり
- 難関高校合格者は中学入学時から成績がトップクラス 中学準備で差をつけて
- 首都大学東京 都市環境学部 自然・文化ツーリズムコース[大学研究室訪問]
- CO-BO│発達障害のある人たちの就労に関わる問題
- あなたならどうする?赤ちゃんの泣きやませ方
- 津田塾大学学芸学部 国際関係学科多文化・国際協力コース(1) 自分のテーマを、自分の言葉で語れる--大学でそんな力を付け、世界の舞台へ[大学研究室訪問]
- あスコラ│Vol.1 『僕たちが考える最高の授業!』
- 子どもを叱るときに「鬼がくるよ!」「お化けが出るよ!」と脅すのはアリ?
- 津田塾大学学芸学部 国際関係学科多文化・国際協力コース(2) 学生時代にしっかり勉強をした人こそ、責任を持って仕事に取り組める[大学研究室訪問]













![首都大学東京 都市環境学部 自然・文化ツーリズムコース[大学研究室訪問]](/_shared/img/ogp.png)
![津田塾大学学芸学部 国際関係学科多文化・国際協力コース(1) 自分のテーマを、自分の言葉で語れる--大学でそんな力を付け、世界の舞台へ[大学研究室訪問]](http://benesse.jp/common/static/kj/common/images/juken/2013/130325_p1_1.gif)
![津田塾大学学芸学部 国際関係学科多文化・国際協力コース(2) 学生時代にしっかり勉強をした人こそ、責任を持って仕事に取り組める[大学研究室訪問]](http://benesse.jp/common/static/kj/common/images/juken/2013/130327_p1_1.gif)