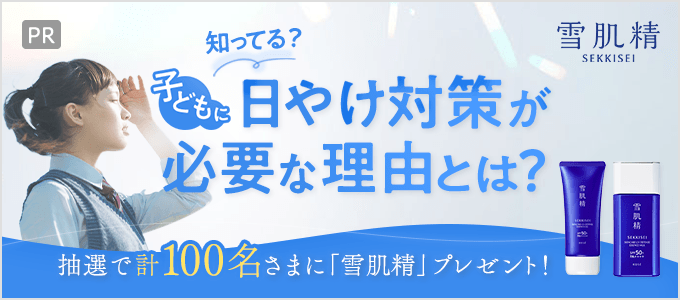苦手克服はほどほどに 子どもの「得意」を見極めて伸ばすコツ
お気に入りに登録
 人によっては中学受験が具体的に視野に入ってくる小学5年生という時期。今、取り組んでおくべきこととは何か? 中学受験のプロ、森上教育研究所の森上展安氏がアドバイスする。
人によっては中学受験が具体的に視野に入ってくる小学5年生という時期。今、取り組んでおくべきこととは何か? 中学受験のプロ、森上教育研究所の森上展安氏がアドバイスする。
***
中学受験において、苦手をつくらないことは重要です。難関校の受験を視野に入れた場合、全教科得意とはいかなくても、せめて「食わず嫌い」はなくしておく必要があります。しかし、保護者が苦手克服ばかりに気をとられていると、子どもとしては「イヤなものを押し付けられている」という意識を抱きがちになります。
この時期はぜひ、お子さまの「得意」に注目してみてください。
5年生は、認知能力の特性がはっきりしてくる時期です。コミュニケーション力に深く関係している能力として、視覚、聴覚、言語能力の3つがあります。この3つにも、得意不得意があるのです。
たとえば視覚が優位な場合、写真を撮るように、映像をそのまま記憶することが得意。ものを考える時も、頭の中で、言葉より映像を操っているといいます。聴覚が優位な人は、耳から聞いたことはよく頭に入ります。町で流れている歌や、CMのフレーズなどをすぐ覚えられる人はこのタイプ。言語能力が優れた人は、文章から情景を思い浮かべたり、体験したことを文章化するのが得意です。
保護者のかたがお子さまを見ていて、どうもこの子は視覚優位で、見て理解するほうが得意だなと思ったら、文章を読ませるより、絵や写真を見せたり、図を描いて説明したりするほうがよく理解できるかもしれません。聴覚優位ならば、文章は黙読させるより、読み聞かせや読み合わせするとよく理解できる傾向があります。言語優位で本や作文が好きならば、勉強と関係があるなしにかかわらず、どんどん読んだり書いたりすることをすすめてください。
また、視覚優位の場合、一気に全体像をとらえて理解するのは得意だけれど、言葉にするのは苦手なケースがあります。一方、聴覚優位の場合、細部を順々にとらえて、全体像をゆっくりと理解していくのが得意なようです。これらは認知の仕方の特徴であって、どちらが優れているとはいえません。
認知能力は、得意な面を伸ばしてあげることが大切です。得意な認知方法を知って、それを生かせれば、勉強が非常に楽になります。お子さまの物の見方、考え方の特性をよく観察してみてください。
出典:得意をつくる![中学受験 5年生] -ベネッセ教育情報サイト
みんなが読んでる!おすすめ記事
- わかりやすい学校案内(パンフレット)とは? [中学受験]
- 【2025年度大学入学共通テスト】「実用的な文章」の大問が新設!表現活動に関わる設問が出された国語の分析と対策は?
- 習い事、何歳から始めてる?初めての習い事やきっかけは?【保護者のホンネ】
- 「情報モラル教育」、学校でどうやるの?
- 【Q&A】中学受験の国語「得意な子」と「苦手な子」の特徴は? 苦手克服の勉強法と読解のコツ
- 大学授業レポート│【私立大学初のデータサイエンス学部 学部長インタビュー】 「研究体験連動型学習」により、1年次から海外研究機関、企業等との実践、研究を実施 世界で活躍できるマインドとスキルを身につける
- 岡山操山中学2年生が作った学校パンフレットを特別公開!
- 【小学生が習う漢字 学年別一覧】漢字を正しく効率よく覚えるコツ、苦手克服法も解説! 漢検にも挑戦してみよう
- 大学授業レポート│「人の夢を笑わない」。 自由に夢を語り、その実現を応援する環境の中で、 社会に新たな価値を創造していくマインドとスキルを磨く















![ほめて励ます……女の子を伸ばすコツ[中学受験]](/_shared/img/ogp.png)