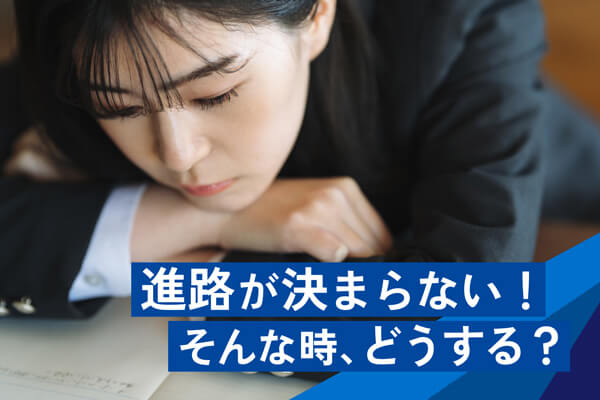ロボットがサッカーW杯を制する!? 大学のロボット学科の研究室訪問
お気に入りに登録
 大学や学部をどのように選び、何を学べば将来につながるのか。そのヒントを求めてさまざまな大学の研究室を訪ねるシリーズ。今回は、ヒューマノイドロボットの研究に取り組む、千葉工業大学工学部未来ロボティクス学科、林原靖男氏の研究室に伺った。
大学や学部をどのように選び、何を学べば将来につながるのか。そのヒントを求めてさまざまな大学の研究室を訪ねるシリーズ。今回は、ヒューマノイドロボットの研究に取り組む、千葉工業大学工学部未来ロボティクス学科、林原靖男氏の研究室に伺った。
***
研究室では、柔らかな関節を持ち、人との親和性を重視するロボットから、人と協調して働く知能ロボットまで、さまざまな種類のロボットの実用化をめざしています。得意分野は、自らの目で状況を判断し、動くことができるヒューマノイドの研究です。ロボットの国際サッカー大会「RoboCup(ロボカップ)」では、2012年、2013年と2連覇中です。
「RoboCup」は、ロボット工学と人工知能の融合、発展のために日本の研究者らによって提唱されスタートした大会です。「西暦2050年、サッカーの世界チャンピオンチームに勝てる、自律型ロボットのチームを作る」という夢に向かって、世界中の研究者たちが参加しています。
ロボット開発技術の進歩を支えているのが工学の力。工学は新しい発見があると、それを工学者の共通言語である式の形で表し、その式や手法を世界中に広めていく学問です。「RoboCup」でも同様に、多くの時間と人手をかけて作った技術の内容を無償公開します。ですから、昨年私たちが作ったロボットは世界中のチームが知っているため、同じロボットでは2度優勝できません。ライバルに勝つロボットではなく、「どうしたら人間に勝てるのか」を考え、年々ロボットを進化させているのです。
抽象的な研究ではゴールが定まっていないため、高いモチベーションを維持するのは難しいですが、コンテストに参加するなど目標が明確だと、学生は伸びます。同じ課題に向かって学部1年生から大学院2年生までが協力してチームで開発を進めることも、互いによい刺激になります。また、コンテスト参加を通じて、世界中の仲間からも多くの刺激を受けることが、学生の成長につながっていると感じています。
出典:千葉工業大学 工学部 未来ロボティクス学科 サッカーW杯の優勝チームに勝てる自律型ロボットを作る! -ベネッセ教育情報サイト
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 1年生の漢字 家庭学習を始めるときに大切なこと 興味や関心を持って学んでいくためには
- 「はやぶさ」をきっかけに、宇宙開発と自分の夢について考える
- 「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]
- 子どもに思いやりの心を持ってもらうためには? 心を育むために保護者ができること
- 「はやぶさ」をきっかけに、宇宙開発と自分の夢について考える
- 進路が決まらない!そんな時に、高校生と保護者がやるべきこと【体験談あり】
- 自分の荷物は自分で持とう! 保育園・幼稚園の送り迎えで意識してほしいこと
- 「食の安全」への興味をきっかけに、私たちの「食」について考えよう
- クラス替え 仲のよい友達とクラスが分かれて元気がない我が子…何と声をかける?













![「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]](/img_o/kj/kyouiku/201003/20100309-1.jpg)