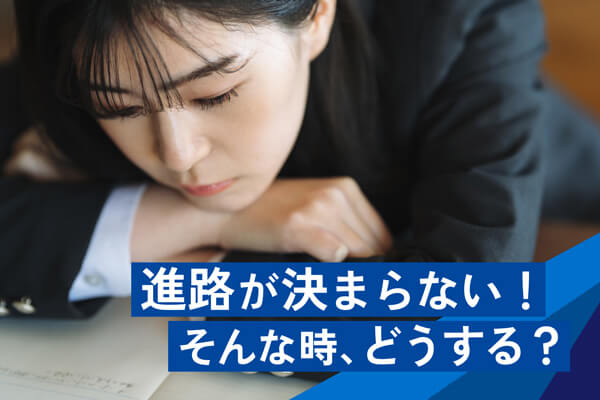中学受験、国語の問題の克服に必要なものは「○○的」な視点
お気に入りに登録
 子どもにも読みたい文章や読みたくない本があるだろう。しかし、入試問題であれば読まないわけにはいかない。大ざっぱ・感情的なタイプの子どもが文章をより好みし、それが国語の成績に反映されることに悩む保護者に、平山入試研究所の小泉浩明氏がアドバイスしてくれた。
子どもにも読みたい文章や読みたくない本があるだろう。しかし、入試問題であれば読まないわけにはいかない。大ざっぱ・感情的なタイプの子どもが文章をより好みし、それが国語の成績に反映されることに悩む保護者に、平山入試研究所の小泉浩明氏がアドバイスしてくれた。
***
【質問】
物語文・説明文共に、文章の好き嫌いが問題の正答率にも比例して、成績にとても波があります。どうしても自分目線でしか物事をとらえられません。読書する際には自分の気に入った本しか読みません。(小6男子の母親)
【小泉氏からのアドバイス】
入試問題の国語は答えが一つになるように問題を作られているので、「客観的な考え方」が必要です。表現の仕方がいくつもあったとしても、必要な要素は決まっていて、それが採点基準となります。
大ざっぱなタイプは、文章全体を大きなイメージでとらえがちですが、これは悪いことではありません。そのあと細かく文脈をとらえようとしないことが問題なのです。大枠でとらえたあとに、問われている箇所を中心に文脈の流れを細かく追っていく “バランス”が大切です。
自分なりに感じたことや、考えたことをいったんは遠ざけ、客観的に眺める必要があります。この時に「自分の感覚を根拠にする」ことと、「本文の内容を根拠にすること」の両方を行わないと、正しい答えにたどり着く確率が低くなります。「深読み」や「妄想」をして物語文を自分でつくってしまいがちです。
対策として、「細かく読む」ためには問われている箇所、たとえば傍線部を中心に、前とあとを丁寧に読むクセをつけましょう。「行動」→「気持ち」→「行動」という文脈の流れを読むことで、その箇所における細かな気持ちを初めて読み取ることができるのです。
さらに、いったん手元から放して本文に書いてある内容に照らし合わせ、確かに正しいことを客観的に確認することです。具体的には、「なぜその答えが正しいのか?」を自問自答します。「問題文のここに書いてあるから」と根拠を問題文の中で示せる客観性が必要なのです。他の人、たとえば保護者のかたに対して説明して納得させられるように練習するのがよいでしょう。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]
- 何から始めたらいいの? トイレトレーニング(トイトレ・オムツはずれ)、初めの一歩
- 進路が決まらない!そんな時に、高校生と保護者がやるべきこと【体験談あり】
- 応用化学ってどんな学問?
- クラス替え 仲のよい友達とクラスが分かれて元気がない我が子…何と声をかける?
- 遊びながら自然と言葉のお勉強......しりとり遊びにチャレンジしてみよう
- 小学校のクラス替えはどう決める?保護者の要望は通る?元小学校教員に聞いた
- 今さらですが行ってみた、なう。[大学受験]
- 家でのスマホ利用 家庭での約束事は?【高校生のスマホの使い方調査】













![「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]](/img_o/kj/kyouiku/201003/20100309-1.jpg)