新東名高速道路一部開通をきっかけに日本の道路について知る
お気に入りに登録
2012年4月14日、新東名高速道路が一部開通しました。道路は、鉄道などと並んで交通の重要な手段であり、歴史の中で政治や産業、文化と密接に関わりながら発達してきました。中学入試の社会でも、さまざまな形で道路について取り上げられています。そこで今回は、日本の道路について解説しましょう。
クイズde基礎知識
新東名高速道路が一部開通した区間はどこの県?/民主党のマニフェストにある道路政策とは?/東名高速道路の開通と関連の深い出来事は?/東名高速道路のルーツである「五街道」の一つは?/「五十三次」とは?
時事問題を学ぶきっかけになる題材をクイズ形式でご紹介します。基本情報の整理に、親子で時事問題について話題にするきっかけに、入試・適性検査対策に、お役立てください。
Q1
2012年4月14日、新東名高速道路が一部開通した区間はどこの県にある?
A.神奈川県
B.静岡県
C.愛知県
A1 正解は 「B.静岡県」 です。
新東名高速道路は、東京と名古屋を結ぶ東名高速道路の渋滞緩和などを目的に建設工事が進められていて、神奈川県、静岡県、愛知県の3県にまたがる計画です。東名高速道路は海の近くを通るところが多く、大地震や津波、異常気象などによって使えなくなる危険があるため、海から離れた内陸部を通る新東名高速道路は、災害に強い道路としても期待されています。
2012年4月14日に、新東名高速道路のうち、まず静岡県内を通る御殿場JCT(ジャンクション)~三ヶ日JCT間の約162kmが一部開通しました。これは、一度に開通する区間としては、国内の高速道路史上、最も長い距離です。また、今回開通した距離の4分の1にあたる約42kmがトンネルであるなどの特徴があります。開通後に迎えたゴールデンウイークでは、東名高速道路のこの区間の混雑が大幅に改善され、30km以上の渋滞が2011年度の13回からゼロになりました。
今後、2014年度には、主に愛知県内を通る浜松いなさJCT~豊田東JCT間が開通し、2020年度には主に神奈川県内を通る伊勢原北IC(インターチェンジ、仮称)~御殿場JCT間が開通して、全長約254kmの高速道路になる予定です。
新東名高速道路(御殿場JCT ⇔ 三ヶ日JCT)の概要

NEXCO中日本ホームページより作成
http://www.c-nexco.co.jp/shintomei/section.html
Q2
民主党に政権交代した2009年衆議院総選挙の際、マニフェストとして掲げていた道路に関する政策は?
A.高速道路料金を原則として無料化する
B.休日の高速道路料金の上限を1000円にする
C.ETC利用者の高速道路料金を割引きにする
A2 正解は 「A.高速道路を原則として無料化する」 です。
現在、日本の高速道路を通行する際には、原則として通行距離などに応じた料金を支払わなければなりません。これに関して民主党は、政権交代した2009年の衆議院総選挙の際、高速道路料金を首都高速、阪神高速を除いて無料化社会実験の対象区間にする方針をマニフェストとして掲げていました。
高速道路料金の無料化がもたらすよい影響として、一般道の渋滞が少なくなること、トラックなどで高速道路を使って物を運ぶのにかかる費用が少なくなること、旅行などのレジャーに行く人が増え、経済が活性化することなどが挙げられます。
その半面、好ましくない影響として、無料化によって個人や家族での自動車の利用が増え、一度にたくさんの人や物を運べる電車などの公共交通機関の利用が減るため、地球温暖化の原因となる二酸化化炭素排出量が増えることなどが考えられます。
こうした影響を調べるため、2010年から一部の高速道路で無料化に関する社会実験(新たな政策などを本格的に導入する前に、場所や期間を限定して実施し、効果や影響を確かめること)が行われましたが、2011年3月の東日本大震災を受けて、2011年6月から実験は一時凍結され、2012年5月末現在、再開されていません。
Bの「休日の高速道路料金の上限を1000円にする」は、2009年3月から大都市圏を除く高速道路で実施された制度で、高速道路の無料化実験の凍結と同じ2011年6月に終了しました。Cの「ETC利用者の高速道路料金を割引きにする」は、料金所を止まらずに通過でき、渋滞解消につながるとされるETC(電子料金収受システム)の普及のために実施されている制度で、時間帯や区間などによってさまざまな割引きがあります。
Q3
1969年の東名高速道路全線開通と関係の深い出来事は?
A.東京オリンピック
B.日本万国博覧会(大阪万博)
C.石油ショック
A3 正解は 「B.日本万国博覧会(大阪万博)」 です。
東京と名古屋を結ぶ東名高速道路は、1969年に全線開通しました。先に開通していた区間も、名古屋と大阪・神戸を結ぶ名神高速道路と接続したため、東京と大阪という2大都市が結ばれることになったのです。
その翌年の1970年、アジア初の万国博覧会である日本万国博覧会(大阪万博)が大阪で行われ、新しくできた道路を通り、東京と大阪をたくさんの人や物が行き来しました。
Aの東京オリンピックが行われた1964年には、東京と大阪を鉄道で結ぶ東海道新幹線が開通し、東京周辺の首都高速道路が整備されています。高度経済成長期には、世界的な大きなイベントの開催が、交通網の発達につながっていたのです。Cの石油ショック(石油危機、オイルショック)は、1973年と1979年、石油の生産量の減少や価格の大幅な上昇によって生じた世界的な経済的混乱のことです。
Q4
東名高速道路や新東名高速道路のルーツともいえる、江戸時代の「五街道」の一つは?
A.日光街道
B.奥州街道
C.東海道
A4 正解は 「C.東海道」 です。
江戸時代のおもな街道
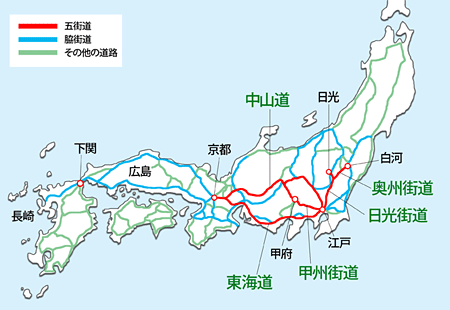
江戸幕府は、初代将軍の徳川家康以降、江戸と各地を結ぶ街道の整備を行いました。特に重要とされたのが、東海道、中山道、甲州街道、日光街道、奥州街道の五街道です。なかでも東海道は、天皇が住む京都と江戸とを結ぶ、最も重要な街道で、現在の東名高速道路や新東名高速道路のルーツといえます。
幕府が街道の整備を行った大きな理由は、諸国の大名に対する支配の強化です。幕府は、諸国の大名を一定期間、江戸と国元とに交互に住まわせる参勤交代の制度を取り入れ、整備された街道はそのための通り道となりました。国元と江戸を往復する費用が、各大名にとって大きな負担となって幕府に対抗する力が弱まり、反対に江戸幕府の力を強めるのに役立ったのです。
Q5
「東海道五十三次」の「五十三次」とは何のこと?
A.53の宿場
B.53日
C.53人
A5 正解は 「A.53の宿場」 です。
江戸時代に整備された五街道をはじめとする各街道にはいくつもの宿場が設けられ、荷物を運ぶ人や馬が置かれました。「東海道五十三次」とは、東海道に設けられた53の宿場を指す言葉です。当時は江戸の庶民の間で伊勢神宮(三重県伊勢市)に参拝する「お伊勢参り」がブームになっており、東海道はそのための交通手段としても利用されました。江戸時代の戯作者・十返舎一九の『東海道中膝栗毛』は、お伊勢参りを思い立った弥次さんと喜多さんが東海道を旅する姿をユーモラスに描いた話で、各宿場のにぎやかな様子が描かれています。
また、「東海道五十三次」は、江戸の絵師歌川広重(安藤広重)の作品の名称としても知られています。東海道の旅の際のスケッチをもとに描いた53の宿場と出発地(日本橋)、到着地(京都)にまつわる55枚の絵のシリーズで、当時の人々に大評判になっただけでなく、ゴッホなど海外の有名画家にも大きな影響を与えました。






















