「他の人の身になって考える」ってどんなこと!? 適性検査で役立つ「社会を見つめる力」
お気に入りに登録
■実際のデータで見る、サポートを必要とする人たち
それでは、高齢者や障がいのある人の数を見てみましょう。
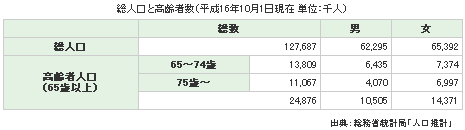
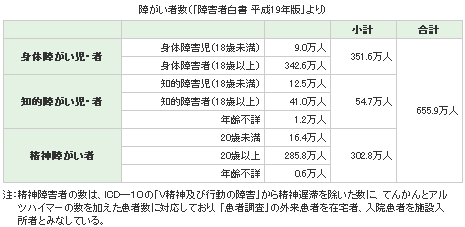
データによると65歳以上の高齢者は平成16年度で過去最高の約2488万人、実に日本の全人口の20%近くにもなっています。そのうち90歳以上のお年寄りがこの年、初めて100万人を超えました。
それでは障がいのある人たちのデータを見てみましょう。障がいのある人の数は約656万人。そのうち身体に障がいのある人たちはおよそ半分の約352万人に及びます。
お年寄りや障がいのある人たちは思うように動けないことも多いので、さまざまなサポートが必要です。そういう人たちに対し、地域に住む人々を含め、街ぐるみで配慮をしていくことが大切です。それこそが、もっか国を挙げて取り組んでいる「バリアフリー」の根幹をなす考え方だといえます。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 「他の人の身になって考える」ってどんなこと!? 適性検査で役立つ「社会を見つめる力」
- 少子高齢化と福祉を考える! 適性検査対策として今家庭でできることは?
- 「他の人の身になって考える」ってどんなこと!? 適性検査で役立つ「社会を見つめる力」
- 「他の人の身になって考える」ってどんなこと!? 適性検査で役立つ「社会を見つめる力」
- 少子高齢化と福祉を考える! 適性検査対策として今家庭でできることは?
- ニートやフリーターの増加問題、キャリア教育って?「働くこと」を切り口に、適性検査に役立つ力を身につける!
- ニートやフリーターの増加問題、キャリア教育って?「働くこと」を切り口に、適性検査に役立つ力を身につける!
- 今の小学生が社会人になったときに求められる力
- 子どもが新聞を読むことのメリット ネットニュースとはなにが違う?親子で新聞を読んで文章力を身につけよう























