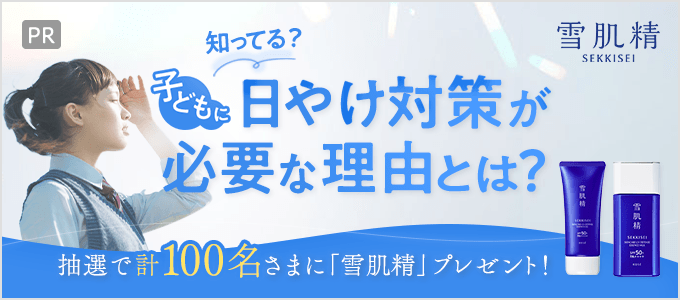第9回 「論理的思考力」とは何か
お気に入りに登録
これまでのコラムの中で、適性検査が求めている学力のコアは「論理的思考力」であり(第1回コラム参照)、また「抽象的論理思考」のできる子どもが偏差値上位校に合格する(第8回コラム参照)と述べてきました。しかし、その意味や内容には、あえてふれないできました。
そこで、これから数回にわたって「論理的思考力」とは何か、それを育てるにはどうすればよいのかについて説明していきます。ただ、その前にご注意いただきたいのは、私が「論理的思考力」をくり返し述べているからといって、感性の乏しい頭でっかちの子を育てるべきと考えているのでは、決してないということです。あくまでも一人ひとりの子どもが、親をはじめとした周囲の人々から愛情を注がれ、情緒が安定し、情操豊かに育つことをなによりも前提にしたうえでの論理性なのです。ともするとロゴス(論理的なもの)とパトス(感性的なもの)は対極にあるものとしてとらえられますが、こと子どもの学力育成に関しては、安定した情緒性の上に論理的思考力が築かれて初めて生かされるということを、どうか心に留めていただきたいと思います。
ところで「論理的思考力」という言葉を辞書で探そうとしても載っていません。
『広辞林』によると「論理的」とは「きちんと筋道を立てて考えるさま」、「思考力」とは「考える能力」と書かれています。それでは「筋道を立てて」「考える」とはどのように考えていくことでしょうか。また、「考える」とはいったい何をどうすることでしょうか。そして、大人社会で要求される「論理的思考」は、子どもにはどのように説明されるものなのでしょうか。改めて問い返してみると、何も明らかにされていないことに気がつきます。 論理的思考が職業上、特に要求される裁判官や弁護士、そして数学を教える教師に直接尋ねたことがありますが、それぞれの専門領域におけるそれを説明できたとしても、小学生に対して具体的にどう説明するのかと問うと、明確な答えが返ってきません。
論理的思考が職業上、特に要求される裁判官や弁護士、そして数学を教える教師に直接尋ねたことがありますが、それぞれの専門領域におけるそれを説明できたとしても、小学生に対して具体的にどう説明するのかと問うと、明確な答えが返ってきません。
私は、これからの国際化社会の中では、知識の量よりもそれをどう使うかという活用力、それも論理的思考力が重要であり、他者とのコミュニケーションを通して自分の考えや意見を論理的に述べて問題を解決していく力が求められると考えています。
「論理的思考力」とは、物事を比較分析して考察する力、知識や体験の引き出しから自由に出し入れして関連づけて判断し課題を解決する力、筋道を立てて論述する力、そして豊かな発想力など、これからの社会で生きていくために必要な、総合的な考える力ととらえています。小学生に対してより平易に説明するならば、【同じものや違いに着目して物事を区別し、あれとこれの関係やつながりがわかるように考えて判断し、さらに判断した根拠を明らかに示したうえで、相手にわかりやすく説明する力】だといえます。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 批判的思考力とは何か
- 【どうなる?どうする?娘の大学受験】第13回 進学先、決定?
- 『これからの幼児教育』2024度 春号 【特集】組織で積み上げる 園と保護者のコミュニケーション|これからの幼児教育
- 第81回 21世紀型能力の育成と評価 ~批判的思考~【前編】
- 【どうなる?どうする?娘の大学受験】第12回 合格発表
- 『これからの幼児教育』2024度 秋号 【特集】全国調査から見えてくる 保育の課題と未来へのヒント|これからの幼児教育
- 止まらない「いじめ」 先生たちの「感度」が働かない理由とは
- 進路が決まらない!そんな時に、高校生と保護者がやるべきこと【体験談あり】
- 『これからの幼児教育』2023度 冬号 【特集】保育者のメンタルヘルスを考える|これからの幼児教育