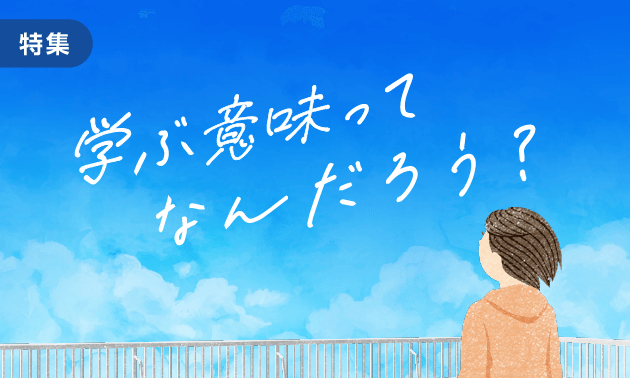科学技術と平和は両立できる?理系・文系を超えた先にある、社会科の学び【東京大学教授・横山広美さんに聞く】
- 学習

「なぜ、社会科を学ぶの?」お子さまからそんなふうに聞かれた時、どう答えていますか? ニュースを理解できるようになる、知識が増える……でも、その先は?
今回お話を聞いたのは、東京大学の横山広美教授。大学院までは物理学を研究しながら、常に「科学と社会の関係」に関心を持ち、現在は《理系出身の人文社会科学の研究者》として活動しています。理系と文系の垣根を超えた、これからの学びとは──。
社会を知ることで、社会に役立てる糸口を見つける
——横山さんは東京大学の理系の研究所で、文系の研究者として活躍されています。珍しいキャリアですが、そんな横山さんが考える、社会科を学ぶ意味は何ですか?
社会科での学びを通じて、自分の生きている社会を知ることは、生きていくのに必要なことですね。社会を知ることは、「社会における自分の役割を見つけること」にもつながります。
——もともと、物理学を勉強されていたと聞きました。どのように興味をもったのですか?
カトリックの学校に通っていて、神様はどうやってこの宇宙をつくったのか不思議に思っていたのですが、中学2年生の時に、物理学で宇宙の始まりを研究できることを知って大きなショックを受けました。1年で宇宙に関する本、70冊ほどに目を通して、ノートに書き留めたのは、楽しい思い出です。
——とてもアクティブに学ばれていたのですね。今はどういった研究をされているのですか?
科学と社会の関係を研究する「科学技術社会論」が専門です。AIや気候変動に関する倫理や、科学者の責任、そして理系に女性が少ない理由などです。この分野の研究につながる、私が高校生だった時に受けた記憶に残る授業があります。
——どのような授業だったのでしょう?
宗教の授業で、「世界には飢餓に苦しむ人がたくさんいるのに、なぜ莫大(ばくだい)なお金をかけて、宇宙開発をする必要があるのか」というテーマで議論をしたんです。簡単に答えが出せない質問で、真剣に悩んだ記憶があります。
——難しい問いですね……。
それに、物理学者たちがなぜ原子力爆弾を作ってしまったか、ということにも関心をもっていました。物理学を学ぶ上では当然かもしれません。今思えば早くから、科学と政治、社会の関係に関心があったのですね。科学と上手に付き合う方法を考え続けることで、社会をよくするために貢献したいですね。
——「社会をよくすることに貢献したい」、すごく明確な志ですね。
たまたまそうした分野であるからです。学問の価値は、直接的に私たちの暮らしに役立つためにするものばかりではないです。理系でも文系でも、学問の世界は広くて、真理の探究がめぐりめぐって人類の知識を積み上げています。お子さんや学生を相手に話す時は、「好きなこと、夢中になれることを見つけよう」とよく伝えています。その先に、社会の中での自分の役割を探すことができると思います。
理系・文系の壁に阻まれず、自由に学ぶ

——とはいえ、理系から文系の研究者になるのは大変そうですが、横山さんはどのように学んだのですか?
本や論文を読む、学生や研究仲間と議論する。これにつきますね。理系よりは徒弟制度によらずに、書かれたものから学べる点が、途中で専門を変更した私にとっては助かりました。
ただもともと、物理学という古典的な専門領域を深く学ばせていただいたことが、新しい領域を学ぶ際の足腰を鍛えてくれたと思っています。何か一つ、しっかりとした専門を学ぶことが大事だと思います。
——社会を学ぶことで、横山さんにはどんな変化がありましたか?
理系の場合は次々と問題をクリアしていくような研究スタイルでしたが、すぐに解決はできない難しい問題を、歴史を学びながら時間をかけて考えることに価値を感じるようになりました。そして、正しく筋の良い「リサーチクエスチョン」を立てることを心掛けるようになりました。
——リサーチクエスチョンとは?
研究を行う際に立てる「問い」です。研究者にとっては、生き方そのものにもかかわってくる問題ですね。
——どのように学んでいくと、よい問いを持てるようになるのでしょうか?
興味があることを見つけ、正しく学び、そして長く考え続ける時間があることが、良い問いを生み出すのに大事であると思います。正しく学ぶ、というのは難しいですが、要は古典的な考え方をしっかりと身に着けて、新しい問題に挑むということだと思います。
——現代の子どもの学びについて、重要な点は何でしょうか?
私の場合は、「なぜだろう」とぼんやり思い続けていた時間が長かったことが重要でした。だからこそ知った時の感動がすごく大きかったから。
ただ今のお子さんたちは、すごく忙しいことが心配ですね。ぼーっとする時間は限られているし、ネットで検索すれば簡単に答えもわかってしまいます。基礎力を高める勉強は大事ですが、興味をひきたてる出会いや、活動があるといいですね。
学びから、夢中や感動が生まれる
——今の時代に子どもたちが能動的に学ぶためには、どのような働きかけをしたらよいでしょうか?
身近なことからだと、本やテレビの特集、YouTubeも入り口としてはよいと思います。さらに言えば、興味から実際に動いて、体験することが大事だと思います。それが楽しいと感じると自ら学ぶ力になると思います。
学びは時に、夢中や感動をつくるもの。私も一人の教育者として、学びの楽しさを伝えていきたいです。
◆横山広美が考える、社会科を学ぶ意味
「自分の好きなことを生かして、社会の役に立つため」
- 社会を学ぶことで、自分の好きや得意なこととの接点を見つけられる
- 接点を見つけられると、それを仕事にできる
- 自分の居場所で社会の役に立つことが「働く」ということ
<文・飯室 佐世子>
- 学習