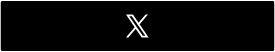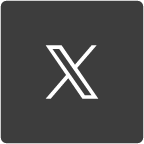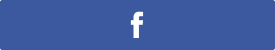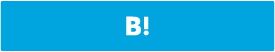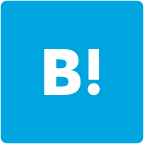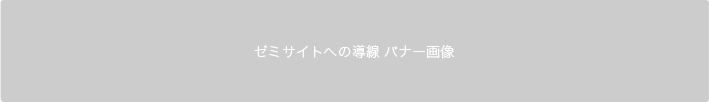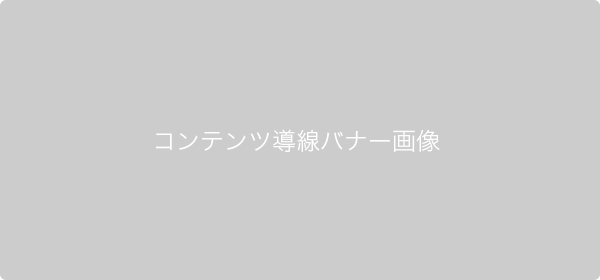教育現場にもっと脳科学の成果を 文科省協力者会議が提言-斎藤剛史-
お気に入りに登録
 最近の脳科学の発達には、驚くべきものがあります。しかし、それがどれだけ学校や家庭で活用されているでしょうか。文部科学省の調査研究協力者会議は、子どもの感情の動きである「情動」に関する脳科学などの科学的研究成果を集めて、いじめなどの問題行動について研究者らと学校教育関係者らが協力して取り組む体制をつくるよう提言しました。近い将来、脳科学の発達が学校の生徒指導を変えることになるかもしれません。
最近の脳科学の発達には、驚くべきものがあります。しかし、それがどれだけ学校や家庭で活用されているでしょうか。文部科学省の調査研究協力者会議は、子どもの感情の動きである「情動」に関する脳科学などの科学的研究成果を集めて、いじめなどの問題行動について研究者らと学校教育関係者らが協力して取り組む体制をつくるよう提言しました。近い将来、脳科学の発達が学校の生徒指導を変えることになるかもしれません。
いじめ・校内暴力などの問題行動は、現在の学校教育の中でも大きな課題です。しかし、しつけなど家庭環境の変化、児童虐待の増加など、社会が急激に変化しているにもかかわらず、学校の生徒指導は基本的にあまり変化していないように見えます。言い換えれば、こういう場合はこういう原因があった、こういうケースにはこんな対応で効果があったというような経験則の積み重ねが、現在の生徒指導の多くを占めています。
一方、最近の脳科学では、家庭環境や人間環境のストレスが子どもの脳にどのような影響を及ぼすのかという研究が進んでいます。ストレスについても、それを取り除くだけではなく、「レジリエンス」(ストレスからの回復力)という考え方が重視されるようになってきました。問題行動について脳科学者らの多くは、子どもたちの「レジリエンス」を育成することが必要だと主張しています。ストレスを回避したり、我慢したりするのではなく、ストレスからいかに立ち直るかが大切だということでしょうか。
ところが、このような研究成果のほとんどは、専門の研究者らの間だけにとどまり、教育関係者や一般の保護者にはなかなか届かないのが実情です。このため協力者会議は、子どもや家庭が多様化し、いじめ問題なども複雑化しているのに対して、科学的研究成果が学校の生徒指導の中で体系的に生かされていないと指摘したうえで、最新の脳科学の研究成果を生徒指導に活用すべきだとする報告書をまとめました。
具体的には、国立教育政策研究所に「情動研究・教育センター(仮称)」を設置し、子どもに関する科学的研究成果を集めて、それをデータベース化したり、研究者と教育関係者が共同研究したりすることで、脳科学などの最新の成果を学校で応用できるようにすべきだと提案しています。また協力者会議は、教育現場のニーズを研究者が受け止めることで、自然科学と教育の連携を図ることも求めています。
子どもの脳などの科学的知見が生徒指導などで活用できるようになれば、教員の経験に頼ってきた問題行動などへの対応も大きく変わりそうです。