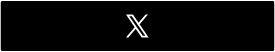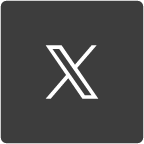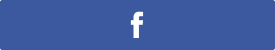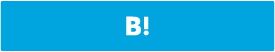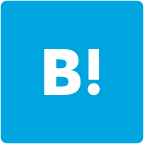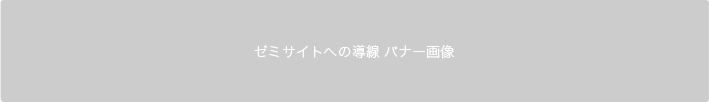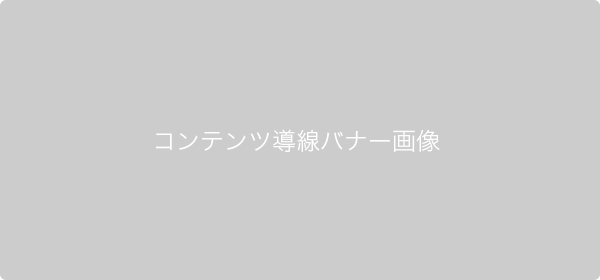先生の若返りは進むけれど……学校が抱える「年齢構成」問題-斎藤剛史-
お気に入りに登録
 文部科学省が発表した2013(平成25)年度「学校教員統計調査」(中間報告)の結果、国公私立学校全体の教員の平均年齢が下がっていることがわかりました。これまで教員平均年齢は上昇傾向を続けていましたが、いよいよ若返りに転じたようです。先生全体の若返りは、子どもたちの教育にも少なからず影響があるようです。
文部科学省が発表した2013(平成25)年度「学校教員統計調査」(中間報告)の結果、国公私立学校全体の教員の平均年齢が下がっていることがわかりました。これまで教員平均年齢は上昇傾向を続けていましたが、いよいよ若返りに転じたようです。先生全体の若返りは、子どもたちの教育にも少なからず影響があるようです。
調査は3年ごとに実施しているもので、2013(平成25)年10月1日現在、非常勤や臨時任用などを除く本務教員の平均年齢は、公立幼稚園が41.6歳(前回調査の2010<平成22>年度は42.4歳)、私立幼稚園が34.7歳(同33.9歳)、公立小学校が44.0歳(同44.4歳)、公立中学校が44.1歳(同44.2歳)、公立高校が45.8歳(同45.8歳)、私立高校が44.1歳(同44.4歳)となっています。私立幼稚園はやや上昇していますが、小学校と中学校は低下、高校も公立は前回と同じですが、公私立全体では平均年齢が低下しました。小学校から高校までのすべての学校段階で平均年齢が下がったのは1977(昭和52)年度の調査開始以来、初めてです。
現在、新規採用教員数は増加しているため、これからどんどん教員の平均年齢は若返っていくと思われます。しかし、教育関係者などの間では学校教育への影響を懸念する声があります。一体、どういうことなのでしょうか。
問題は、平均年齢の低下自体ではなく、教員年齢構成の不均衡にあります。第2次ベビーブーム世代が学齢期に達した1980年前後、児童生徒の増加に対応するため大量の教員が採用されました。この大量採用層がずっと教員平均年齢を押し上げてきたのですが、現在この層が定年退職時期を迎えており、その穴埋めのため新規採用者が大幅に増えています。つまり小学校から高校の教員は、大量採用の分厚い50代のベテラン層、そのあおりで極端に数が少ない40代と30代後半の中堅層、再び増えている30代前半から20代の若手層という「ひょうたん型」のアンバランスな構成になっているのです。
民間企業も含めて組織の中堅層には、業務の実質的中心を担うだけでなく、世代間ギャップの大きいベテランと若手の間を仲介する役割があります。ところが学校現場では、中堅層が主任クラスになって非常に多忙なうえに数が少ないため、若手の面倒を見たり、ベテランと若手の橋渡しをしたりすることに手が回らず、その結果、「若手教員の孤立」という状況が一部で起きているとも指摘されています。
また指導力のある教員は、視線やしぐさだけで騒いでいる子どもたちを鎮めることができますが、このような指導技術はある意味「職人技」とも言えます。講義などで伝えることは難しく、現場の長い経験の中で上から下の世代へと受け継がれていくような種類の技術です。しかし、ベテラン層の一斉退職により、これらの日常的な指導技術が若手教員に継承されないまま、失われる可能性があると教育関係者の間で懸念され始めています。
教員平均年齢の若返りの裏側には、このような課題があることを知っておくことも大切でしょう。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 解消されない先生の多忙化…「教育の質」も心配
- 多様性社会で特に身につけたいのは「共感力」。 どう伸ばせばいい?ボーク重子さんに聞く! これからの子どもを幸せにする「非認知能力」の育み方~Lesson3 共感力
- 自由研究のテーマが見つかる!~天動説と地動説について調べる~
- 小学校で理科の「専科教員」増える理由 教員の理科への苦手意識
- 好奇心は親が子どもの手本になることで育つ ボーク重子さんに聞く!これからの子どもを幸せにする「非認知能力」の育み方 ~Lesson8 好奇心
- 自由研究のテーマが見つかる!~水の硬度とお茶~
- 一生学び続け、社会で活用を e-ラーニングや大学の「学び直し」も‐渡辺敦司‐
- 非認知能力で最重要!「自己肯定感」を育むために、親が知っておきたいこととは?[ボーク重子さんに聞く]
- 自由研究のテーマが見つかる!~手作り発泡入浴剤~