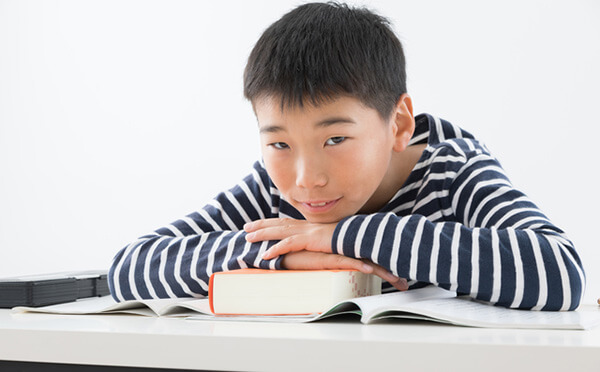自学自習の力を育む「辞書引き学習法」、家庭でのコツは?
お気に入りに登録
 辞書を引いて、知っている言葉に付せんを貼る「辞書引き学習法」をご存じだろうか。中部大学准教授の深谷圭助氏が開発・提唱するこの学習法は、子どもたちの言葉への関心を高め、自学自習の力を育むことから、現在、多くの小学校でも導入されている。「辞書引き学習法」を家庭で実践する時のコツを、深谷氏に伺った。
辞書を引いて、知っている言葉に付せんを貼る「辞書引き学習法」をご存じだろうか。中部大学准教授の深谷圭助氏が開発・提唱するこの学習法は、子どもたちの言葉への関心を高め、自学自習の力を育むことから、現在、多くの小学校でも導入されている。「辞書引き学習法」を家庭で実践する時のコツを、深谷氏に伺った。
***
辞書引き学習法を継続させるには、まず辞書を気軽に手にとれる環境にしてあげることが大切です。ブックカバーは外して、鉛筆と付せんを近くに置き、いつでも引けるようにしておきましょう。
辞書に貼ってある付せんが増えてきたら「付せんが増えてきたね」「よく知っているね」などとほめてあげてください。「面白い言葉はあった?」と、辞書引き学習法を話題に出してあげるのもよいですね。
まず、第1段階として3か月で付せん1,000枚を目指しましょう。辞書の中から知っている言葉を見つけるなかで、自分にとって面白い言葉に出会うことが目標です。この言葉との出会いが、「もっと調べてみたい」という原動力になります。
ここで、保護者のかたに注意していただきたいのは、「意味を読みなさいと言わない」こと。付せんを貼るだけでは効果がないと思われるかもしれませんが、たくさんの言葉に触れていくうちに、子どもが自ら言葉の意味に興味を持つようになっていきます。その時まで、保護者のかたは温かく見守ってあげてください。
子どもにとっては、自分で調べて、面白い言葉に出会ったという喜びが、次の言葉を調べたくなる原動力になります。この喜びは、ほかの教科の勉強においても自然と応用されるはずです。たとえば、虫を観察していて気付いたことを昆虫図鑑で調べるなど、生活のいろいろな場面での気付きや疑問を、自分で解決してみたいと思うようになるのです。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 国語力って何?大人にも重要な国語力を子どものうちに伸ばす勉強法4選
- 辞書引きを面倒がる子ども 興味を持たせるには
- 第1志望大現役不合格者が後悔している4つのこと
- 小学生の読書量と国語の学力、どれくらい関係する? 学力を伸ばすだけでなく、心の安定にも効果あり?!
- 【どうなる?どうする?娘の大学受験】第11回 国立大本番でのハプニング!
- 【2025年度入試】大学入試の基礎知識 「大学入学共通テスト」とは?日程・時間割などを解説!
- 【どうなる?どうする?娘の大学受験】第6回 併願大、決定!
- 「理性」と「感性」を生かして国語力を養う[2012年度入試で何が問われたか<国語> 「理性」と「感性」に注目して国語力を上げる 第3回]
- 【どうなる?どうする?娘の大学受験】第12回 合格発表