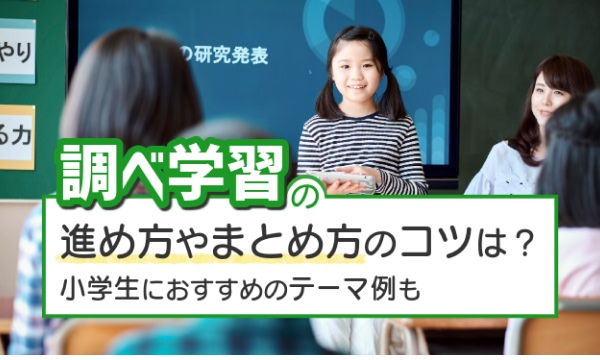東京の伝統工芸「江戸切子」について<調べ学習:まとめ方>
お気に入りに登録
取材する
いよいよ取材当日です。メモ帳や筆記用具はもちろん、スケッチブックやデジタルカメラなども用意するとよいでしょう。また、立ち入ったり触ったりしてはいけない所など、注意事項はしっかり聞いて守りましょう。
江戸切子の場合の取材項目はこんな感じです。
| ●伝統工芸の歴史について: | 江戸切子はいつごろからつくられ始めたのか? |
| なぜ、この地域で受け継がれているのか? |
●江戸切子の特徴:いちばんの特徴は何か? 他のガラス製品とどこが違うのか?
●江戸切子の種類について:色や柄、形、大きさなど
| ●道具や材料について: | 削ったり磨いたりするのに、どんなものを使うのか? |
| 昔と今とでは違うのか、同じなのか? |
●工程について:江戸切子はどのように作られるのか?
以上のような内容は、事前の下調べである程度わかることでもありますが、種類などは実際に見せていただくことで、より理解が深まるでしょう。また取材させていただけるのが実際の職人さんだったら、次のようなことも聞いてみてはいかがでしょうか?
●何歳からこの仕事を始めたのか、職人歴は何年か?
●どのくらい、どんな修行をしたか? 修行で大変だったことは何か?
●江戸切子をつくるうえで、難しいところ、工夫するところはどこか?
●江戸切子の職人として、やりがいは?
●これからどんな江戸切子を作っていきたいか?
わたしが江戸切子を取材させていただいたときは、職人歴60年のかたとお話しすることができました。切子の作業は水を使うので、エアコンのなかったころの冬場の仕事は本当につらかったそうです。現在は工場長という立場になっていらっしゃいましたが、今も、「これまでの中で一番良いものを」と切子づくりに取り組んでいらっしゃいました。そうした生のお話から受ける感動が、何よりの自由研究になるでしょう。
実際に体験する
江戸切子の工房では、ペーパーウエートなど簡単なものを体験させてくれるところもあります。実際にやってみることで、職人ワザのすごさを改めて実感することができます。
まとめ
取材から帰ったら、すぐにまとめ始めましょう。お伺いした話、スケッチしてきた絵、撮ってきた写真などを整理して、どうすれば取材の内容をわかりやすく伝えられるか考えてみましょう。
※江戸切子の自由研究の例はこちら(PDFファイル)※PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。
![]()
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 東京の伝統工芸「江戸切子」について<調べ学習:まとめ方>
- 子ども時代から必要な「がんの教育」‐渡辺敦司‐
- いつもどこか間違える?! ひらがなをきちんと覚えてもらうための対策
- 小学生の「調べ学習」 宿題に出たけどテーマの決め方やまとめ方がわからない…家庭でどうフォローする?
- 「アクティブ・ラーニング」時代の教員養成とは‐渡辺敦司‐
- 4年目を終えた大学入学共通テストの傾向と対策【まとめ】
- 調べ学習の進め方やまとめ方のコツは?小学生におすすめのテーマ例も
- 学びを深め、人と人とのつながりを広げる「教育」へのタブレット導入 ‐渡辺敦司‐
- 学校貸与の一人一台タブレット、家庭での付き合い方と活用方法を考える