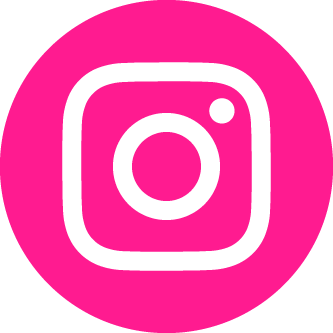親野先生に聞いた!ポジティブな夏休みの迎え方~どんな1学期だったとしても子どもは頑張っていた
- 育児・子育て
1学期の終わりは、それまでの成果を振り返り、次の目標を立てる絶好の機会。とはいえ、振り返り方によっては、自信をなくしたりやる気を落としてしまうこともあるようです。どんなときにも役立つ、振り返りと目標の立て方とは? 教育情報サイトでもお馴染みの教育評論家、親野智可等先生にうかがいました。

どんな1学期だったとしても子どもは頑張っていた
入学はもちろん、進級でも1学期はなにかしらの環境の変化があるものです。先生や友だちとの関係、授業のレベルアップ、上級生になればそのプレッシャーを感じることもあるでしょう。いずれにしても4月からの4か月、子どもはそれぞれの環境で頑張ってきたのです。そう思うと、まずは「よく頑張ったじゃない」と、ねぎらってあげたくなりますね。
当たり前のようですが、誰でもほめられれば嬉しいですし、自信がもてます。でも、これが意外と難しいもので、例えば通知表をもらうと、ついできていないところに目が向いて「ここがダメじゃない」「もっと頑張らないと」などと言ってしまうこともあります。一番よくないのは他の子ども、特にきょうだいと比べて評価することです。「お兄ちゃんはちゃんとしているのに」「妹くらいやってくれたら」などというのは、子どもにとっては本当にがっかりする言葉ですし、やる気もしぼんでしまいます。
1学期の終わりは、子どもを否定してがっかりさせる機会ではなく、ほめるためのチャンスにしましょう。通知表の評価だけでなく、例えば、元気よく遊べたとか、ペットの世話がしっかりできたとか、サッカーの練習を頑張ったなども十分立派なことです。子ども自身が頑張った、よかったと思っていることがあれば、「本当にそうだね!」と共感を。また、子どもが通知表の結果にがっかりしているときこそ親の出番。「でも、あなたにはこんなにいいところがあるよ」「私はここを評価しているよ」と伝えて自信を回復してあげましょう。
言葉が変わると前向きになる!
ほめることは子どもに自信をもたせるだけでなく、親への信頼感を高めます。親への信頼感は、周りのすべての人への信頼感の土台になる大切なもの。大袈裟なようですが、親のほめ言葉というのは、子どもの人生の支えになる重要なものだといえるでしょう。
では、ほめたい気持ちはあるけれど言葉が出てこないというときは、どうすればいいでしょうか。子どもをほめられるかどうかは、子どもではなく親次第です。例えば「いつもふざけてばかりいる」子は「明るくて何でも面白がれる」子とも言えます。「引っ込み思案」も「慎重」や「しっかり観察している」子かもしれません。見方によって、個性は短所にも長所にも見える。そう考えると、ほめるところがない子というのは、いないのです。
こうした言い換えを「リフレーミング」と言います。最初に感じる「ふざける」「引っ込み思案」という見方は親の理想と違うことから生じるマイナスの印象です。その見方(フレーム)をやめて、新たな視点から見直すことがリフレーミングです。
困ったな、心配だなと思ったら、リフレーミングを意識してみてください。パパッと言い換えるのが難しいときは、短所と思えることを書き出して、長所への言い換えをゆっくり考えてみてもいいでしょう。次第にプラスにとらえるのが上手になっていくと思います。
リフレーミングに限らず、よいところを書き出してみるというのは効果的です。その場で結果をほめることはできても、いつまでも覚えているのは難しいもの。1学期のできごとを思い出しておうちのかたが嬉しかったことや、お子さまが頑張ったことを書き出してもいいですし、日々の様子から「よく笑う」「絵を描くのが好き」「歌がうまい」などの個性を書いてもいいでしょう。思いつくだけ書き出して、それを子どもに伝えてください。
言葉にすると、親も改めて子どもの良さに気づきますし、子ども自身も自分にいいイメージをもつことができます。
なぜ「最初にほめる」とうまくいくのか
どんな場面でもいえることですが、まず最初にほめることが大事です。ほめられると、子どもは前向きな気持ちになります。例えば漢字の練習をしているとき、全体に見るとバランスが悪かったり乱雑だったりしても、その中で比較的よく書けている字を見つけます。そして「これは、ていねいに書けていていいね」「このはらいはカッコいいね」などとほめてみます。すると、次に書くときに「今度もしっかり書こう」と自分から意識するようになります。
算数で間違えがあったときも、「計算は間違っちゃったけど、解き方は合ってたね! 算数が得意だね!」など、肯定的に言いましょう。すると、自分は算数は得意なんだとやる気が出て、次は計算も注意するようになります。
夏休みの目標を立てるときも、先にほめるところを見つけて、「もう少し頑張るともっと良くなる」と思えるようにできるといいですね。勉強でも、生活習慣や新しいチャレンジでも、子どもが「とてもできそうにない」と感じるような大きな目標や、「できないから、できるようにする」という苦手意識からのスタートばかりでは、心の負担が大きくなってしまいます。反対に、「今これができているから、きっとできる」と思えれば、前向きに向かっていけるはずです。
最後になりますが、そもそも「夏休み」は「休み」なのですから、休むことが本来の意義であるはずです。子どもらしいのびのびした気持ちの中でいろいろな体験ができれば、子どもはその中でたくさんの学びに出会うでしょう。目標が思うように達成できなくても「でもこれはできている」「でも楽しめているからいいか」とおうちのかたが柔軟に見方を変えて前向きに過ごしてください。
そして2学期のはじめには、また夏休みを振り返り、たっぷりほめてあげられるといいですね。
まとめ & 実践 TIPS
まず、ほめられるところを見つけてたっぷりほめる。課題については、達成できそうなところから少しずつ乗り越えていく。このように声かけの順番と課題の設定に気を配れば、ゆっくりでも着実に伸びていくことができます。すべての始まりは、親の前向きな受け止めから。
さっそくお子さまへのほめ言葉を見つけて伝えてみませんか?
- 育児・子育て