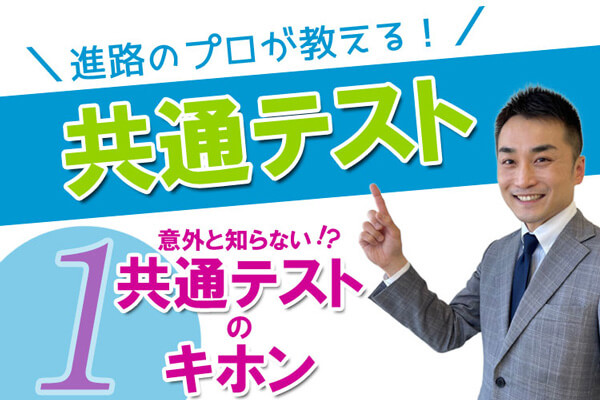受験を迎える子どもに声をかけるべき? そっとしておくべき?
お気に入りに登録
中学受験、高校受験を控え、家庭全体がぴりぴりしているような気がする…そんなふうに感じている保護者のかたも多いかと思います。そうなると、なんとか声をかけて少しでも雰囲気をよくし、受験に向かう子どもの背中をうまく押してあげたいところ…。しかし、それは本当に子どものためになり、家庭の雰囲気を変えてくれるのでしょうか? 受験前の子どもへの声かけについて考えてみましょう。

どんどん声をかけることだけがベストではない
まず、ふだんどんなふうにお子さまに話しかけているのかを考えてみましょう。「会話がないとなんだか気まずいから」と、あまり深く考えずに「がんばれ」「大丈夫なの?」などと言ってしまっているかもしれません。
実は、受験生には積極的に声をかけることは必ずしもいいとは言えない場合もあります。子どもの性格にもよりますが、幼稚園・保育園時代や小学校低学年時代とは違い、会話が少ないことが「なんとなく寂しい」という感情に直結してないことも多いからです。ひとりでじっくり考えているときは、むやみな声かけは必要ありません。
大切なのは受験生の様子を見ること、彼らの話を聞くこと。頻繁に受験について話したり、様子を探るような、あるいは腫れ物に触るような話し方になってしまったりするようであれば、いっそのこと「黙って見守る」ようにしましょう。
「言わなければ動けない」というタイプの子どもの場合には
昔から声がけが必要なお子さまであったり、声がけが減ることでお子さまの行動に悪影響が見られるようであったりするのなら、言葉や言い方を選んで声をかけてみましょう。一番よくないのは見たままで判断してそれについて注意することです。
例えば、テレビをみている=勉強をさぼっている、と決めつけてしまってはいないでしょうか。勉強がはかどっていないと一方的に判断し、「どうして勉強していないの?ちゃんと勉強しなさい」と声がけを続けてしてしまうと、親子関係が悪化してしまいかねません。テレビを見ている時間が長いな、と思ったら、そのまま「テレビを見ている時間が長いみたいだけど、どう?」など、今の状況に気づかせるような声がけをしてみてください。子ども自身も考えて行動しているという前提で、言葉を選ぶのです。「休憩時間?勉強の前に(部屋に戻る前に)何か食べる?」などの言い方もおすすめです。
どんな言い方もあまり繰り返すと嫌味になってしまうので要注意。ですが、適度にということであれば、子どもも時計を見たり、われに返ったりもするでしょう。いきなり「もう勉強しなさい」と言うよりずっと子ども自身に判断を任せることになり、自発的に動くきっかけをつくることになります。
親は「過大評価」するくらいがちょうどいい
なんでもかんでもほめればいい、ということではありませんが、学習については「過大評価」で構いません。「もっとがんばれ」「もっと勉強時間を増やしたほうがいいのではないか」といったことは、既に学校でも言われており自覚もあるため、親が追い打ちをかけて言う必要はないのです。
それよりも、「最近勉強集中できている感じだね」とプラスの言葉を投げかけるようにしましょう。もちろん、学校の先生からの忠告があれば真摯に受け止め、それについて話し合う時間も必要ですが、あくまでもその内容を毎日、ずっと引っ張ってしまわないように気をつけなければなりません。
また、言ってしまいがちなのが、模試や成績の結果だけを見ての「あなたは国語が苦手だからがんばれ」といった内容のことです。このような声がけはあまりにも具体性に乏しく、本人も既にわかっていることであるため意味がありません。そこを指摘するのではなく、少しでもいい点数が取れたり、その教科を勉強している様子が少しでもあったりするのなら、「最近この教科が得意になってきたんじゃない?」など、高く評価してあげてください。
「ほどよく関わる距離感」で過ごしやすい環境づくりを
気を遣いすぎるのもよくありません。しかし、親が自分の心配をそのまま言葉にすれば、子どもを不必要に追い詰めてしまいます。「ほどよく関わる距離感」を意識し、子どもの自主性を伸ばすよう心がけましょう。重要なのは受験というひとつのハードルを越えることではなく、その先に続くハードルを自分自身で超え続けることなのです。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 高校入試の過去問 いつから?何年分?効果的な解き方は? 併願校の過去問対策も【高校受験】
- 「英語が好き」な小学生、得意をもっと伸ばす方法とは?
- 朝のバタバタは、子どもの段取り、親のフォローを変えるとうまくいく!
- 夏休みの宿題には何がある?その目的とは?保護者のサポート方法も紹介
- 好きな映画で英語耳が育つ?リスニングの力が身につく映画の選び方
- 読書感想文を通じて読解力を鍛えられる?!国語のカリスマ受験コーチがオススメする1冊と、読書とのつきあい方
- 理科が苦手な子ども、家庭でどうフォローする? 原因別に考える家庭学習のコツとは
- 小学生の保護者約2,000名に学ぶ!子どもが英語好きになるアイディア
- 反抗期?低学年の口ごたえは「自立」のための大切なステップ【後編】